食事はただ日々の栄養補給をするだけではなく、人との交流を楽しむ場としても重要です。ですが「会食恐怖症」に悩む人にとっては、強い不安と恐怖を感じる場となってしまいます。
会食恐怖症は、他人と一緒に食事をする場面で強い恐怖や不安を感じる精神的な疾患で、人前での食事に対する強い羞恥心や、自分の食べ方が相手に見られることへの恐れなどが背景にあります。
要因としては、幼少期の家庭環境や、過度の注目が集まる経験など、さまざまなことが影響しています。
この記事では、会食恐怖症の定義や特徴、原因、症状、診断、克服方法、支援制度について詳しく解説します。
会食の不安から解放されるための道筋を知ってもらい、一人でも多くの人の生活の質の向上につなげていければと思います。
会食恐怖症とは何か?

「会食恐怖症」の名の通り、食事の場面での出来事だと予想はできると思います。
では、実際の症状はどのようなものなのでしょうか?
会食恐怖症の定義と特徴
会食恐怖症とは、他人と食事をする場面に対して過剰な恐怖や不安を抱く状態です。
「自分の食べ方が変に見えるのでは」「食事中の態度が批判されるのでは」といった具体的な不安が伴い、動悸や発汗、震え、嘔吐などの身体症状が現れることもあります。
これは単なる「人見知り」や「社交不安」とは異なり、食事の場に特化したものです。
恐怖が過剰であると自覚していても制御が難しく、食事の場を避けることで孤独感や社会生活への支障を招くこともあります。
会食恐怖症の背景にある原因
会食恐怖症の背景にある原因しては、以下のようなものがあげられます。
- 幼少期の経験
- 家庭内での厳しいしつけ
- 学校での給食指導
- 性格的な要因
- 他人の評価に敏感な性格
「きちんと食べなければならない」「マナーを守らなければならない」と考えすぎる完璧主義な性格
- SNSの普及による不安の増加
- 食事風景を撮影・SNSにアップされるリスクへの不安
理想的な食事シーンの発信によるプレッシャー
- 状況や相手による違い
- 家族との食事は問題なく過ごせるが、初対面の人がいる場面では強い恐怖を感じることがある
会食恐怖症の症状

会食恐怖症の症状は、身体的なものと精神的なものに大きく分けられます。
身体的な症状
身体的な症状としては、主に以下のようなものが上げられます。
- 主な症状
- 動悸
- 発汗
- 吐き気
- 震え
- 嚥下障害(飲み込みづらさ)
主な原因として、緊張や不安が高まることで自律神経が乱れ、これらの症状が現れます。特に吐き気や嚥下障害は食事を困難にし、食事そのものへの恐怖感をさらに強める悪循環を生み出してしまいます。
精神的な症状
精神的な症状も会食恐怖症の人にとっては大きな問題となります。
- 主な症状
- 人前で食事をすることへの強い羞恥心や不安
- 食事の場を避けようとする回避行動
自己嫌悪や劣等感精神的な症状の要因しては、「自分の行動が注目されているのではないか」「批判されているかもしれない」といった過剰な意識が原因といえるでしょう。この精神的負担は、単に会食を避けるだけでなく、日常生活全体にも悪影響を及ぼすことがあるという面も問題視されています。
身体的・精神的な症状が複雑に絡み合うことで、会食恐怖症は日常生活に大きな支障をきたすことがあるため、適切な理解と対応が必要です。
会食恐怖症の診断方法

適切な診断と専門的なケアを受けることで、会食恐怖症は改善の糸口を見出せる可能性があります。
会食恐怖症の診断と治療法
会食恐怖症かな?と不安を感じたら、まずは専門機関に相談することから始めることが重要です。
自分だけで判断せずに、不安であれば診断を受けるようにしましょう。
診断の流れ
相談先としては、精神科や心療内科の専門医に相談することが重要となります。
診断の基準は、以下の通りです。
- 強い不安感
- 避ける行動
- 身体的な症状
- 6カ月以上の持続
- 重大なストレスや機能の低下
- 他の精神疾患や身体的な問題が関係していない
主な治療法
会食恐怖症の治療法には、主に2つの治療方法があります。
- 認知行動療法(CBT)
- 目的:会食への不安や恐怖を引き起こす思考パターンを見直し、現実的で柔軟な考え方を身につける。
- 具体的なアプローチ:
- 徐々に他人と食事をする機会を増やす段階的な練習。
- 成功体験を積み重ね、不安感を軽減する。
- 薬物療法(補助的な治療法)
- 使用される薬:
- 不安を和らげる抗不安薬
- 気分を安定させる抗うつ薬
- 注意点:薬物療法は症状の緩和を目的とした補助的なものなので、根本的な解決には心理療法やカウンセリングが重要。
- 使用される薬:
会食恐怖症の治療には時間がかかります。
最初は少しずつ慣れていく必要があり、薬物などの緩和措置などと組み合わせて、長い目で見ていく必要があるでしょう。
会食恐怖症の克服に役立つ日常の対策
病院などでの治療などに加えて、自分でも会食恐怖症に対するアプローチ方法がいくつか存在します。
すぐに会食恐怖症が治るといったものではありませんが、覚えておくだけで負担が和らぎます。
1. 緊張感を和らげるリラクゼーション法
会食時の不安から、自律神経に悪影響を及ぼしてしまいます。そのため、食事前に自分にあったリラクゼーション法を試してみてはいがかでしょうか?
簡単にできるリラクゼーション法を3つ紹介します。
- 深呼吸
ゆっくりとした呼吸で心拍数を落ち着かせ、リラックス効果を高めます。 - 瞑想
短時間でも意識を内側に向けることで、不安感を和らげます。 - 筋弛緩法
体の特定の筋肉を緊張させてから緩めることで、全身の緊張をほぐします。
2. 少しずつ段階的に挑戦する
会食恐怖症の治療には長い時間がかかります。いきなり治そうとするのではなく、まず以下のようなスモールステップから試してみましょう。
- 家族や親しい友人との食事からスタート
知らない人との食事ではどうしても緊張してしまいます。まずは親しい間柄の人と、できれば個室などの他の人目のない場所からチャレンジしてみるとよいでしょう。 - 徐々にハードルを上げる
身近な人との食事に慣れてきたら、職場の同僚とのランチや少人数の食事会に挑戦していきましょう。この時無理をしては逆効果になるので、一緒に食事にいく同僚などには事情を伝えておきます。 - 自分のペースを尊重する
何度も言う通り、会食恐怖症の治療には時間がかかります。無理をせず、成功体験を少しずつ積み重ねることが重要です。
3. 信頼できる人に悩みを話す
治療には専門家のアドバイスがとても重要ですが、周りの人の理解がないと続けていくことは困難です。
一人で悩むことで、精神的に落ち込むという悪循環に陥ってしまいます。まずは親しい人と悩みを共有することで、気持ちが楽になり孤独感も和らげることが必要です。また、周りの人にも自分の状況を知ってもらうことで、無理のないサポートを受けやすくなります。
日常の小さな工夫を積み重ねることで、少しずつ不安を克服し、自信を取り戻すことができます。
会食恐怖症に悩む人のための支援制度

会食恐怖症の克服には、専門家による治療だけでなく、公的な支援制度や地域のサービスを活用することが重要です。適切なサポートを受けることで、症状の改善や社会復帰への一歩を踏み出すことができます。
1. 医療機関や地域の専門相談窓口
精神科などの医療機関などの他に、公的支援がいくつかあります。どのような支援があるかは地域によって変わってきますので、まずは役所や公的機関に問い合わせて聞いてみることをおすすめします。
- 精神科・心療内科での診療
医師や臨床心理士によるカウンセリングや診断、治療を受けられます。 - 地域保健センターや専門相談窓口
地域によっては無料相談が可能な窓口もあり、経済的な負担を抑えながら支援を受けることができます。 - 精神保健福祉センター
精神的な不安や悩みについて総合的な相談ができ、適切な支援先の紹介も行っています。
2. 支援団体やピア・サポート活動
公的機関での支援の他に、同じ悩みを持つグループの集まりや、民間の支援団体などもあります。
当事者でしかわからない悩みの共有や、最新情報などが得られるなど数多くの利点がありますので利用してはいかがでしょうか?
- 会食恐怖症克服支援団体
例:「日本会食恐怖症克服支援協会」では、情報提供や当事者同士の交流イベントなどを実施しています。 - ピア・サポートグループ
同じ経験を持つ人同士で励まし合うことで、安心感や共感を得ることができます。
3. 教育現場での支援体制
小中学校のような教育現場では、給食のように集団で食事をする機会が多くあります。会食恐怖症になってしまうと、不登校などの問題に発展してしまう可能性もあるので、学校側との連携は必要不可欠です。
- スクールカウンセラーとの面談
子どもが会食恐怖症になってしまった場合、どうしていいか親の方もわからないことが多くあります。その場合、学校内のカウンセリングで、不安や悩みを気軽に相談して対策を考えるなどをすることが重要になります。 - 教師や保護者との連携
会食恐怖症の克服には、周りの理解が不可欠です。家庭と学校が協力してサポート体制を整えることで、早期の対応が可能になります。
- いじめ・不登校相談窓口
会食恐怖症が学校生活に影響を与えている場合、関連する支援窓口を活用することも有効です。
このような支援制度を活用することが会食恐怖症の改善だけでなく、社会復帰への第一歩となります。
「一人で抱え込まず、まずは相談すること」が解決への重要なステップ。勇気を出して一歩を踏み出すことで、新しい可能性が広がるでしょう。
会食恐怖症と向き合うために

会食恐怖症は、一見すると単なる「緊張しやすさ」と誤解されがちですが、その背景には深刻な精神的な苦痛が隠れています。しかし、適切な治療と周囲のサポート、そして本人の努力次第で改善は可能です。
大切なのは、一歩ずつ進むことです。小さな成功体験を積み重ねることで、食事に対する恐怖心を少しずつ和らげていきましょう。
食事はただ栄養を摂取するだけでなく、人とのつながりを深める貴重な時間でもあります。その喜びを再び感じられる日が訪れることを心から願っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- すべての家族に”写真を撮る喜び”を 医療的ケア児・発達障害児にも寄り添う写真館 - 2026年1月20日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【後編】 - 2026年1月12日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【前編】 - 2026年1月11日

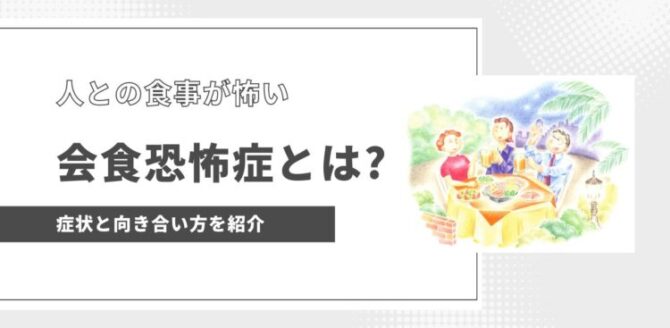

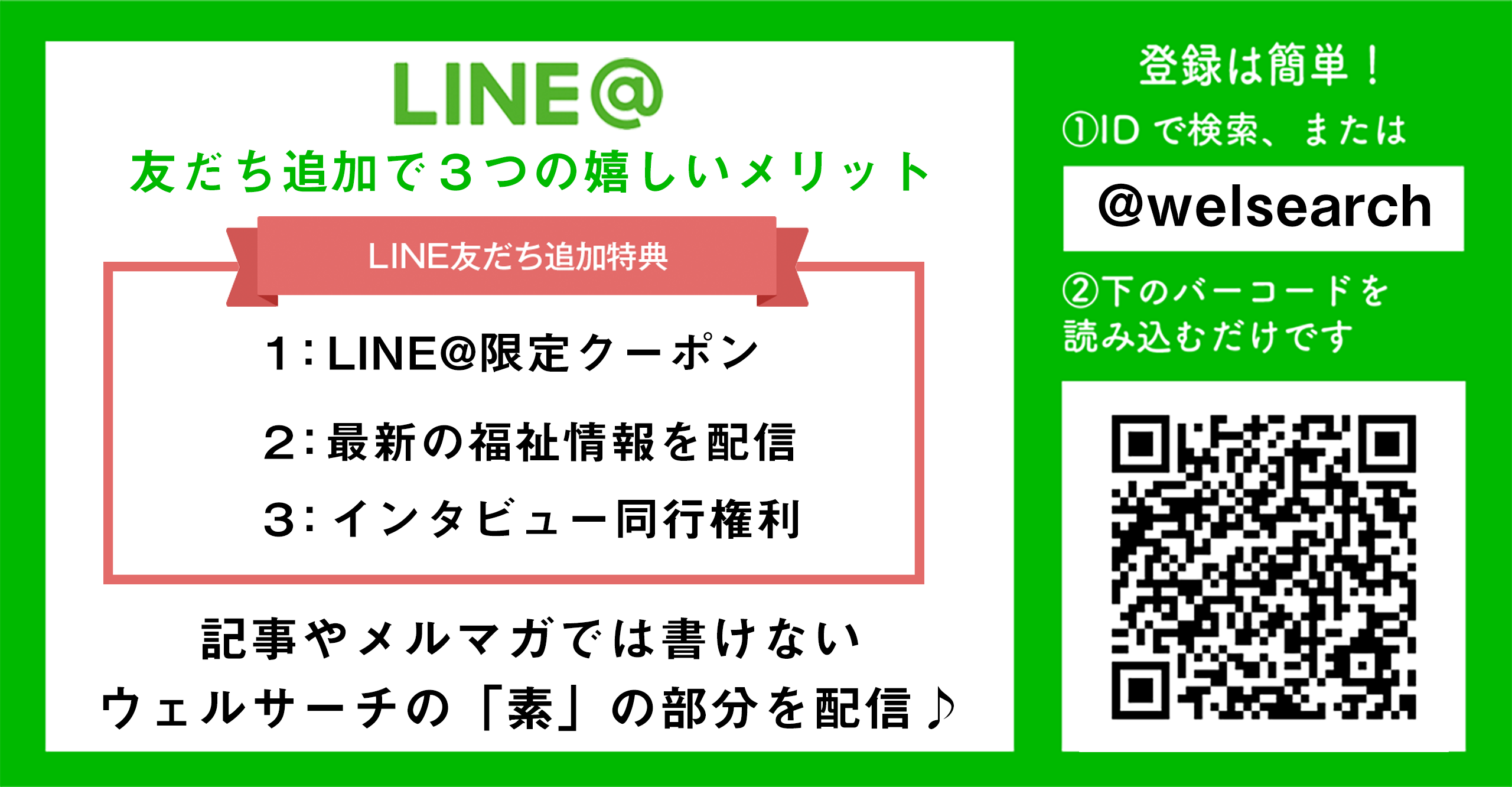
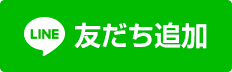
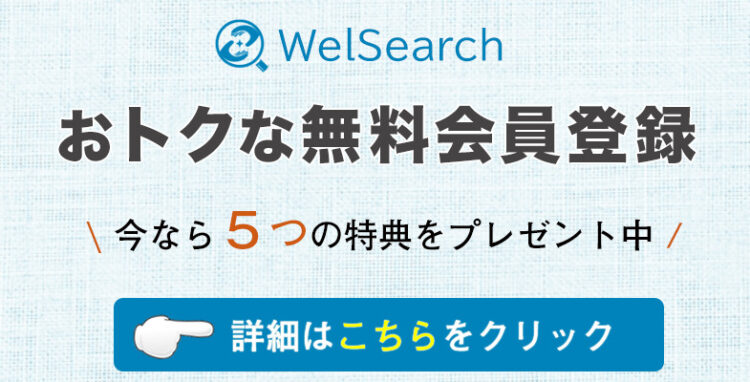







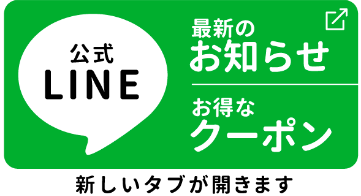


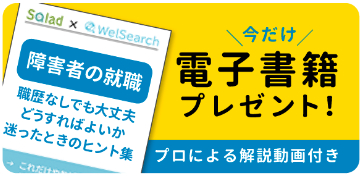
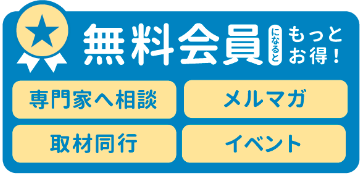

この記事へのコメントはありません。