障害年金の制度について、みなさんはどの程度ご存知でしょうか?
年金申請を検討中の方や、すでに受給されている方にとって大切な障害年金制度ですが、実はこの制度、毎年さまざまな変更が行われています。
私自身、精神障害で障害年金2級を受給しています。定期的な審査を受けながら制度と向き合う中で、「どんな変更が行われているのだろう?」と興味を持ちました。
今回の記事は、2023年から2025年にかけての制度改正について、自分なりに調べたことをまとめてみました。当事者の視点から「何が変わったのか」「それはどんな意味を持つのか」を考えながら、できるだけわかりやすくお伝えします。
お好きなところからお読みください
障害年金の基本を知ろう

障害年金とは、病気や障害の影響で日常生活や仕事に支障がある人のための公的年金制度です。高齢者がもらう「老齢年金」とは異なり、現役世代でも一定の条件を満たせば受け取ることができます。
障害年金の対象になるのは?
以下のような方が対象になります
- 病気やけがで日常生活や就労に支障がある人
- 身体障害だけでなく、精神疾患(うつ病・統合失調症など)や発達障害も含まれる
- 原則として、「初診日」から1年6カ月経過後の状態をもとに審査される ※一部例外あり(例:末期がんなど)
「初診日」というのは、その障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診察を受けた日のことです。この日付が、後ほど説明する年金の種類を決める重要な要素になります。
等級と年金の種類
障害年金には以下のような区分があります
| 年金の種類 | 等級 | 主な対象者 |
| 障害基礎年金 | 1級・2級 | 主に国民年金加入者(自営業・学生など) |
| 障害厚生年金 | 1級・2級・3級 | 厚生年金加入者(会社員・公務員など) |
精神障害の場合、障害基礎年金では1級・2級のみが対象です。ただし、障害厚生年金に加入している人は3級も支給対象になることがあります。
私の場合:精神疾患で2級を受給中
私は2年ほど前に精神障害を理由に障害年金を申請し、現在は2級を受給しています。申請するまでは「自分が対象になるのだろうか」と不安でしたが、医師や周りの支援者に背中を押してもらい、申請に踏み切りました。結果的に生活の安定につながっており、本当に助かっています。
障害年金を申請する方法には、主に以下の2つがあります
- 自分で書類を揃えて申請する方法
- 社会保険労務士(社労士)に依頼して代理申請してもらう方法
自分で申請する場合は、費用はほとんどかかりません(診断書代などを除く)。でも、書類の不備やミスがあると、手続きがスムーズに進まないリスクも。特に精神障害の場合は、状態を客観的に伝える書類作成が難しいこともあります。
そのため私は、費用はかかりますが、社労士の方に依頼して申請することにしました。事務所によって料金は異なりますが、書類の不備が防げたり、必要なサポートを受けられたりと、安心感には代えられないと感じました。
申請方法や必要書類については、日本年金機構のホームページや、お近くの年金事務所でも詳しく案内しています。わからないことがあれば、遠慮なく問い合わせてみることをお勧めします。
2023~2025年の主な制度改正まとめ

障害年金の制度も多岐にわたりますが、ここ数年ではどのような改正が行われたのでしょうか?特に重要だと思われる部分について解説します。
診断書様式の変更(2023年4月~)
障害年金の申請や更新に欠かせない「診断書」の様式が、2023年4月から全国で新しい形式に変更されました。この変更は、より正確で公平な評価を行うことを目的として導入されたものです。
主な変更ポイント
- 日常生活の具体的な状況を書く欄が増えた → 「どの程度支援が必要か」「日常動作をどれくらい自力で行えるか」などの詳細記入欄が設けられました
- 医師の記載ミスやあいまいな表現を減らす仕組みが加わった → 「できる・できない」をはっきり記述するよう促す設計で、評価のブレを防止します
- 一部の項目にチェック式が導入された → 選択肢を用いた記載ができるようになり、審査側とのズレが起きにくくなりました
たとえば、旧様式では「買い物ができるか」という項目について、医師が自由記述で「たまにできる」「調子のよい日は行ける」といったあいまいな表現を書くことが多く、それを見た審査側が「自立している」と判断してしまうこともありました。
新様式では
- 「頻度」(例:毎日・週1回程度・できない)
- 「方法」(例:一人で行ける・同伴が必要・代行)
- 「意思決定の力」(例:品物を自分で選べるか)
といった具体的な設問やチェック項目が用意されているため、より正確に「できる/できない」ではなく「どういう条件でできるか」が伝えられるようになっています。
精神障害における認定の見直し(2024年~)
2024年ごろから、精神障害に対する障害年金の認定基準や評価の運用方法が少しずつ見直されてきています。これは制度そのものの改定というよりも、審査実務での「見方」や「重視するポイント」の変化に近い動きです。
具体的な変化例
- 「日常生活能力」の評価項目の再検討 → 「食事」「清潔保持」「金銭管理」など、各項目ごとに”どの程度の支援が必要か”を細かく見る方向へ
- 単なる症状の重さよりも、「どれくらい支援が必要か」を重視 → 「症状があるかどうか」ではなく、「それが日常生活にどう影響しているか」が重視されるように
- 精神障害特有の”波”や”見えにくさ”を、より丁寧に評価する傾向 → 調子のいい日と悪い日がある、外見上は普通に見える、といった特性にも配慮されつつある
これまでは、「身の回りのことが一応できている」と判断されると、それだけで”自立している”とみなされやすい傾向がありました。
しかし現在では、以下のような視点も含めて判断されるケースが増えてきています。
- 食事はできているが、「作る」までの準備が一人ではできない
- 金銭管理は本人名義でもしているが、「支出をコントロールできず浪費がある」などの問題がある
- 外出できる日もあるが、「日によってはまったく動けない」「予定をこなすと数日寝込む」といった”波”が大きい
つまり、「できる/できない」の2択ではなく、「どういう条件でできているのか」や「どれだけの支援が必要なのか」を、より具体的に評価する動きが進んでいます。精神障害の当事者として、この変化は本当に嬉しいですね。
更新や再認定に関する見直し
障害年金を受給している人には、一定の期間ごとに「更新」や「再認定」の手続きが求められます。これは「今の状態が引き続き該当するかどうか」を確認するための仕組みですが、精神疾患のある当事者にとっては、大きな不安やストレスに繋がっていました。
最近では、この更新に関しても、受給者の負担や不安を減らす方向で運用の見直しが進められています。
変化してきているポイント
- 病状が安定している人は、更新の間隔が長くなる場合がある → たとえば、これまで1年ごとに診断書の提出が必要だった人が、3年ごとでよくなるケースも
- 精神疾患でも「3年ごと」など、長めのスパンが適用されるケースが増加 → 「回復傾向が続いている」「状態が一定で変わりがない」と判断されると、期間延長される傾向に
- 更新時の診断書の審査も”経過観察”が中心に → 急な支給停止よりも、「もう少し様子を見ましょう」という方向に調整されやすくなっている
これまで
- 精神疾患で2級の障害年金を受けていた人が、毎年更新を求められ、毎回「切られるかも」と不安になる
- 状況は大きく変わっていないのに、毎年同じ診断書を提出し続ける必要があった
現在
- 症状が安定していると認定されれば、3年ごとの更新になることもある
- 医師が「状態は変わらない」と診断し、支給継続の可能性が高い場合は、急な打ち切りではなく”経過観察”として継続される例も増えている
精神障害の場合、調子の波があるだけでなく、「手続きのストレス自体が体調に影響する」ことも珍しくありません。更新間隔が延びることで、「生活の安定を守りながら安心して過ごせる時間」が増えるという点で、この見直しは大きな意味があります。
当事者として見て感じたこと
今回、障害年金の制度について改めて調べてみて、いくつかの気づきがありました。とくに精神障害のある当事者として、「なるほど」と思えた部分と、「ここがまだ課題かも」と感じた部分の両方が見えてきました。
精神障害に対する評価が、少しずつ丁寧になってきた
私自身、障害年金の申請をした当時は、「精神障害は外から見えにくいから、ちゃんと評価してもらえるのか」という不安を強く感じていました。身体障害のように”はっきり見える基準”が少ないため、どこまで伝わるのか不安だったのです。
でも、最近の制度や運用の流れを見ていると、「日常生活でどのくらい困っているか」「どれくらい支援が必要か」といった点を具体的に見てもらえるようになってきたことを知り、少し安心しました。
評価が”できる・できない”だけでなく、”どれだけ負担があるか””どれくらい助けが必要か”に変わってきているのは、大きな変化だと感じています。
一人一人の状況をより丁寧に見てもらえることで、私たちのような「見た目ではわかりにくい障害」を持つ人も、より適切な支援を受けられる可能性が高まるでしょう。これは確かな進歩だと思います。
発達障害の自分にとって、申請手続きは本当に大変だった
私は発達障害があり、書類作成や手続きが苦手でした。そのため、障害年金の申請は社会保険労務士(社労士)さんに依頼しました。書類の準備ややりとりを一人で行うのは、ほぼ不可能だったと思います。
それでも、病院で診断書を依頼したり、細かい情報を集めたりといった部分では、かなりの負担とストレスがあったのが正直なところです。
費用面でも、社労士に依頼するとなれば決して安くはなく、「お金の余裕がない人はどうするんだろう」と考えてしまいます。自分で申請する方にとっては、ミスが許されない書類や、不備による不安が精神的にのしかかってくるのではないでしょうか。
だからこそ、最近の「様式の見直し」や「運用の標準化」といった流れが、少しでも申請時の金銭的・心理的な負担を軽くする助けになればと強く思います。実際、診断書の新様式では、チェック項目が増えたことで、医師との意思疎通もしやすくなったのは大きなポイントです。
なぜ精神障害にも年金が必要なのか、知ってほしい
精神障害のある人が年金を受け取ることに、疑問を持つ人もいるかもしれません。でも、実際の生活では、「できないわけではないけど、やるのに大きな負荷がかかること」「日によって調子が大きく変わること」など、目に見えにくい困難が日常的にあるのが現実です。
単に”仕事ができないから”ではなく、”生活を続けるだけでも多くのエネルギーや支援が必要”だからこそ、障害年金は必要なんです。
こうした「見えにくい困難」があることを、少しでも多くの人に知ってもらいたいと感じます。特に精神障害や発達障害は、周囲から「努力すればできるのでは?」と誤解されやすいですが、実際には日々の生活のハードルが想像以上に高いことを理解してもらえたらと思います。
制度がもっと優しくなることを願って
不正受給などの問題がある中で、制度をむやみに簡略化することが難しいのは理解しています。でも、精神障害に関しては、そう簡単に回復するものではないというのが実情です。
更新のたびに診断書を取り直し、「切られないか」と不安になる負担は、精神的にも大きいものです。できれば、症状が安定している人に対しては、もっと長期の継続支給を前提にしてほしいと思います。
幸い、最近では更新の間隔が長くなるケースも増えてきているようで、少しずつ改善の兆しは見えています。今後も当事者の声が制度に反映され、より生活に寄り添った支援になっていくことを願っています。
結局のところ、障害年金は「困っている人を支える」ための制度です。手続きの複雑さや更新の不安が、本来支えるべき人たちの負担になってしまっては本末転倒。当事者の立場から見ると、まだまだ改善の余地はありますが、少しずつでも良い方向に変わっていくことを信じています。
おわりに

今回、障害年金制度の改正について調べてみて、「難しそう」と感じていたものが少し身近に感じられるようになりました。精神障害を持つ当事者として、評価の視点が丁寧になり、更新の負担が軽減されてきていることは心強い変化です。
一方で、申請の複雑さや支援の必要性も実感しています。私自身、社労士さんの助けがなければ受給までたどり着けなかったでしょう。
障害年金は生活を支えるだけでなく、「困っている状態を社会が認めてくれた」という安心感をもたらす大切な制度です。これからも情報をアップデートしながら、制度がどう変わっていくかに関心を持ち続けたいと思います。
この記事が、皆さんの不安を少しでも和らげ、「知ることで安心できる」きっかけになれば嬉しいです。
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- 移乗介助のリハビリにも|自立支援型立位介助ロボット『すくっとたてる君』開発背景 - 2025年12月12日
- 障がいがある方向けの短時間職業体験が育む「働く自信」|志村学園×レバレジーズの挑戦 - 2025年12月4日
- 絵本が紡ぐ、共生社会への想い|絵本作家・由美村嬉々(木村美幸)先生インタビュー後編 - 2025年12月2日

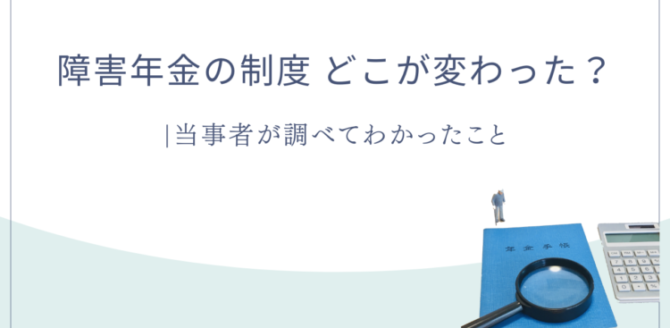

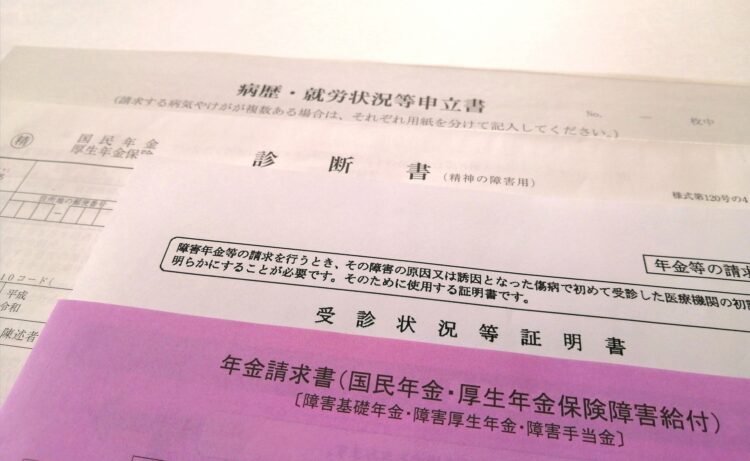
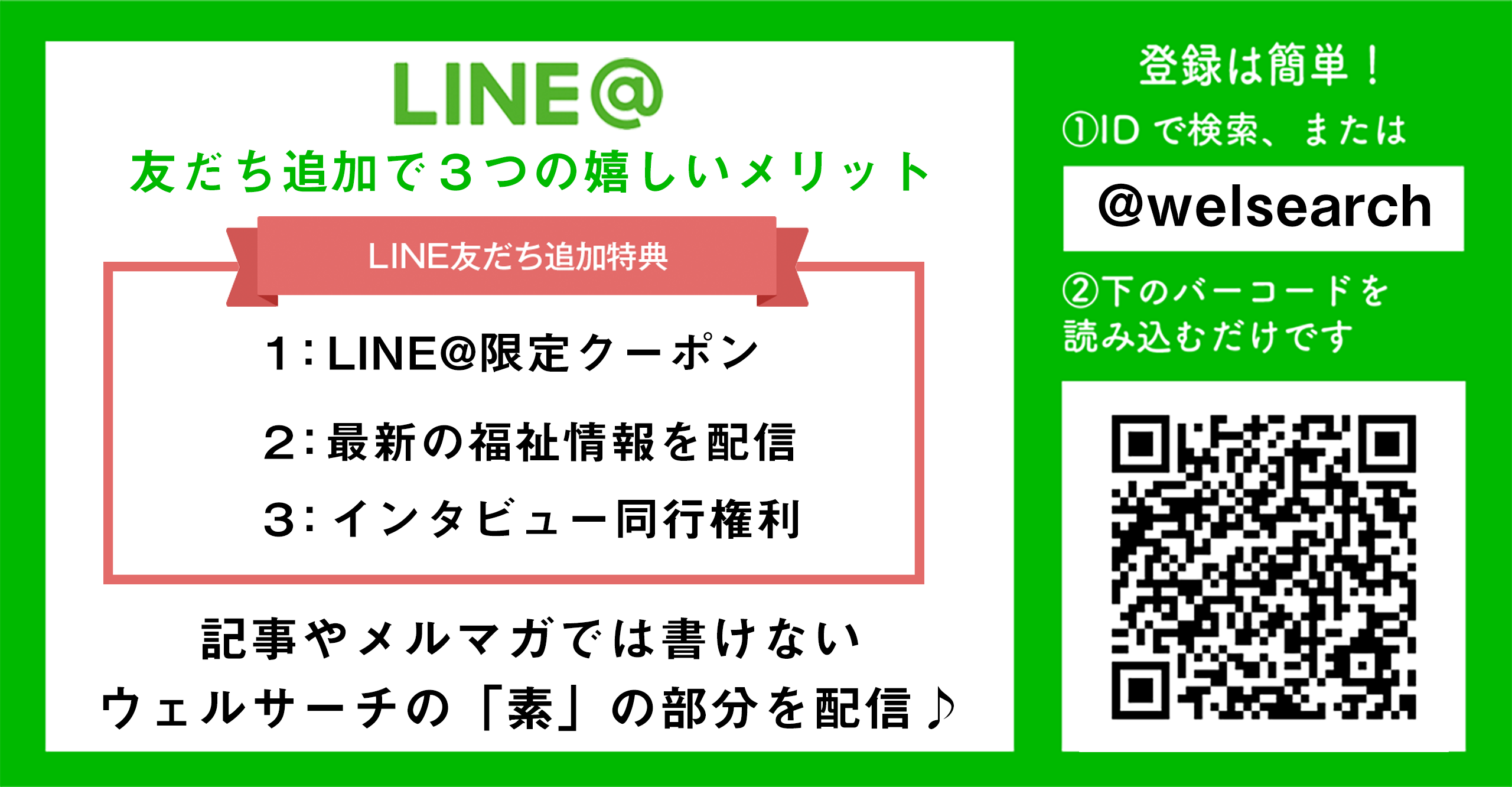
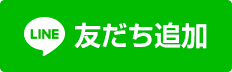
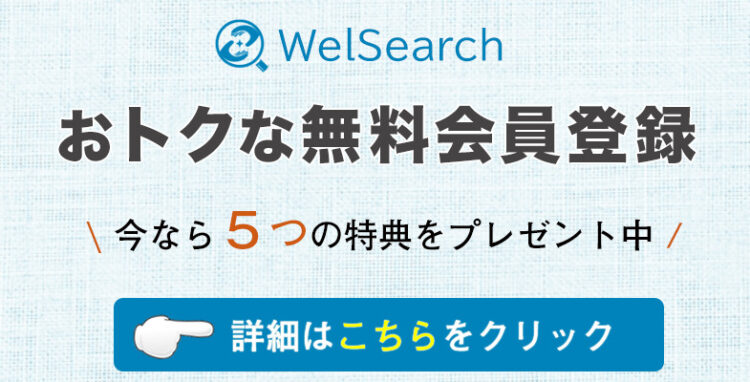



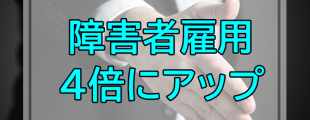
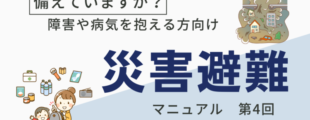

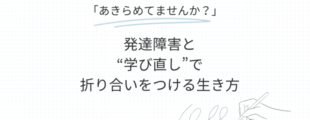
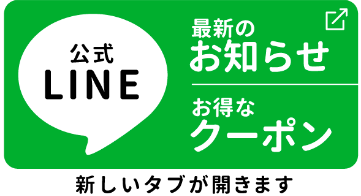


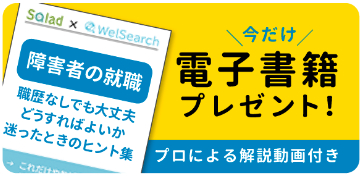
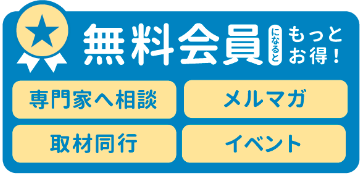

この記事へのコメントはありません。