今や、国民の誰もが利用しているといっても過言ではないSNS。有益な情報もたくさんありますが、「なんとなく嫌な感じがしたこと」、ありませんか?
直接的な悪口じゃなくても、ちょっとした言葉や空気感で、「それ、もしかして……」とモヤモヤすることも。
私は、発達障害と吃音を抱えながら、日々を過ごしています。同じような特性を持つ人たちと関わる中で、SNS上での誤解や無自覚な偏見に出会うこともありました。
この記事では、SNSという場所で起こる障害や病気への偏見や誤解について、ちょっとだけお話しさせてください。怒ったり、強く訴えたりするつもりはありません。
ただ、「それって偏見かも?」と気づいてもらえるきっかけになればうれしいです。
お好きなところからお読みください
SNSに潜む“障害への誤解の種”

SNSは、誰もが気軽に発信できる便利な場です。
その一方で、「ちょっとした言葉」や「共感を得るための投稿」が、無意識の偏見や誤解を広げてしまうこともあります。
たとえば、障害や病気を取り上げたニュースに対するコメント欄では、このような反応をよく目にします。
よく見かける「障害への偏見や誤解」の例
| 表現例 | 背景にある誤解や偏見 |
| 「発達障害?ただの言い訳でしょ」 | → 本人の努力不足・怠けと結びつけられてしまう。 |
| 「精神疾患の人って危ないんでしょ?」 | → 事件報道と結びつけ、不安視されがち。 |
| 「配慮を求めすぎるのもおかしい」 | → 支援や合理的配慮を“わがまま”と受け取られることがある。 |
| 「昔はそんな言葉なかったのに」 | → 時代や認識の変化を無視した発言。 |
SNSの種類に関係なく、こうした言葉は形を変えて何度も拡散されています。
でも、「よく見かける」=「正しい情報」ではありません。
これらの発言は、必ずしも悪意のある中傷とは限りません。多くの場合、その背景には「知らない」「なんとなく不安」といった感情があります。
けれど、本人や家族にとっては、何気ない一言が“自分を否定された”ように感じられることもあります。
SNSは情報を広げる力を持つ一方で、誤解やレッテルもまた、あっという間に広がってしまう場所です。だからこそ、発信する側も、受け取る側も、ほんの少し「立ち止まる」意識が大切なのだと思います。
伝えることが“前に進む”きっかけに
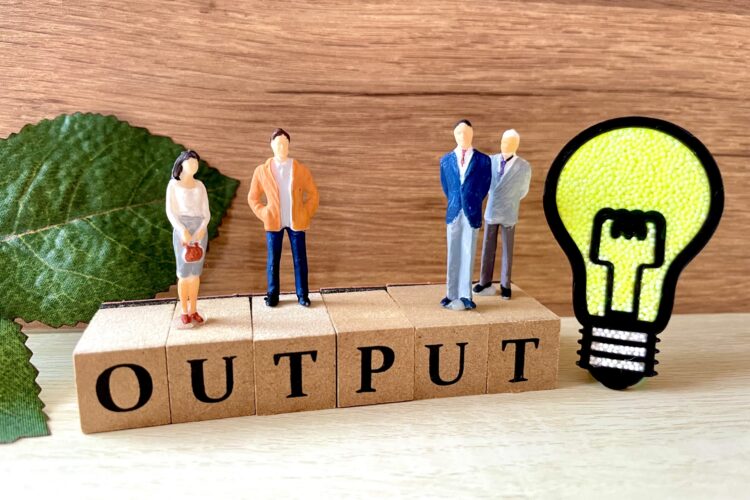
SNSで障害や病気に関する話題を目にするとき、私は少し身構えるクセがついてしまいました。なぜなら、「努力が足りないだけでしょ?」という声や、「また精神障害者が…」という心ないコメントを、何度も見てきたからです。
私は発達障害と吃音があります。
どちらも、自分で完全にコントロールできるものではありません。
それでも、まるで“怠け”や“問題を起こす存在”のように語られてしまうとき、言葉にできないモヤモヤが胸に残ります。
特に、事件のニュースが流れたあとのSNSや掲示板では、「障害者=危ない」という誤ったイメージが、簡単に拡散されてしまうことがあります。
一部の人には、何を言っても伝わらないかもしれない。でも、そういう声があまりにも大きいと、それを信じる人が少しずつ増えてしまうのではないか。そんな不安も、私は抱えています。
一方で、希望を感じたこともあります。専門家がSNSで丁寧に誤解を解こうとしている姿や、当事者自身が思いを発信しているのを見かけたとき、「ちゃんと声をあげる人がいる」と感じられて、少し救われてもいます。
ただ、それでも「届いてほしい人に、なかなか届かない」というもどかしさも。
私は今も、毎日が楽なわけではありません。障害を抱えていることで、苦しさやしんどさを感じる瞬間はたくさんあります。
でも、心のどこかでは「誰かが、ほんの少し浮き上がれるきっかけを持てたらいい」と思って、こうして言葉を綴っています。障害をオープンにできない人もいると思います。
それでも、自分の中で「ちょっと前に進めた」と思える瞬間があるだけでも、人は救われる。そう信じて、私はこの文章を書いています。
怖い”と“わからない”は、隣り合わせ

偏見や誤解の多くは、「知らないこと」から生まれるのだと思います。
発達障害も吃音も、たとえば一緒に過ごしてみれば「そういう特性なんだな」とわかってもらえることが多いのですが、SNSではそういった“体験を通じた理解”の機会がほとんどありません。
人は、知らないものを「怖い」と感じがちです。それはある意味、自然な反応でもあります。
でも、そこから「迷惑」「危険」などとレッテルを貼ってしまうと、本来なら理解できるはずの距離が、かえって遠ざかってしまうのではないかと感じています。
たとえば、吃音についても、「言いよどむ=緊張している」と誤解されたり、「ちゃんと話せないのは自信がないからでは」といった反応をされることがあります。けれど、当事者にとっては、自分の言葉が“詰まる”こと自体が苦しみの一つであり、そこに「評価」や「心構え」を重ねられるのは、つらいものです。
SNSでは、短い言葉がすぐに流れていきます。誰かが発した誤解や決めつけの言葉が、「共感」や「いいね」で広がってしまうことも。
それに反論するのは、とてもエネルギーがいることです。だからこそ、「全部を理解しようとしなくても、“わからない”と立ち止まってくれるだけで違う」と私は思っています。
「わからないままでも、否定しない」
そんな距離感のやさしさが、SNSにも、社会にも、もう少し広がっていってほしい。
炎上を避けつつ、やさしく伝えるには?

SNSは、思ったことをすぐに言葉にできる便利な場所です。けれど同時に、それが「誰かを傷つける」可能性と常に隣り合わせにあります。
私は、自分の特性や感じたことを発信するとき、「どう伝えたら届くだろう」「角が立たないだろうか」と何度も文章を見直します。それは、炎上を恐れているからというよりも、「相手を責めない形で、自分のことを理解してほしい」という気持ちがあるからです。
ですがこうした慎重さは、発信する人にばかり求められがちです。
一方で、受け取る側は「読むだけ」「反応するだけ」と思っていることも多く、言葉の背景にある思いや事情に、目を向けないこともあります。
たとえば
- 「怒ってないのに、どうして強く聞こえちゃうのかな?」
- 「説明したつもりだけど、もしかして伝わってないかも?」
- 「言葉を選んだつもりだけど、それでも誰かを傷つけたかな……」
発信する側が悩みながら書いた言葉を、「自分に関係ない」「過剰反応だ」と一蹴されてしまうのは、とても苦しいことです。
だからこそ、私たちはお互いに少しずつ、SNSでのやりとりのあり方を見直していけたらと思います。
- 書く側は、「伝えたいこと」と「言葉の印象」のバランスを考える。
- 読む側は、「この言葉の裏に、どんな事情があるんだろう」と少しだけ想像してみる。
それだけで、SNSはもっと安心して言葉を交わせる場所になる気がしています。
障害をわかってほしいとは言わない。でも気づいてくれたら
私は、すべての人に障害や病気のことを理解してほしいとは思っていません。それは、きっと難しいことだから。
経験も立場も違えば、感じ方も受け止め方も違って当然です。
でももし、SNSで見かけた誰かの言葉に、「なんだか違和感があるな」「ちょっとモヤッとするな」と感じたとき、ほんの少しだけ、立ち止まってみてくれたら。それだけで、世界は少し変わるような気がします。
誰かが話している「困りごと」や「生きづらさ」に
「それって甘えじゃないの?」
と決めつける前に、「そう感じる理由があるのかもしれない」と思ってくれる人が少しずつ増えたら、言葉の空気は、きっともっと優しくなる。
私は、自分の発信が大きな影響力を持っているとは思っていません。でも、一人の声が、誰かの「偏見じゃないかも?」という気づきになるなら、それだけで意味があると思っています。
SNSは冷たく感じることもあるけれど、言葉がつながれば、ちゃんとあたたかさも届く場所だと信じています。
今日も発信を続ける誰かが、誰かの無意識の壁を、そっとやさしくノックできていますように。
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- すべての家族に”写真を撮る喜び”を 医療的ケア児・発達障害児にも寄り添う写真館 - 2026年1月20日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【後編】 - 2026年1月12日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【前編】 - 2026年1月11日

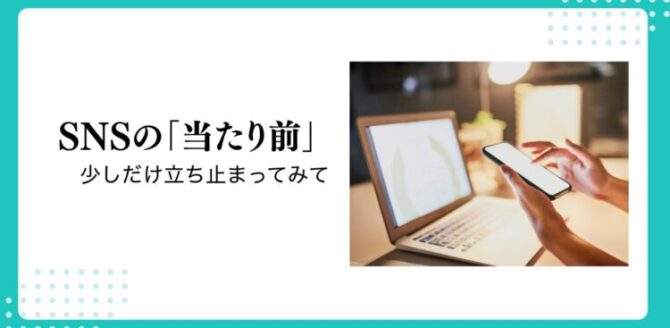

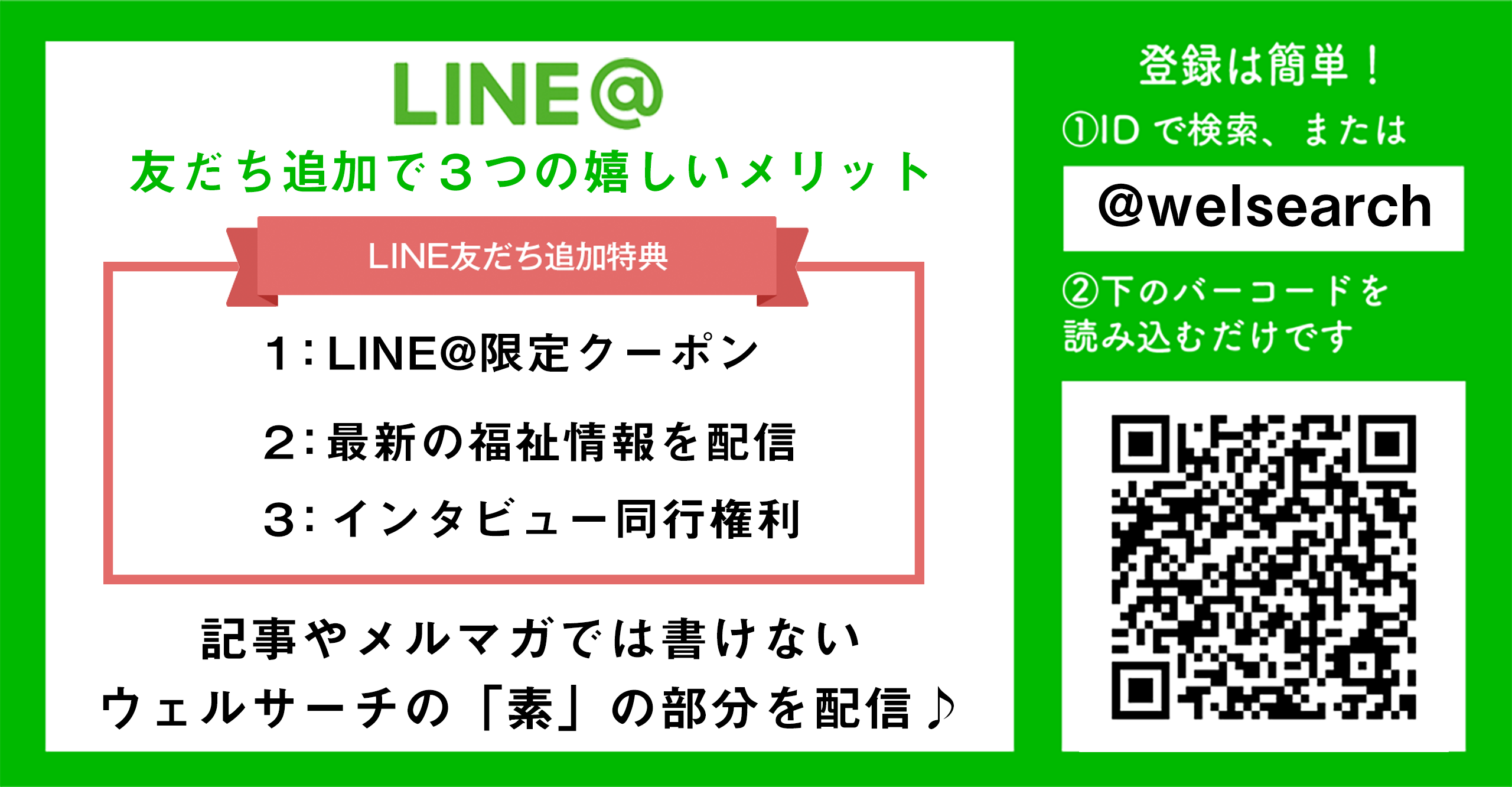
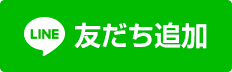
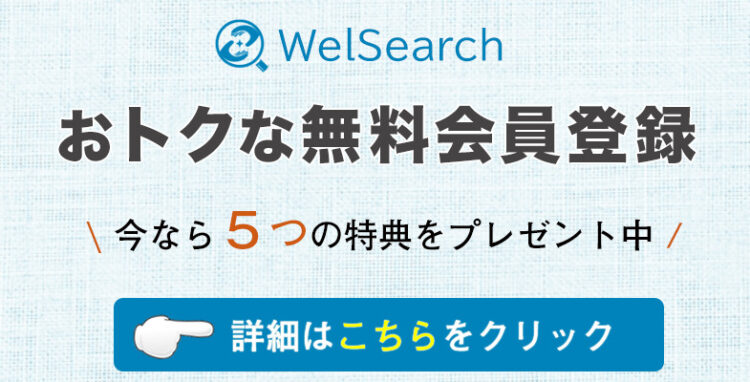

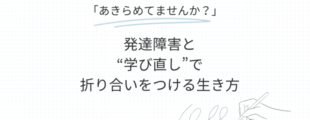





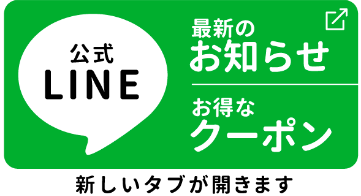


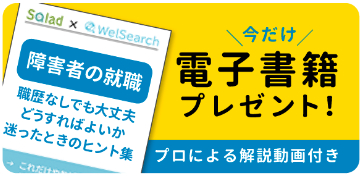
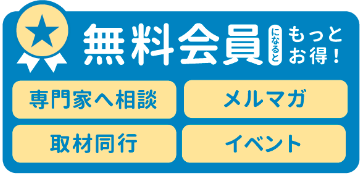

この記事へのコメントはありません。