「心因性失声症(しんいんせいしっせいしょう)」。この病名を聞いたことはあるでしょうか?
喉には異常がないのに、突然声が出なくなる──
私は吃音持ちであり、「話すこと」に関しては人一倍意識しがちです。だからこそ、「声を出したいのに出せない」ことのつらさは身に染みています。心因性失声症は、喉ではなく心の負担が原因で起こるものです。けれど、まだあまり知られていないため、誤解されやすい病気でもあります。
声が出ないことに周囲が気づかず、無理に話そうとして悪化してしまう場合も・・・。
今回は、「心因性失声症とは何か?」をわかりやすく解説しながら、吃音を持つ立場からも「話せないこと」について考えてみたいと思います。
お好きなところからお読みください
声が出ない?それってどんな病気?

声が出なくなる症状を医学的には「失声」と称しています。失声は様々な原因で引き起こされ、一般的に風邪や上気道感染による喉の炎症が原因で、声がかすれたり、出しにくくなることがしばしばです。
しかしながら、喉や声帯に明白な異常がないにも関わらず、声が出なくなる場合も。こうした症状は「心因性失声症」として呼ばれ、精神的なストレスや心理的なものが主な要因として考えられています。
心因性失声症は、突如として声が出なくなりますが、声帯や喉の構造には問題が認められません。このため、耳鼻咽喉科の検査では異常が確認されないことが多く、診断時には心理的な背景を考慮する必要があります。
心因性失声症の主な特徴
心因性失声症の主な特徴としては以下のようなものがあります。
- 喉や声帯には異常がない
- 医師の診察でも「器質的な異常なし」と診断されることが多い
- 突然、または徐々に声が出なくなる
- ある日突然話せなくなる場合もあれば、少しずつ声がかすれていくこともある
- 咳や咳払いはできることが多い
- 声を出そうとしても話せないが、咳や笑い声は出ることがある
- 心理的なストレスが関係する
- 強いプレッシャーや不安、トラウマなどが引き金になる
なぜ声が出なくなるのか?
声を出すには、脳が「声を出すぞ!」と指令を出し、それが喉の筋肉に伝わる必要があります。しかし、強いストレスや不安が積み重なると、脳が「声を出さないようにしよう」と判断してしまうことがあります。
これは、極度の緊張で手が震えたり、動けなくなったりするのと同じように、脳が「話すこと」にブレーキをかけてしまう状態です。
どんな場面で発症しやすいのか?
心因性失声症は、日常のストレスが蓄積されるような状況の方が、ふとしたきっかけが元で発症することが多く見られます。
- 大勢の前で話す機会がある(発表・プレゼン・演劇など)
- 職場や学校で強いプレッシャーを感じる
- 人間関係のストレスが重なる
- 「話すこと」に対する恐怖心がある(過去に怒鳴られた・バカにされたなど)
こうした状況が重なると、脳が「話すこと」を危険だと判断し、無意識に声を止めてしまうことがあります。このように、心因性失声症は単なる「気のせい」ではなく、心の負担によって声を出す機能が抑制される現象です。
他の声の病気とどう違うの?

声が出なくなる病気はいくつかありますが、心因性失声症は他の病気とは原因が異なります。ここでは、代表的な声の病気と心因性失声症の違いを比較します。
代表的な声の病気と心因性失声症の違い
| 病名 | 原因 | 主な症状 | どんな時に起こる? |
| 風邪・喉の炎症 | ウイルス・細菌感染 | 喉の痛み、声のかすれ、発熱 | 風邪やインフルエンザにかかったとき |
| 声帯ポリープ | 声の使いすぎ、喫煙 | 声のかすれ、しゃがれ声、喉の違和感 | 大声を出す職業(教師・歌手など) |
| 機能性発声障害 | 声帯の使い方の問題 | 声が出にくい、違和感 | 長時間の発声、ストレス |
| 心因性失声症 | 心理的ストレス | 突然声が出ない、ささやき声しか出せない | 強いプレッシャーや不安を感じたとき |
心因性失声症の特徴的な違い
① 喉や声帯には異常がない
他の病気は、喉の炎症や声帯の損傷など身体的な問題が原因ですが、心因性失声症は精神的なものが原因となります。
② 突然声が出なくなることが多い
風邪や声帯ポリープは徐々に症状が悪化することが多いですが、心因性失声症はある日突然、または短期間で声が出なくなるのが特徴です。
③ 声を出そうとすると出ないが、咳や笑い声は出る
心因性失声症の人は、咳やくしゃみ、無意識の笑い声は普通に出せます。これは、声を出す機能自体は正常だが、意識的に声を出そうとすると抑制されるためです。
④ プレッシャーやトラウマが発症の引き金になる
他の声の病気は声の使いすぎや感染症などが原因ですが、心因性失声症は強いストレス、トラウマ、環境の変化などが引き金になります。例えば、仕事や学校のプレッシャー、人前で話すことへの恐怖などが関係することが多いです。
どんな人がなりやすい?

心因性失声症は、特定の性格や環境に置かれた人が発症しやすいとされています。特に、以下のような特徴がある人はリスクが高いと考えられます。
責任感が強く、真面目な人
- 仕事や学校で「失敗できない」と感じやすい
- 周囲の期待に応えようと無理をしてしまう
- 自分の気持ちを押し殺してしまうことが多い
このような人は、プレッシャーを抱え込みやすく、ストレスが限界に達すると声が出なくなることがあります。
緊張しやすく、人前で話すのが苦手な人
- プレゼンや発表の前に強いストレスを感じる
- 人と話すときに「うまく話さなきゃ」と意識しすぎる
- もともとあがり症で、緊張すると声が震えることがある
人前で話すことに強い不安を感じていると、ある日突然「声が出ない」という状態になってしまうことも。
過去に「話すこと」で嫌な経験をした人
- 発言したことで怒られたり、バカにされたことがある
- 学校や職場で自分の意見を言いにくい環境にいる
- 子どもの頃に「黙っていなさい」と言われることが多かった
過去のトラウマが影響し、「話すこと=危険」と無意識に思い込むことで、声が出なくなることがあります。
強いストレスや環境の変化があった人
- 進学・転職・引っ越しなどで生活環境が大きく変わった
- 人間関係の悩み(いじめ・ハラスメントなど)を抱えている
- 重要な試験や仕事のプレッシャーに追われている
ストレスが長期間蓄積すると、ある日突然声が出なくなることがあります。特に「話すこと」が求められる場面で発症しやすい傾向が見られます。
吃音の私が、心因性失声症について考えたこと

他の私の記事でも何度か話していますが、私は吃音持ちです。他の障がいにも共通することですが、「目に見えない症状」は、健常な方にとって理解が難しい部分があると感じています。
例えば、腕を骨折して包帯を巻いていれば、周囲はすぐに「ケガをしていて不便なことがある」と気づき、自然と配慮が生まれます。しかし、私のような吃音の場合、外見からは何も異常がないため、「話し方の問題だ」「努力すれば治る」と思われがちです。
吃音について語るとき、よく出てくるエピソードとして「もっとゆっくり話せば大丈夫」「焦らないで話せば普通に話せるでしょ?」といった言葉があります。これらは、「話し方の工夫で治せる」「努力不足が原因」と思われている一例です。
心因性失声症の方も同じように、「見えない症状」だからこそ、誤解されやすいのではないかと思います。
「甘え」と言われることの心理的影響
吃音の当事者として、「気にしすぎ」「努力すれば話せるはず」と言われることがどれほどつらいかを身をもって知っています。「気にしなければ話せる」と言われると、逆に「気にしてはいけない」と意識しすぎて、ますます悪化するという悪循環。
心因性失声症も、「声が出ないのは甘え」「話せるのにわざと話せないようにしているんじゃないの?」と言われることがあると聞きます。
しかし、極度のストレスで手が震えたり、体が動かなくなることがあるように、「声が出なくなる」のも症状のひとつです。心因性失声症ではなくても、例えば発表会などでしどろもどろになり、何も話せなかったという経験などをした方もいるのではないでしょうか?
話したいのに話せない状態なのに、「努力不足」「気持ちの問題」と言われることで、当事者はさらに自分を責めてしまい、より深刻な状態になってしまうことがあります。
吃音と心因性失声症の「周囲の反応の違い」
吃音と心因性失声症はどちらも「うまく話せないこと」が共通していますが、周囲の誤解されやすいポイントは少し異なります。
- 吃音の場合:「変な話し方をしている」と思われがち
- 心因性失声症の場合:「話せないわけがない」「がんばれば話せる」と誤解されがち
どちらの場合も見た目ではわかりにくいため、本人の気持ちを考えずに「正しい話し方をすればいい」と思われてしまうことが多いのです。
「見守ってほしい」とは、どういうことか?
心因性失声症や吃音に限らず、精神的なことに関しては「静かに見守って欲しい」と繰り返し訴えています。ですが、「見守る=何もしない」ではありません。その人に合わせた適切な関わり方があると思います。
例えば、
- 無理に話させようとしない(プレッシャーを与えない)
- 「声が出なくてもいいよ」と伝える(安心感を与える)
- 会話のペースを相手に合わせる(筆談やジェスチャーなども活用する)
こうした対応をしてもらえると、話すことに対する不安やプレッシャーが軽減され、少しずつ改善する可能性があります。無理のない範囲で、相手を尊重する。見守るというのはそういうことではないでしょうか?
当事者本人が一番治したいと思っている
もう一度いいます。治したいと思っているのは、当事者本人です。吃音も、心因性失声症も、決して「甘え」や「怠け」ではありません。話せるようになりたいと願い、できる限りのことはしているのに、それでもうまくいかない。
だからこそ、周囲の理解が大切です。「話さなくてもいい」と思える環境があれば、少しずつ話せるようになるかもしれません。
無理に「話させよう」とするのではなく、そっと寄り添ってほしい。それが、当事者にとって何よりの支えになるのではないでしょうか。
心因性失声症の対処法

心因性失声症は、喉の問題ではなく、ストレスや心理的な負担が原因で起こります。そのため、無理に声を出そうとしたり、プレッシャーをかけたりすると、逆に悪化してしまうことも。回復には、安心できる環境と適切なサポートが重要です。
「がんばって話して!」は逆効果
心因性失声症の人に対して、「がんばって話してみて」「気持ちの問題だから、リラックスすれば大丈夫」と言ってしまうことがあります。しかし、これは逆効果です。
- 「がんばれば話せる」と言われると、プレッシャーがかかり、ますます声が出なくなる
- 本人も「話さなきゃ」と焦ることで、余計に悪化する
- 「自分のせいで話せないんだ」と思い込んでしまうと、ストレスが増してしまう
大切なのは、声が出なくても大丈夫だと思える環境をつくることです。
安心できる環境を作るのが大事
心因性失声症の回復には、ストレスを減らし、安心できる環境を整えることが重要です。
- 話すことを強要しない(無理に声を出させようとしない)
- 「話せなくてもいいよ」と伝える(プレッシャーを減らす)
- コミュニケーションの方法を工夫する(筆談やジェスチャーを活用)
「話さなくても大丈夫」と思えることで、緊張が解け、少しずつ声が出るようになることがあります。
無理に声を出さず、筆談やジェスチャーも活用
声が出せない状態でも、コミュニケーションを取る方法はいくつもあります。
- 筆談(スマホのメモ機能や紙とペンを使う)
- ジェスチャー(手振りで意思を伝える)
- LINEやチャット(会話の代わりに文章でやり取り)
「話せなくても意思は伝えられる」ことを本人が実感することで、安心感につながることがあります。無理に話すことを求めるよりも、こうした方法を活用するほうが、回復を早めることにつながります。
専門家のサポートも有効
心因性失声症は、心理的な要因が大きいため、専門家のサポートが有効です。相談できる主な専門家は以下のようなものがあります。
- 言語聴覚士(ST):発声のリハビリを行い、少しずつ声を出せるようにする
- 心療内科・精神科:ストレスや不安を軽減し、心の負担を和らげる
- カウンセリング:過去のトラウマやストレスを整理し、原因を探る
症状が軽い場合は環境を整えるだけで自然に回復することもありますが、長期間続く場合、専門家のサポートを受けることで改善のきっかけを作ることが重要です。
心因性失声症のまとめ
心因性失声症は、身体の異常ではなく、心が発するSOSのサインです。風邪や声帯の病気とは異なり、ストレスや心理的負担が原因で声が出なくなるのが特徴です。
私自身、吃音を持つ立場として、「話したいのに話せないこと」のつらさをよく理解しています。話せないことで誤解されることも多く、「気にしすぎ」「がんばれば話せる」と言われると、さらにプレッシャーを感じてしまいます。心因性失声症も同じで、無理に声を出そうとすると、かえって悪化することがあるのです。
大切なのは、声が出ないことを責めず、安心できる環境を整えることです。筆談やジェスチャーなどを活用し、本人が「話さなくても大丈夫」と思えるような環境を作ることで、少しずつ回復していく可能性があります。
焦らず、無理をせず、心と体を休めながら、ゆっくりと回復を目指しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- すべての家族に”写真を撮る喜び”を 医療的ケア児・発達障害児にも寄り添う写真館 - 2026年1月20日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【後編】 - 2026年1月12日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【前編】 - 2026年1月11日



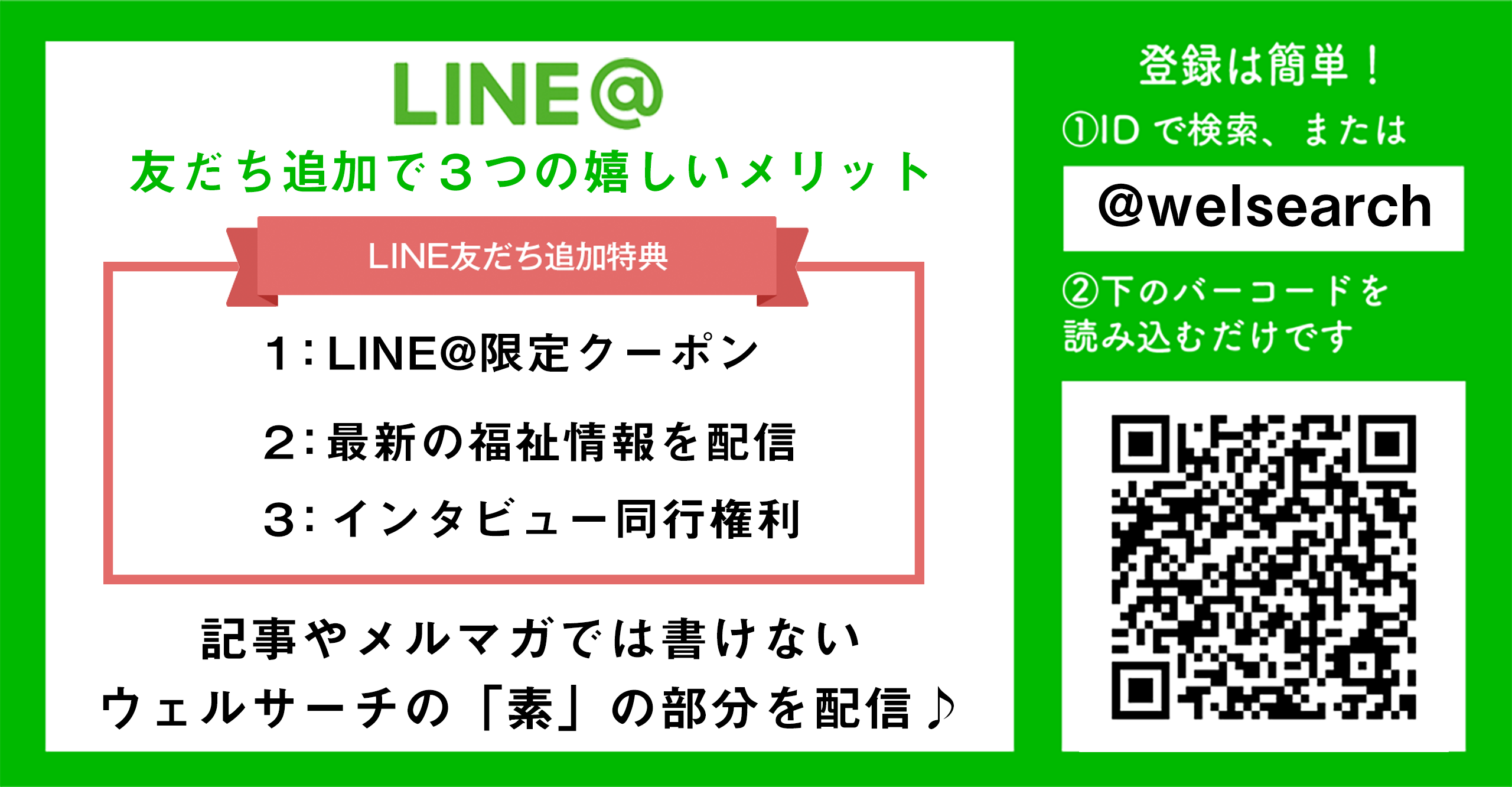
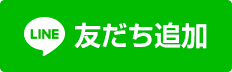
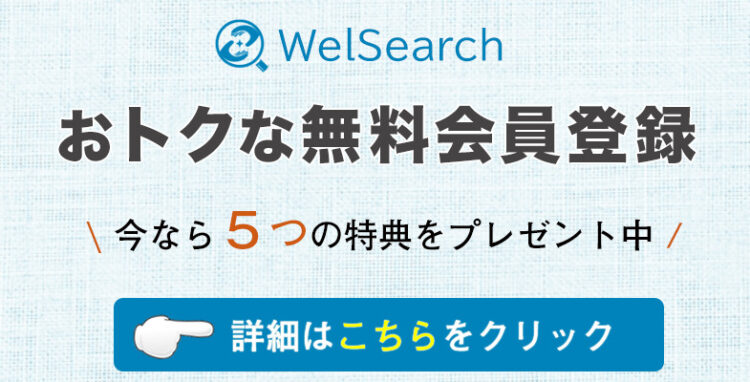







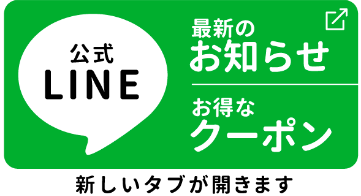


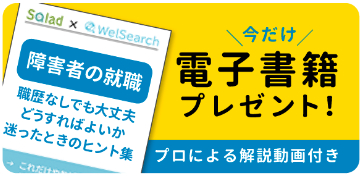
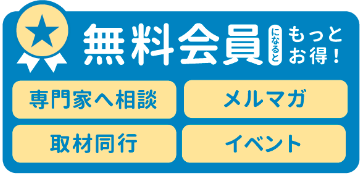

この記事へのコメントはありません。