現代では、いたるところでAIの話題を耳にするようになりました。
ですが、「自分には関係ないな」と感じている方も、まだまだ多いのではないでしょうか?
実はそんなことはありません。
AIというと、専門的な知識や高価な機器が必要な“特別な技術”のように思われがちです。
でも実は、スマートフォンひとつあれば、私たち障害のある人でも日々の生活を少し楽にする頼もしいパートナーとして活用できるのが、いまのAIなのです。
この記事では、ChatGPTのような「対話型AI」を中心に、それぞれの障害特性に応じた使い方を紹介していきます。
私自身も発達障害と吃音がありますが、AIを利用することで日々の仕事や生活に役立てています。 そんな体験談も交えながら、AI活用のヒントをお届けできればと思います。
AIは、あなたの生活をちょっとだけラクにしてくれるかもしれません。
まずは、一緒にその可能性をのぞいてみませんか?
AIって実際どうなの?
AIは今では、基本的な機能であればパソコンやスマホで簡単な登録だけで使えるようになっています。
有料版ではさらに多くの機能が使えますが、無料でもかなりのことができるのです。
それでも、「なんとなく敷居が高そう」と感じている人は、まだ多いのではないでしょうか。
AIってほんとうに難しい?

最初、私も使い方がよくわからないまま試していましたが、少し慣れてくるだけで、思ったより多くのことができると気づきました。 「むずかしくない」と思える理由には、こんな点があります。
- 思ったよりも簡単に質問できる
- 普通に日本語でやりとりできる
- 答え方もやさしく、ちょっとおもしろい
- 「会話する」ことが、なんだか楽しくなる
AIを使うのに難しいプログラミングの知識などはまったく必要ありません。 日本語で会話をするように入力するだけで、いろいろなことができる。 それが、AIはむずかしくないと感じる一番の理由です。
いま使えるAIの代表例
AIといえば、いちばん話題になっているのが「ChatGPT」です。 ただそれだけでなく、私たちの身近では、さまざまなAIが活躍しています。
- ChatGPT(対話型AI):文章作成、相談、質問などに対応
- 音声読み上げツール:画面の文字を読み上げてくれる
- 画像説明AI:視覚的な情報をテキストで伝えてくれる
- スマホアプリ型AIアシスタント:スケジュールや情報検索を音声で補助
この記事では主にChatGPTの活用を中心に紹介しますが、ほかのAIについても興味があればぜひ調べてみてください。「どんなAIがあるの?」という疑問そのものをAIに聞いてみることもできます。
AIを使うときの注意点
AIはとても便利な道具ですが、“魔法の杖”ではありません。使ううえで、次のような点に気をつけることが大切です
- 誤った情報が出てくることもある(事実確認は大事)
- あくまで参考のひとつとして使う(絶対的な正解ではない)
- 人との関係や現実の支援を置きかえない(AIに頼りすぎない)
AIはまだ発展途上です。インターネットと同じように、正しい情報もあれば誤った情報もあります。それでも、AIとうまく付き合えば、頼れるパートナーにもなれる。私はそう感じています。
初心者でもできる!ChatGPTのはじめかた
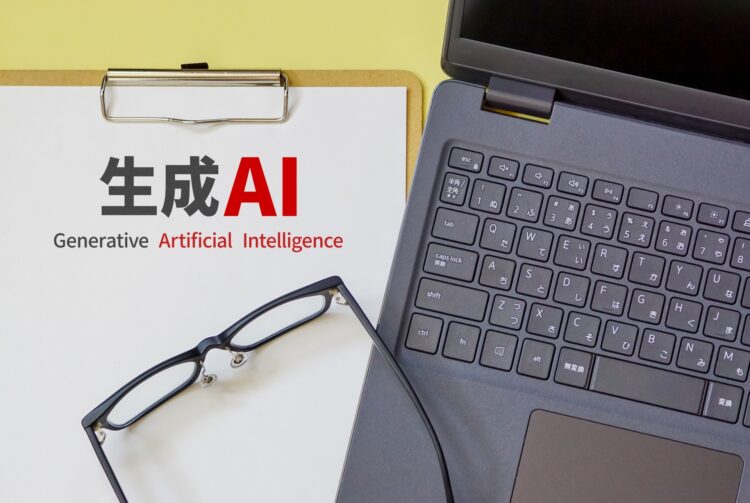
「ChatGPTって、なんだか難しそう」「スマホ操作も苦手だから無理かも…」
そう思う方も多いかもしれません。でも実は、使い方はとてもシンプルです。
まずはアプリを入れる
App Store(iPhone)やGoogle Play(Android)で「ChatGPT」と検索し、公式アプリをダウンロードしましょう。有料プランもありますが、無料プランでも十分使えます。
使い方は「話しかけるだけ」
アプリを開いて、画面下の入力欄に話しかけるように文字を打ち込むだけでOK。 たとえば
- 「今日の予定を確認したい」
→「おはようございます!今日は13時に通院、夕方に買い物の予定がありますね。午前中はゆっくりできますよ」
- 「ご飯を作るのがめんどう。簡単なレシピある?」
→ 「それなら、レンジでできる親子丼はいかがですか?ごはん・鶏肉・卵・めんつゆがあれば5分でできますよ」
- 「なんとなく気分が落ち込んでる。どうすればいいかな?」
→ 「まずは深呼吸してみましょう。今日は何か好きなことをひとつやってみませんか?小さなことでも大丈夫です」
このように、どんな質問にもやさしく返事をしてくれます。
文字入力が苦手な場合は、スマホの「マイク」ボタンを使って音声で話すこともできます。(※機種により設定が必要な場合ありますので注意が必要です)
大事なのは「正しく使おうとしすぎないこと」
完璧に使おうとしなくても大丈夫。困ったときの「ちょっとした相談相手」として、気軽に話しかける感覚でOKです。AIがいったから従うのではなく、こんな意見もあるんだという風な使いかたですね。
障害者別AI活用法

では実際、AIを使って各障害別にどのようなことができるのでしょうか?こんなことが出来そうという一例をあげますので参考にしてください。
身体障害の場合(肢体・視覚・聴覚を含む)
身体障害には、手足の不自由さから視覚・聴覚の困難さまで幅広くあります。
ここでは障害の程度に応じて、特別な設定や機器がなくても、初心者がスマートフォンだけで簡単に使えるAI活用法を紹介します。
車椅子ユーザーの方向けの活用法
車椅子を利用している方にとって、「目的地までどうやって安全に移動するか」は大きな課題です。
ChatGPTのような対話型AIを使えば、移動前の不安を軽くしたり、事前準備をサポートしてもらうことができます。
- バリアフリー対応の移動ルートを一緒に考える
例:「○○駅から○○駅まで行きたい。段差や乗り換えの少ないルートを知りたい」
- おすすめのアプリやサイトを紹介してもらう
例:「エレベーターの場所や混雑情報を調べるアプリを教えて」
- 駅員さんへの伝え方やチェックリストを作成
例:「はじめて行く場所なので、準備することをまとめて」「駅員さんに頼むときの例文を教えて」
ChatGPT自体がリアルタイムの運行情報を直接教えてくれるわけではありませんが、「何を、どこで調べるといいか」「移動前に何を準備すべきか」といった事前相談相手として頼れる存在です。
視覚障害の方向けの活用法
視覚に障害がある方にとって、長い文章を読むことや、画像・イラストの内容を理解することは、日常的な困りごとのひとつです。
そんなとき、ChatGPTのような対話型AIを使うことで、「内容をかんたんに知る」工夫ができます。
- テキストの要約をお願いする
例:「このページの内容をかんたんに教えて」
- 画像や写真の内容を説明してもらう
例:「この写真には何が写っている?」「このラベルの内容を教えて」
視覚に困難があっても、ChatGPTを使えば見えにくい部分を補ってくれます。
読みづらい文章を要約してくれたり、写真の内容を説明してくれることで、情報へのアクセスがぐっと楽になるでしょう。
聴覚障害の方向けの活用法
聴覚に障害がある方にとって、現在でも字幕や手話通訳など、情報取得のための支援は少しずつ広がってきました。
その中で、ChatGPTのようなAIを活用することで、より柔軟に情報を整理したり、作業の負担を減らすこともできます。
- 音声入力を活用して会議の内容を要約
例:「この音声ファイルの内容を要約して」
- 動画や音声の内容を文字で把握
例:「この動画の字幕を3行でまとめて」
耳からの情報が得づらい方にとって、ChatGPTは「言葉を文字で受け取る」「整理して理解する」ための補助役になります。特別な設定はいらず、字幕のコピーや音声入力でやりとりするだけでも、作業の負担がぐっと軽くなるでしょう。
精神障害(うつ・不安・発達障害など)の方向けの活用法
精神障害といっても、症状や困りごとはさまざまです。
ここでは次の3つのタイプを例に、AIの活用方法をご紹介します。
- うつ病・気分障害
- 不安障害・パニック障害
- 発達障害
うつ病・気分障害の方向けの活用法
気分が落ち込みやすいときや、やる気が出ないとき。
「誰かに話したいけど、相手がいない」「人には言いにくいけど、心の中を整理したい」
そんなとき、ChatGPTに話しかけてみるという選択肢があります。
人間と同じように話せるわけではありませんが、AI相手だからこそ話せることもあるかもしれません。
- 感情を言葉にする練習
例:「今日は気分が沈んでいるけどなんでだろう?」
- 一日の過ごし方のヒント
例:「今日は気分が落ち気味。どう過ごせばいい?」
自分だけで考えていると、悩みがぐるぐると頭の中に残ってしまいます。側にいる人のように一度話しかければそこから抜け出すきっかけになるのではないでしょうか?
不安障害・パニック障害の方向けの活用法
強い不安やパニックにおそわれやすい方にとっては、事前の準備や対処法の確認がとても大切です。
ChatGPTのようなAIを使って、どのような場面で不安になりやすいかをあらかじめ整理しておくことで、実際にパニックが起きたときも、少し落ち着いて行動できる心の準備ができるかもしれません。
- 不安の原因を言語化して整理
例:「今、不安になっている理由を整理して。それって本当に起こりそう?」
- パニック時の対応方法を一緒に確認
「不安になったときの対処法を5つ教えて」「呼吸を整える方法をステップで教えて」
- 外出や緊張する場面のシミュレーション
「初めての場所に行くのが不安。何を準備すればいい?」
ChatGPTがあればなんでも大丈夫というわけにはいきませんが、少しの準備が整うだけでパニックに対しての心構えが違ってきます。
発達障害の方向けの活用法
発達障害は個人差が大きく、困りごともさまざまです。
まずは、自分がどんな場面で困りやすいのかをChatGPTに話してみるところから始めてみましょう。その上で、以下のような活用法が役立つかもしれません。
- 時間管理や予定把握が苦手な方に
例:「今日の予定を簡単に整理して、優先順位を教えて」
- 衝動買いを抑える工夫
例:「予算3000円で必要な日用品の買い物リストを作って」
- 苦手な場面の練習や声かけの準備
例:「電話応対が苦手。練習させてほしい」「相手にどう返事したらいいかわからない時の返答例を教えて」
AIが答えを教えてくれるのではなく、自分の頭を整理して答えを導き出す。AIとの対話を通じて自分の訓練にも繋がっていくのが大きなポイントです。
発達障害と吃音持ちの私が実際にChatGPTを使った際の体験談はこちらからお読みください。
AIは、あなたの生活の「味方」になるかもしれません

障害のある私たちにとって、日々の生活にはたくさんの「ちょっと困ったこと」や「なんだかうまくいかないこと」があります。
ChatGPTのようなAIは、そんな私たちのすぐそばで、話しかけるだけで力になってくれる身近な存在です。
もちろん、AIは人間ではありませんし、万能でもありません。
でも、「人には言いづらいこと」や「ひとりで抱えがちな悩み」を、少しでも整理するきっかけになってくれる。それだけでも、とても心強い存在といえるでしょう。
最初は、AIの力に半信半疑かもしれません。
けれど、「今日の予定は?」と聞いてみるだけでも、少しずつ変化が生まれてくるはずです。
できないことばかりに目を向けるのではなく、「できること」をひとつずつ増やしていく。
そんな感覚で、気軽に一歩を踏み出してみてください。
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- コスプレで届ける笑顔と元気──日本コスプレ委員会の地域貢献活動 - 2026年2月14日
- 多様性を認め、それぞれの得意で生きる社会へ|発達障害当事者会「一刻の会」が歩む支援の道 - 2026年2月12日
- すべての家族に”写真を撮る喜び”を 医療的ケア児・発達障害児にも寄り添う写真館 - 2026年1月20日

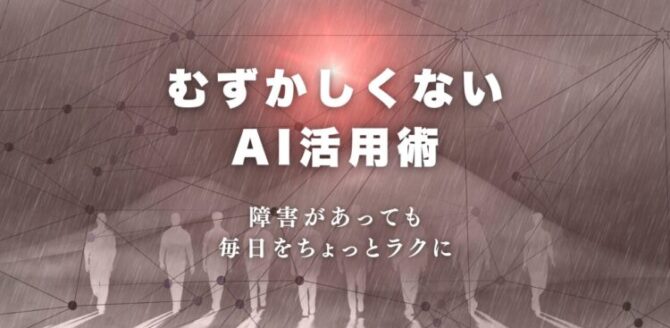

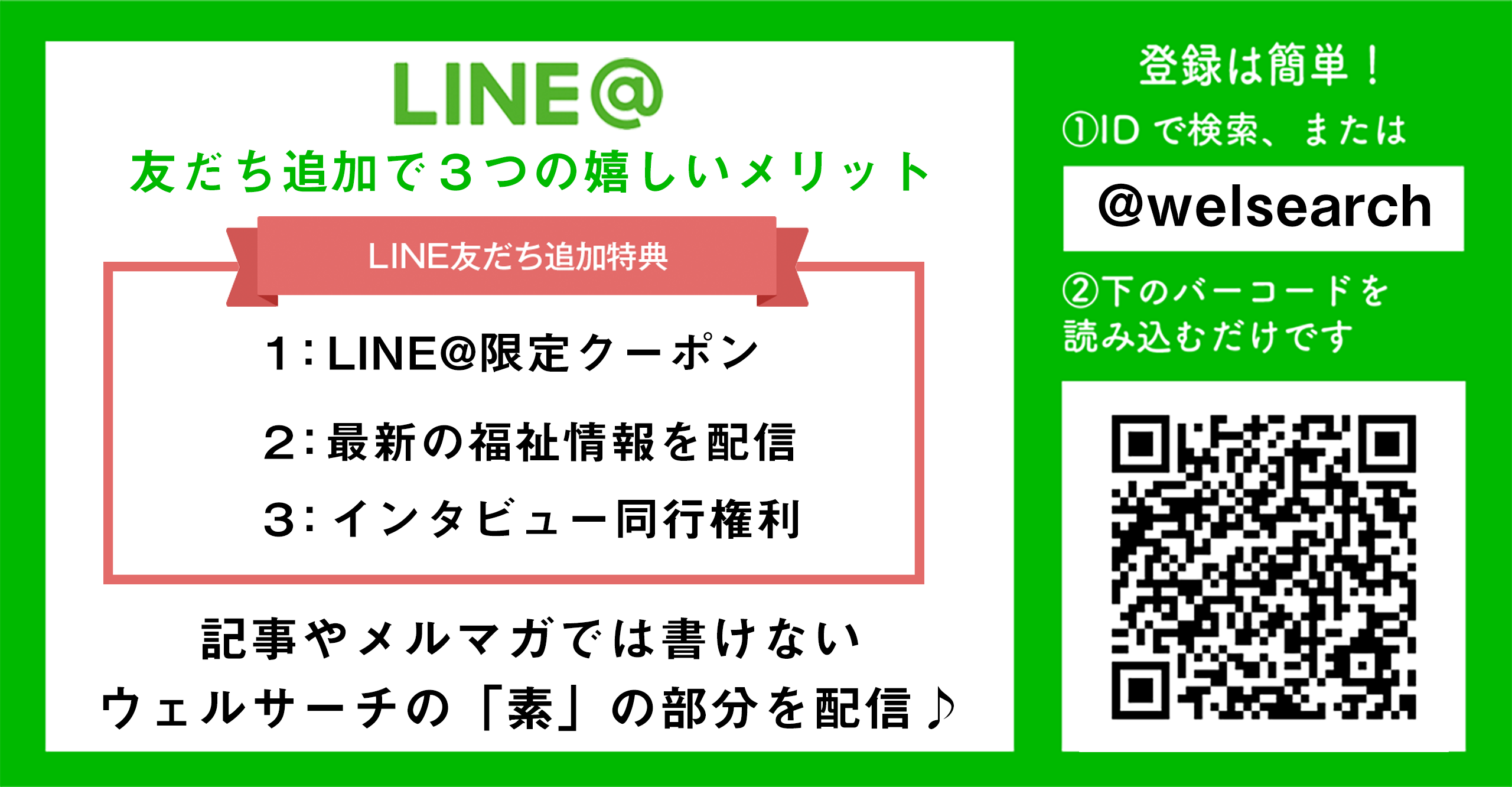
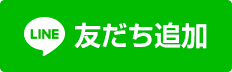
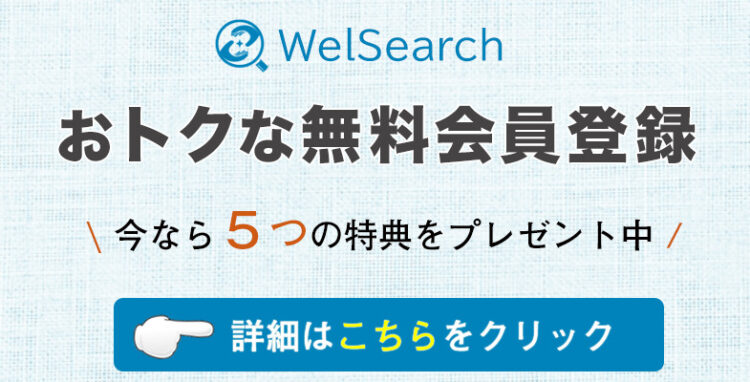

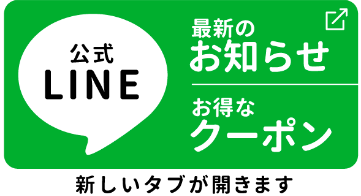


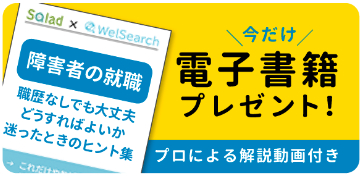
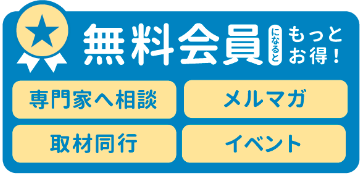

この記事へのコメントはありません。