「運転できるなら、通勤もできるでしょ?それって障害なの?」
そんなふうに言われたことがあります。
たしかに、私は車通勤をしていました。電車で通っていた時期もあります。表面的には「普通に働いている人」に見えたかもしれません。
けれど、実際には職場にたどり着くまでに消耗してしまったり、朝の準備だけで疲れてしまったり。日々働くために、大分無理をしていた記憶があります。
「通勤できる=働ける」という考え方は、一見もっともらしく聞こえます。
でもその言葉の中には、「どんな手段で」「どれだけの負担を抱えて」「どれほど無理をして」通っているか、という視点が抜け落ちていることも少なくありません。
今回は「障害と通勤」というテーマを通して、当事者の立場から感じてきた現実と、通勤を少しでも楽にするにはという視点考えてみたいと思います。
お好きなところからお読みください
「通勤がしんどい」って、どういうこと?

「通勤がつらい」
そのひと言には、人によってまったく異なる理由が隠れています。
障害の種類や状態によって、感じる負担も、対処の方法もまったく違います。 見た目には分かりづらいことも多く、周囲に理解されにくいまま、日々を過ごしている人もいることをまず知っておきたいと思います。
私の場合(発達障害・吃音)
私にとって通勤でつらいと感じたのは主に2つありました。
- 多くの人が狭い場所に一緒にいることでの精神的負担
- 朝の準備や段取りに時間がかかり、毎日出発がギリギリ
今でもたまに電車は使いますが、やはり人の目が気になったりで落ち着いて移動することができません。電車に乗れないというほどでもありませんが、やはり移動は車の方が気楽だったりします。
電車より車が楽というと「なんで運転して疲れる車より電車の方が疲れるの?」と聞かれることがありますが、やはり車は自分のプライベート空間という意識があり、また自分のペースで移動できる。そのような部分が大きいと感じます。
さまざまな障害と「通勤の壁」
障害と一口にいっても、多くの種類があることは過去の記事でも何度も申し上げています。通勤に対する問題も同じように多くあり、ここでは主に障害別にこのようなことで困っているだろうという例をあげてみます。
感覚過敏(自閉スペクトラム症など)
- 匂い・音・他人の体温など、日常的な刺激が“拷問”のように感じられることも。
- 満員電車は「我慢すればいい」ものではなく、生理的に耐えられない人もいます。
感覚過敏な方にとって、電車やバスといった密室空間はさまざまな面で苦労を強いられます。人々の話し声、混ざり合うアナウンス。「香害」とも呼ばれる香水や柔軟剤の匂い。これらは健常な方にとっては当たり前の環境でも、感覚過敏を持つ方にとってはまさに通勤で消耗してしまう一例です。
精神障害(うつ病・双極性障害など)
- 体調や気分の波があるため、毎日決まった時間に起きて通勤することが困難。
- 「起きられない」「外に出られない」は、“甘え”ではなく症状そのものです。
毎朝目覚ましで起きて、朝食を摂り、玄関のドアを開ける。当たり前の日常に感じますが、精神に障害を持つ方にとっては、朝起きることがすでに辛さのはじまりです。「今日は会社に行きたくないな」という気分は多くの人が感じる感情かもしれませんが、障害がある方にとってはドアをあけるのにも精神力が問われます。この段階で消耗して仕事に集中できない。まさに悪循環といえるでしょう。
視覚・聴覚障害
- 白杖での通勤は人混みでのストレスが大きく、誘導設備にも限界があります。
- 聴覚障害のある人はアナウンスが聞き取れず、緊急時の対応に不安を抱えながらの通勤はそれだけで体力や精神的に消耗してしまいます。
公共交通機関ではバリアフリー化が進んでいます。それでも、やはり視覚や聴覚に障害がある方にとっては少し移動するだけでも困難がつきまといます。特に通勤時間ともなれば、他人は自分のことで精一杯。白杖などをもっていても、配慮が期待できないことも多々という状況です。せめて人が少なければなんとか、という人も多いのではないでしょうか。
内部障害(心臓疾患・腎不全など)
- 外見では分かりにくいため、周囲に理解されづらい。電車通勤などでは席を譲ってもらえないケースも。
- 通勤のような「時間・体力を縛られる行動」で体調が悪化しやすいケースも。
一見何も不自由を抱えてない方を注意深く観察してみると、実はヘルプマークをつけている場合も。優先席などではヘルプマークをつけていもなかなか席を譲ってくれといえる雰囲気がないこともあり、通勤へのハードルが高くなることも。
通勤という行為が「見た目以上にハード」なこともある
ただ電車やバスにのって移動する。
通勤というと健常な方にとっては「都会の満員電車はきついよねぇ」程度のことなのですが、障害を抱える方にとっては上記のようなこともあり、ただの移動というわけにはいかないのです。では、どうしていけばいいのでしょうか?
試行錯誤する企業側
合理的配慮が求められる企業側ですが、画一的に通勤面での配慮を求めるのも難しいの事実です。よく言われる時差通勤一つとっても、時間の自由の効くデザイナーやプログラマーの一部と、チームで動く工場勤務や販売接客業では取り入れるのは難しいでしょう。
通勤の負担を減らす手段も多種多様。企業側にとってもなるべく配慮をすることで仕事へのパフォーマンスをあげて欲しいのが実情でしょう。
ここでは、主な通勤に対する配慮をみていきたいと思います。
事例1:障害者送迎バスの導入と運用
ある製造業系の企業では、通勤に困難を抱える障害者従業員のために、リフト付きの送迎バスを導入しています。
主に車椅子を利用する従業員を対象とし、専用の乗降支援スタッフが同乗。
通勤ラッシュを避けた柔軟な出発・到着時刻に対応し、体調に合わせた勤務が可能に。
障害者にとって、満員の状況というのはそれだけで体調を崩す原因ともなります。企業の通勤バスを運行している会社は数多くありますが、一部の会社では障害に応じた支援があります。このような手段があれば、車椅子で通勤をためらっている方や、知らない人が満員のバスはちょっとという方も安心ですね。
事例2:時差通勤の工夫された取り組み例
通勤での配慮と言われれば、「オフピーク通勤」などとも言われる時差出勤かと思います。企業によっては取り入れることも難しい制度ですが、いろいろな工夫によってとりいれられている例もあります。
ある地方自治体の事務局
フルタイム勤務を「4週間で155時間」とする制度を導入し、週4勤務・時差出勤など柔軟な時間運用を職員に許可。
→ 通勤混雑を避けたい障害者職員や介護中の職員も、ライフスタイルに応じて働ける環境が整備された。中堅企業の印刷業者
始業時刻を30分刻みで自由に選択できる制度を導入。感覚過敏のある社員が混雑を避けて通勤できるようになり、遅刻や欠勤が大幅に減少。
→ チームワークと柔軟性の両立に成功した好事例。画一的に時間をずらすのではなく、企業によって柔軟に時差出勤を取り入れられれば効果はありそうですね。
障害者側のちょっとした工夫
企業側でもさまざまな配慮が行われていますが、障害を持たれる側としては何ができるのでしょぅか?
完全に通勤の負担を減らすことは不可能でも、ちょっとした工夫で通勤が楽になるかもしれません。
身体障害(車椅子・肢体不自由など)
身体に障害を抱える方にとって、通勤ルートは大きなポイントです。通勤ルートを以下のツールを使って見直してみるのはいかがでしょう?
アプリによるエレベーター・スロープの事前確認
→ 鉄道会社アプリ(例:東京メトロ「my! 東京メトロ」)などで利用駅のバリアフリー設備を確認。- Googleストリートビューで道順と地面の状態を事前確認
→ 凹凸のある歩道や傾斜の強い道を事前に避けるルートを選べる。
アプリなどで普段使うルート以外を見直すと、思わぬ発見があるかも知れませんよ?
精神障害・発達障害(感覚過敏・パニック障害など)
精神に障害を抱える方にとって、周りに人がいるというだけで不安になります。音などの感覚をできる限り遮断する方法をもっていくといいでしょう。
ノイズキャンセリングイヤホン+自然音設定
→ 電車内の騒音から自分を守り、落ち着きや集中力を保ちやすくする。安心できる休憩スポットを事前に把握
→ 通勤ルート上にあるトイレ・カフェ・駅ベンチなど「一息つける場所」を覚えておく。
「いかに自分の落ち着ける環境を作れるか」を考えて、少しでも不安になったら休める環境を作っておく。それだけで安心感が違うと思います。
視覚障害・聴覚障害
公共交通機関のバリアフリーが充実していますが、個人でも利用できる便利なアプリなどもあります。
乗り換えアプリの読み上げ機能や振動機能の活用
→ 乗り換えアプリには、読み上げ機能や振動などで通知をしてくれる機能がついているものがあります。それにより乗り過ごしなどの問題も解消されやすく。自分の状況を伝えやすくする
→ ヘルプマークや、障害があることを伝えるカードを見やすくすることで回りに伝える。アプリは万能ではありませんが、それでも最新技術によってあなたをサポートしてくれるでしょう。
毎日の通勤が、少しずつ私をすり減らしていた

私はこれまで、いくつかの工場を中心に、正社員・派遣社員の両方を経験してきました。通勤は車と電車の両方を使ったことがありますが、どちらも「楽」とは言えません。
電車通勤では、決まった時間に遅れず乗らなければならないという緊張感や、人と同じ空間にいることの息苦しさがありました。
会社のことを考えるだけで憂うつになり、「電車が止まってくれたらいいのに」と願った朝も、少なくありません。
車での通勤は、確かに人の視線を感じにくい分、精神的には少し楽でした。しかしその一方で、自分の不注意が事故につながるのではという不安も常にあったのも事実です。
発達障害を持つ私にとって、それはまた別のプレッシャーでもあったのです。
毎日きちんと通勤していたとはいえ、「通勤がつらい」と感じる余裕すら持てないほど、日々をこなすことに必死だったように思います。
- 人前に出るために身だしなみを整えること
- 時間に間に合うように家を出ること
- 体調にかかわらず、毎日同じように出社すること
今思えば、その時点ですでに集中力や気力を大きく削られていたのだと思います。
「運転もできるし、通勤できてるでしょ? それって障がいなの?」
そんなふうに言われたこともあります。
確かに、私は運転ができて、車で通勤もしていました。でもそれは「通勤に支障がない」という意味ではありません。実際には、無理をしてでも通勤していた。それが正直なところです。
もし、当時の自分に声をかけられるとしたら、こう言うでしょう。
「世の中には、もっと多くの手段がある。まずは立ち止まって、他に何かできることがないか探してみな」と。
今、私はフリーランスとして、在宅で働いています。 このような働き方があることを、もっと早く知っていれば。 無理に自分を押し込めるような日々を、少しは減らせたかもしれません。
通勤をがんばることがすべてではありません。
「続けられる形を見つけること」が、長く働き続けるためにはとても大切なのだと、今では実感しています。
通勤を「当たり前」にするために

障害があることで、「通勤」そのものが大きなハードルになる。ですが、その課題の多くは、制度やテクノロジー、そして職場の理解によって、確実に乗り越えられるものになってきています。
合理的配慮とは、「できないことを可能にするための橋」。
通勤においても、それは特別な“優遇”ではなく、すべての人が公平に働ける環境をつくるための整備にすぎません。
一人ひとりの事情に寄り添った出勤時間、移動手段、仕事とのバランスのとり方。そうした小さな配慮が積み重なることで、通勤のしやすさは働きやすさにつながり、ひいては職場全体の安定や成長にも結びついていくのです。
障害があっても働きたい。そのためには障害がある方にもできることはたくさんあります。何かまず一つ試してみて、今日は少し通勤が楽だったかも。そのような積み重ねが自信にも繋がってきます。
「障害者が働き続けやすい社会」は、同時に「すべての人にやさしい社会」。制度の整備と、現場の対話。その両輪で、無理なく通勤できる未来を一緒に作っていきませんか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- すべての家族に”写真を撮る喜び”を 医療的ケア児・発達障害児にも寄り添う写真館 - 2026年1月20日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【後編】 - 2026年1月12日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【前編】 - 2026年1月11日



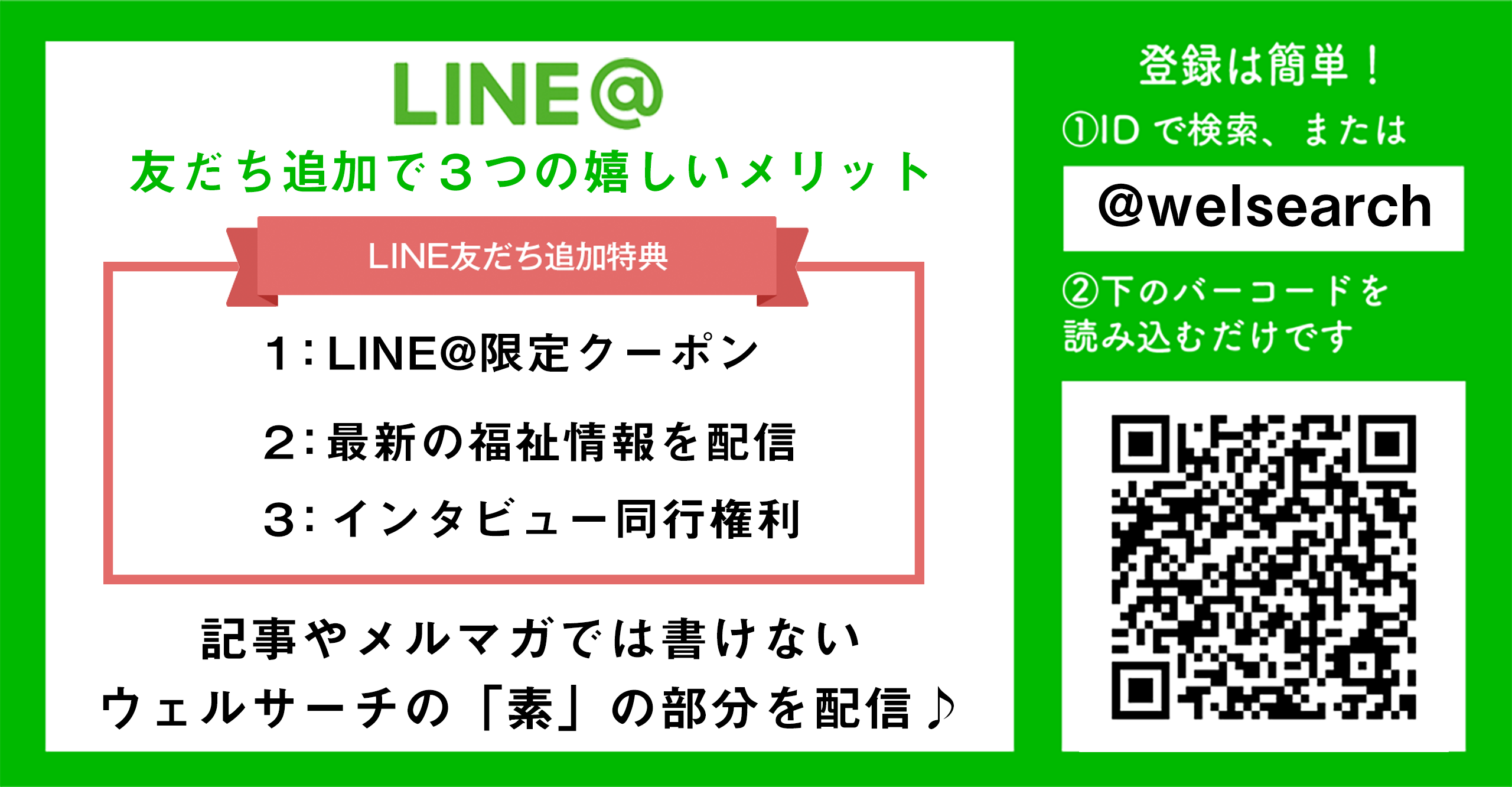
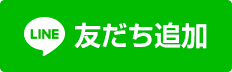
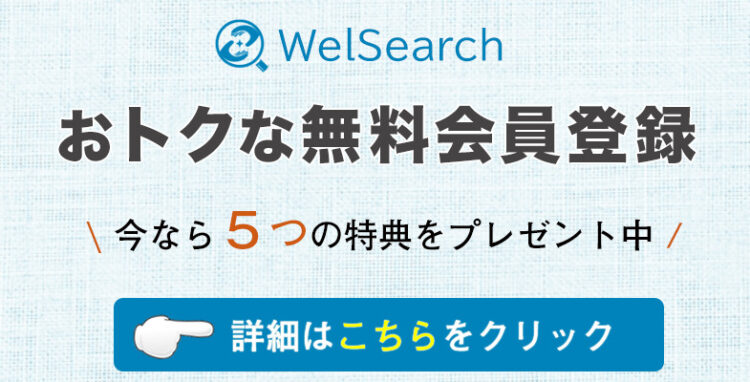










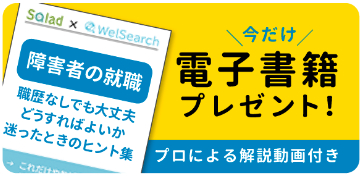
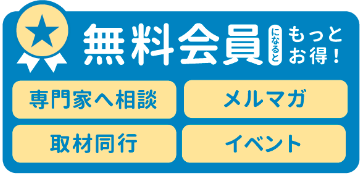

この記事へのコメントはありません。