介護現場の人材不足や地域格差といった課題に対し、行政はどのように寄り添い、支援の仕組みを整えているのでしょうか。
地方自治体でもさまざまな取り組みが行われる中、今回は栃木県保健福祉部高齢対策課の関口様に取材しました。
前編は下記からご覧いただけます。
介護現場を支える人材確保や人づくりの最前線|栃木県保健福祉部が語る現状と課題〜前編〜
後編では、栃木県が設置を進める「介護生産性向上総合相談センター」の役割や、テクノロジー導入時の支援、地域ごとの人材難への対策、そして県全体としての今後のビジョンまで、具体的にご紹介します。
お好きなところからお読みください
介護現場に寄り添う栃木県の役割

既存の人数だけでは回らないといった状況や、「では、どうすればよいか」といった相談が出てきた場合、こちらでそうした事業者をサポートする手法を提案し、このような取り組みがありますといったことを紹介したり、専門的な機関につなぐ拠点として、2025年7月に設置する予定です。 これからの取り組みとして、この機能を活用して事業者の不安解消の拠点にしたいと考えています。
不安に思っていたり、どうすれば良いかと考えているものの、なかなか他の事業所に聞きづらいということがあるのではないかと思います。ノウハウや解決策については、セミナーなどを通じて広く横展開することも想定しています。
経産省の補助金が活用できるのではないかとか、IT補助金や中小企業庁の支援、融資などといった相談についても、そうした話が出た場合はそちらにつなぐことも可能な仕組みにしているので、まずはここを入り口として活用していただき、一元的に対応しようという考えで取り組んでいるところです。
介護業界における専門家を充実させる
介護事業所によっては、「こういうのは人間らしくない。やっぱり人間の手で入れてあげたい」と思うかもしれません。その場合は、このリフトを導入することがその事業所にとって正解ではなく、腰痛予防のための基本動作について講習した方が、その事業所が本当に望んでいることに応えられます。 それぐらい個別性があることだから、何を入れれば正解という世界ではありません。慎重に考えなければいけないと思います。
見守り機器などの活用についても、結構繊細な部分があります。ベッドの位置のズレがセンサーの検知精度に大きく影響するなどよく聞く話ですので、適切な運用に配慮しなければなりません。
今度開設する介護生産性向上総合相談センターでは、セミナーを開催したり、専門家を実際に事業所に派遣したり、現場で指導するといった機能を持たせようとしており、このような課題に対応していきたいと考えています。
時代は確実に進展してきているものの、どのように楽に使いこなせるようになるかという点については、県がしっかりと手を入れていかないといけない部分だと感じています。
栃木県内における地域格差
地域で必要なサービスが提供できなくなると、その分遠くの事業所の力を借りなくてはならなくなってしまいます。そういう地域がある一方で、都市部を中心に事業所が集まる傾向があり、まさに地域格差があるのが現状です。
現在どのように対応しているかというと、ケアマネージャーが「この方だったら、ここからなら行ってもらえそう」といった形でつないでくださり、なんとか今その地域のサービス断絶が起こらないようにしているという状況だと思います。 そうした地域でも、せっかく来てくださる訪問介護事業者で人が足りなくなってしまったら、そういった対応もできなくなってしまうため、行き着くところは、きちんと人材が確保できるようにしておかないと、今よりもさらに後退してしまうということになります。 最終的には人材確保対策に行き着くのだなと思います。
これは、新人の訪問介護員が一人前になるまでの間は先輩をつけて2人体制で対応するのですが、現在の介護保険制度では1人分しか報酬が出ません。 これまでは、事業所がいわゆる投資として持ち出しでやっていた部分だったので、そこに補助をするという仕組みを作りました。そうすれば、事業所も負担が重くならずにすむため、安心して新しい人を呼び込めるという仕組みにしたいと考えています。 そうした一つ一つの事業で、どれぐらい現在の地域格差の拡大を食い止められるかということを考えながら取り組んでいます。
栃木県の介護業界における横のつながり
県だけ、あるいは市町村だけ、事業所だけという単独での対応では限界があると思います。県も市町村も事業所も業界側も、みんなで知恵を出し合って、まずこれをやっていこうという方向性を決めることです。 今の時期だと、介護現場の生産性向上の取り組みを推進しなければならないという認識で、介護テクノロジーを活用した業務改善などの様々な施策を用意していますが、こうした取り組みについてもしっかりと意見を聞いて、「まずこれをやっていきましょう」という方向性をみんなで決めていく必要があると思います。 もちろん、予算も確保しなければならないため、ある意味、施策の意見や具体的な取り組み、どういうことをやればよいかということを検討する場として、こういう方向でやっていきましょうという方針をみんなで決めるということを現在心がけています。 その第一弾の成果が、この介護生産性向上総合相談センターにつながってくるという形になります。
そういう意味でも、私たちはこの革新会議で現場の声を頂きながら業務を進めようとしている状況です。栃木県のこうした姿勢が伝わっていけばいいなと思っています。
地域格差と人材不足に挑む栃木県のこれから

ですから、現在行っている事業はもちろんしっかりと継続し、必要な人に必要な支援を届けていきながら、栃木県で働き、そのまま介護人材として定着していただけるような仕掛けを、県としてもどんどん積極的な姿勢で取り組んでいきたいと思っています。 まず当面は、このリアルな拠点である介護生産性向上総合相談センターが事業所のサポート拠点としてできますので、ここを発射台としながら、様々なセミナーや現場支援を発信していきたいと思います。引き続き県として一生懸命頑張って参ります。
私たちが支援しているのは、まずその下支えをするという目的でありますが、今後は、これだけではなく、これから介護業界に期待を持っていらっしゃる求職者の方々に対して、これだけの様々な支援を行っているとか、介護の世界では国家資格を取得し、働くスキルを身につけることができるといった、きちんとしたメッセージを伝えていかなければならないことが、非常に大きな課題意識となっています。 ですから、事業者にはもちろんのこと、県内外の求職者の皆様についても、しっかりとアピールしていくという所を大きな意識として、これから事業展開を進めていきたいと考えています。
栃木県保健福祉部とのインタビューを終えて
介護の現場で今、求められているのは単なる人材の確保だけでなく、「定着」と「納得」を生む仕組みづくりです。
栃木県では現場の声を丁寧に拾い上げ、補助制度や相談支援、テクノロジー導入のサポートを通じて、多様な事業所に寄り添う体制を整えています。
今回のインタビューからは、現場と行政が共に手を取り合って課題解決に向かう姿勢、そして「地域を支える力は人である」という確かな思いが伝わってきました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- すべての家族に”写真を撮る喜び”を 医療的ケア児・発達障害児にも寄り添う写真館 - 2026年1月20日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【後編】 - 2026年1月12日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【前編】 - 2026年1月11日




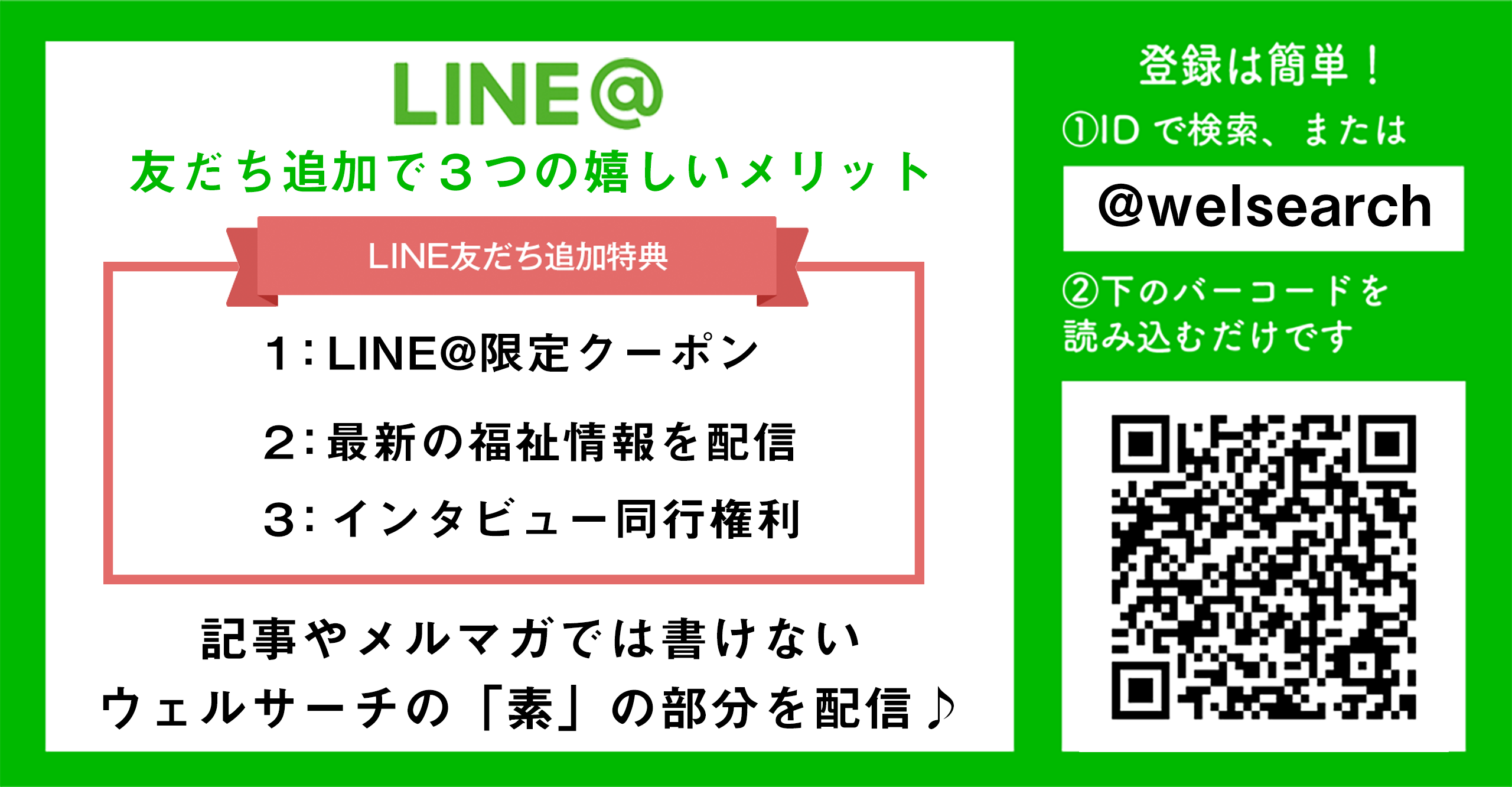
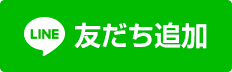
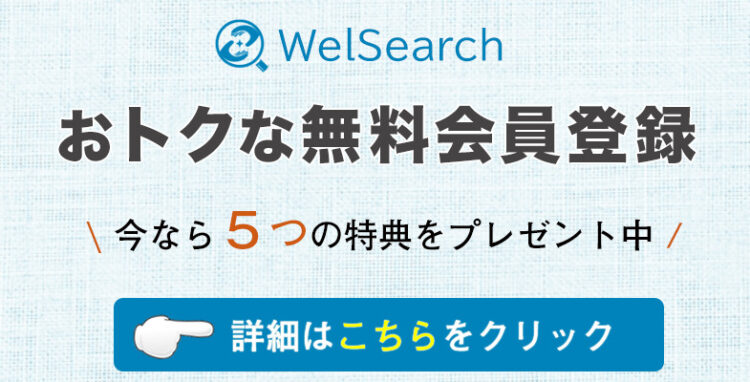

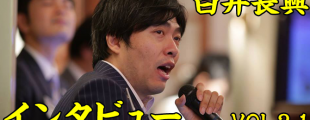





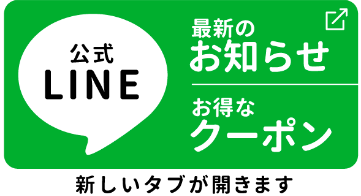


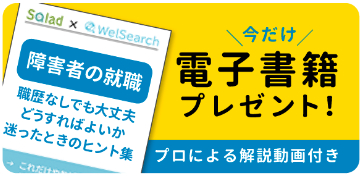
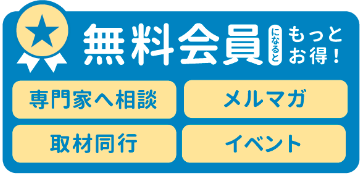

この記事へのコメントはありません。