定着率約90%を支えるワークリアの具体的な支援策とは?
週1回の面談、業務量調整シート、感覚過敏への配慮など、現場で実践される仕組みを詳しく紹介します。
転籍後も同じ環境で働ける制度や、マネジメントを担うまでに成長した事例もお伝えします。
お好きなところからお読みください
定着率約90%の秘密は?相談しやすさを生む3つの仕組み

週1回の面談と「業務量調整シート」で可視化する
——精神・発達障がいの方への具体的な支援内容について教えてください。
——津留
入社いただいた後、週に1回30分の振り返り面談を設けています。この頻度は他社様と比べても多い方だと思います。担当のマネジメント社員が付き、その方と振り返りができる仕組みです。
面談では、仕事の振り返りだけでなく、体調面の相談もできます。一般雇用の場合、精神・発達障がいの方でも面談は月に1回程度が一般的だと思いますが、当社では週に1回実施しているため、相談しやすい環境になっています。
これは全員に提供している支援です。
その他にも、障がい者雇用ならではの配慮として、10分の小休憩制度を設けたり、休憩室を設置しています。
感覚過敏への対応では、座席パーティションの設置や耳栓の使用許可などを実施。個々のニーズに応じた働き方を柔軟にサポートしています。
——発達障がいの方は過集中になったり、細かい作業が苦手だったり、感覚過敏があったりと、個々に配慮が必要な部分が異なると思います。本人からの配慮の要望にはどのように対応されていますか。
——津留
出入りが多いオフィスだと、人が立った瞬間に気づいてずっと見てしまい、仕事に集中できなくなることがあります。そういった場合は、ヘッドホンを着用してもらったり、仕切りを準備したりしています。
「ヘッドホンを使ってもいいですか」「座席の配置を工夫してほしい」といった要望は、かなり柔軟に上がってきます。座席配置などは頻繁に調整していますし、そうした個別の配慮には柔軟に対応しています。
——そうした配慮に即座に対応できるというのは、大きなメリットですね。
——津留
はい。まず、ハード面において対応してもらえることは、当事者の安心感に大きく寄与すると思っています。
ソフト面では、週に1回の振り返り面談で社員と接する時間を確実に取っているため、相談ができなくて困るということはほとんどありません。その上で、ハード面において、見える形でどう対応するかが重要になってきます。
——仮に最初から上手くいかなくても、ある程度フォローし合える余裕がある環境なのでしょうか。
——津留
先ほど説明したように、業務の種類が多いというのはかなり大きな要素です。
「業務量調整シート」という仕組みがあり、2週間に1回程度、本人たちにアンケートを取っています。
業務量をA・B・Cの3段階で本人が自由に選択できます。例えば『Aを選択しているので余裕がある。もう少しレベルの高い仕事に挑戦したい』といったコメントを記入できます
また、「何時から何時まで空いています」「この仕事の後は比較的空いています」といった情報も共有できます。
このシートは振り返り面談以外でも、本人たちが今の自分の状態を表現できるツールになっています。お互いに見えるようになっているため、「この人が空いているなら、この仕事をお願いしたい」といったやり取りを本人たち同士で行うこともあります。こうした形で、フォローアップや業務の調整を行っています。
——精神・発達障がいの方は、どうしても疲れてしまって仕事ができなくなることもあると思います。
——津留
無理をしすぎてしまう傾向があるため、遠慮なく「C(余裕がない)」を選択できるようにしています。他の人がCを選択しているのを見ると、「自分もつけていいんだ」と思って記入しやすくなる効果もあります。
見えないようにするのではなく、あえてお互いの状況を可視化することで、「この人がこれくらいと書いているから、自分もCで書いておこう」と感じられる環境を作っています。これが心理的な安全性につながっていると考えています。
マジョリティであることの安心感
——安心感があるからこそ、無理をしないという選択ができるということですね。
——津留
自分たちがマジョリティだという感覚を持てることが大きいと思います。未経験から働き始める方が多いので、健常者がたくさんいる職場にいきなり入ると、どうしても「どうしよう」と不安になってしまいます。
同じような立場の人がたくさんいて、「言ってもいいんだ」とわかると、簡単に相談できるようになります。それは非常に大きな要素だと考えています。
——特にASD(自閉スペクトラム症)の方は、「空気が読めない」と言われた経験から、自分の意見を言い出せなくなっていることも多いと思います。そういった意味でも、この環境は重要ですね。
——津留
そういった経験をたくさんしてきたことは、面接の時にも教えてくださいます。当社では、みんな何らかの障がいを持っていますが、誰がどんな障がいを持っているかは、お互いに公表していません。自分はうつ病だけど、あの人はうつ病ではないかもしれない、といった状況です。
「自分も何かあるし、相手も何かあるかもしれない」という前提で接しているため、お互いに優しくなれます。
何か問題が起きても、ある程度柔軟に対応できるという雰囲気をお互いが持てているのは、大きな強みだと思います。
——お互いが障がい者だからこそ仲間意識がありつつ、過度に干渉しないバランスが取れているのですね。
——津留
過去にいろいろな経験をしてきたことは、自分も同じなので理解できます。そのため、変に干渉しすぎないように気をつけてくださる方が多いです。
これも、うまくいっている要因の一つだと考えています。
これらの仕組みが定着率約90%を支えているんですね。
特に印象的だったのは、「自分たちがマジョリティ」という安心感です。
同じ立場の人が多いからこそ、「言ってもいいんだ」と思える。この環境が、相談のハードルを下げているのだと感じました。
障がい者同士のトラブルをどう防ぐ?境界線の引き方

——障がい者が集まるとトラブルが起きやすいという話も聞きますが、実際はいかがですか。
——津留
ゼロではありませんが、当社では、健全な職場環境を維持するため、業務上の関係とプライベートな関係には明確に線引きをしています。そのため、職場での円滑なコミュニケーションは促進します。
一方、業務時間外の個人的な関係については、会社として過度に介入しないというスタンスを基本としています
——健常者のスタッフがしっかりとサポートするからこそ、成り立っているということですね。
——津留
障がい者だけになってしまうと、逆に辛くなってしまう面もあるかもしれません。
障がい者の中にリーダーをしてくださっている方もいらっしゃいますが、「障がい者だから相談しやすい」という理由で、一時期その方に相談が集中してしまったことがありました。
相談が集まりすぎると、本人が苦しくなってしまいます。フォローアップしようとリーダーを引き受けてくれたものの、キャパシティがいっぱいになってしまうケースもありました。
これは障がい者雇用に限らず、一般の組織運営と同じ課題です。適切な役割分担や、必要に応じた各部署との連携が求められます。
事業として合理的な判断をするためには、相談が分散する仕組みが必要です。また、『ここが相談先だ』と認識できる場所があることが非常に大切だと考えています。
——通勤がつらいという方や、リモートワークを希望される方もいらっしゃいますか。
——津留
当社の場合は逆に、出社したいという方が意外と多い傾向があります。
ただ、完全なフル出社よりも、週に1回か2回程度リモートワークがあると働きやすいという方もいらっしゃいます。そのため、リモートワークの基準を設けており、基準を満たしていれば週に2回までリモートワークが可能という制度にしています。
一方で、オフィスに来てみんなと会いながら仕事をする方が良い、相談しやすいという理由で出社を好む方もいらっしゃり、そういった方はずっと出社されています。働き方の選択肢を用意することで、それぞれに合った形で働いていただいています。
——この環境が良いからこそ、出社したいという気持ちになるのでしょうね。一般就労で人間関係がうまくいかなかった方が、ここでは良好な関係を築けているということでしょうか。
——津留
前職であまりうまくいかなかったという方も確かにいらっしゃいます。
前職でも障がい者雇用だったけれど、それでも合わなかったというケースもあります。環境の作り方は、一般雇用でも障がい者雇用でも、それぞれ企業や組織側の意図によって違いが出る部分ですね。
「質問していい」前提を作るインターン制度
—— このサテライトオフィスでは、周りもみんな相談し合えることがわかっていますし、相談できる人がちゃんといるという安心感がありますね。
——津留
比較的どのタイミングでも声をかけて良いということを伝えた上で、入社していただいています。
また、当社では入社前にインターンを経験していただくのですが、インターン期間中からいつでも質問できる体制を作っています。
「わからないことがあったら聞いて良いんだ」という前提を作った上で入社してもらう流れにしているため、いつ聞いたらいいか、どう聞いたらいいかといったことをあまり考えなくても大丈夫だとお伝えできています。
質問のハードルが低い環境であることを体感した上で入社を決められることは、活躍の土台になっていると思います。
——不安感ではなく安心感を持って働けるというのは、本当に大きいですね。.
障がい者同士の助け合いに頼りすぎず、相談先を分散させる仕組みが印象的でした。
そして、インターン期間中から「質問していいんだ」という前提を作ることで、入社後も相談しやすい環境が生まれています。不安ではなく安心。この土台があるからこそ、長く働けるのだと感じます。
サテライトオフィスはどんな環境?現場レポート

取材時、秋葉原のサテライトオフィスを見学させていただきました。いくつかの区画に区切られたオフィス内では、多くの障がい者の方が真剣に業務に取り組んでいて、突然の訪問にも関わらず、皆様丁寧に対応してくださいます。
私も発達障がいを持つ身として、サテライトオフィスの環境を当事者目線で見させていただきましたが、物理的な工夫の数々を目の当たりにして、さまざまな配慮があるからこそ安心して働けるのだと実感しました。
特に印象的だったのが、それぞれの机が個性的だったことです。通常、オフィスの机といえば、書類や事務用品、パソコンがある殺風景な印象ですが、ここでは好きなキャラクターの小物や写真など、それぞれの個性が出るアイテムがちりばめられていて、それでいて整理されています。
周囲が気になる人へのパーティションや防音対策など、集中するための工夫はよく見かけますが、発達障がいがある人にとって一番大切なのは、「自分が落ち着ける環境」を整えられるかだと思います。
仕事に影響がない範囲で、自分の最高の環境を作れる——それがサテライトオフィスの魅力なのだと感じました。
そして、オフィス見学の中で特に興味深かったのが、前編でもお伝えした「別の企業の障がい者社員が同じサテライトオフィスで働いている」という光景だった。この仕組みについて、改めて詳しく伺った。
転籍後も同じ環境で働ける仕組み
——安藤
今ご覧いただいた部屋で働いている方々は、実はもともとワークリアで1年以上勤務していた方たちなんです。
つまり、ワークリアの障がい者雇用で1年ほどしっかりとスキルを身につけた後、面接を経て別の企業に所属を変更したものの、同じ場所で働き続けているという形になります。
転職する際、場所が変わると環境の変化が大きなストレスになります。健常者でもストレスがかかるものですが、特に精神・発達障がいをお持ちの方は環境に慣れるまでに時間がかかり、それが原因で体調を崩してしまうこともあります。
当社のサービスでは、働く場所も、サポートするスタッフも変わりません。業務内容は転職先の仕事になるため変わる場合もありますが、周囲の環境が変わらないため、ストレスがない状態で新しい仕事やキャリアに挑戦できます。その結果、転職した後も長く働いていただいています。
——環境が変わらないというのは、本当に大きいと思います。特に人間関係が変わってしまうと、それが原因で仕事を辞めることも多いですから。私自身、以前工場で正社員として働いていた時に、人間関係のトラブルで仕事が嫌になった経験があるので、環境の安定は何より大切だと感じます。
——津留
本人の希望次第ですが、慣れるまでずっとこのサテライトオフィスで働いていただくことも可能です。また、オンライン上でコミュニケーションを取りながら、少しずつ関係性を構築できてきたら、その企業のオフィスに移動するという選択肢もあります。実際に、今そのトレーニングをしている方もいらっしゃいます。
——本当に柔軟に対応できる仕組みですね。
「自分が落ち着ける環境」を整えられることが、サテライトオフィスの魅力なんですね。そして、転籍後も同じ場所・同じスタッフで働ける仕組みは、環境変化が苦手な障がい者にとって大きな安心材料です。
人間関係が変わらないからこそ、新しい仕事に集中できる。この柔軟さが、長期雇用を支えているのだと実感しました。
今後の展望は?企業内への移行と新しい支援の形

——今後の展望について教えていただけますか。
——津留: 拠点展開としては、現在、秋葉原、渋谷、千葉の3拠点でサテライトオフィスを運営しています。まずは、これらの拠点をしっかりと埋めていきたいと考えています。
秋葉原が6部屋、渋谷が約10部屋、千葉も約10部屋という規模で展開しており、これを1年程度で企業様に使っていただけるよう埋めていくことを目標に動いています。
さらに大きな目標としては、サテライトオフィスを利用しながら、企業内に移動していける事例を増やしたいと考えています。
一般的なサテライトサービスは、サテライトで雇用して終わりという形が多いのですが、当社の場合は企業のオフィスが近くにあることも多いため、社員の方に定期的に来ていただいたり、本人ができる仕事があれば企業に行ってやっていただくといった柔軟な働き方を実現したいと思っています。
こうした新しい支援の形を通じて、企業の中に障がい者雇用の体制を構築していくサポートをしていきたいと思っています。
—— 段階的に成長して、最終的には自立していくという形ですね。
——津留
実際に、未経験で入社した方が、当社の本社の障がい者雇用とは全く関係ない部署に配置転換され、そこで正社員のメンバーをマネジメントするまでに至った事例もあります。
そういった事例がどんどん広がっていくと、障がいに対する認知が変わり、誰もがやりがいを持って活躍できる組織の体質が実現できると思います。
読者へのメッセージ
—— 最後に、この記事の読者に向けて、メッセージをいただけますか。
——津留
法定雇用率の引き上げもあり、社会全体で障がい者雇用への関心が高まり、その動きは大きな広がりを見せています。画一的な働き方ではなく、個々の状況に合わせた様々な選択肢が、今まさに求められているのではないでしょうか。
それに応じて、企業側も受け入れ方を考え、前向きに進めようとしている企業がたくさんありまして、先日開催したイベントにも多くの企業にお越しいただき、こんなに来ていただけるのかと驚きました。
企業の担当者は、やり方がわからず苦戦していたり、自社に合う雇用の形がわからず困っていることが多いのです。
当事者の方は、法改正などで風向きが変わっている部分もあるため、積極的に情報を集め、ご自身に合った選択肢を見つけていただくことが重要です。新しい働き方が生まれていることを知って、可能性を広げるチャンスを掴んでいただきたいです。
——障がいがあっても働きたいけれど、どう働いていいかわからないという方が多いのが現状ですね。
——津留
日々の業務では、障がいのある社員の方々にいつも助けられています。特に、定常的な仕事だけでなく、急なタスクにも快く対応してくれるので、本当に頼りになる存在です。
未経験から入社した時は、本人たちもこうなるとは想像していなかったと思いますが、できることはたくさんあります。
諦めないでいただきたいですし、「障がいがあるから」という先入観で自分を制限しすぎないでほしいです。未来を見てくれたら良いなと、みんなを見ていて思います。
——ありがとうございました。
そして、未経験から入社した方が正社員のマネジメントを担うまでに成長した事例。
これらは、「障がい者雇用=単純作業」という固定観念を覆すものです。
適切な支援と環境があれば、ここまで成長できる。ワークリアの取り組みは、障がい者雇用の新しい可能性を示しています。
取材を終えて
定着率約90%——この数字の背景には、「相談しやすさ」を徹底的に追求する仕組みがありました。
週1回の振り返り面談、業務量を可視化する調整シート、感覚過敏への柔軟な配慮。そして何より、「質問していいんだ」という前提を作るインターン制度と、「自分たちがマジョリティ」という安心感。これらが組み合わさることで、精神・発達障がいのある方が無理なく働ける環境が生まれています。
印象的だったのは、「障がいの有無に関係なく、相談が分散する仕組み」でした。障がい者同士の助け合いは大切ですが、それに頼りすぎると支援する側が疲弊してしまう。健常者スタッフが適切にサポートし、職場とプライベートの境界線を明確にする。こうしたバランス感覚が、持続可能な雇用を支えているのだと感じました。
さらに、転籍後も同じ場所・同じスタッフで働き続けられる仕組みや、障がい者雇用の枠を超えて正社員のマネジメントを担うまでに成長した事例は、「障がい者雇用=単純作業」という固定観念を覆すものです。
未経験からでも、適切な支援と環境があれば、ここまで成長できる——それを証明しているのがワークリアの取り組みでした。「やり方がわからないだけで、決して雇用したくないわけではない」という言葉が、企業側の本音なのかもしれません。
一方、障がい者側も、「障がいがあるから」という先入観で自分を制限する必要はありません。選択肢は確実に増えています。
大切なのは、お互いに歩み寄り、対話しながら進めていくこと。そして、「どう働いてもらい、どう活躍してもらうか」を一緒に考えていくこと。ワークリアの取り組みは、その可能性を示してくれています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
レバレジーズ株式会社/ワークリア詳細
レバレジーズ株式会社
ホームページ:https://leverages.jp/
住所
〒150-6190
東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 24F・25F
電話番号
0120-978-435(フリーダイヤル)
03-5774-1632(代表)
お問い合わせフォーム:
https://leverages.jp/contact/
ワークリア(障がい者就労支援サービス/レバレジーズ株式会社運営)
ホームページ:https://worklear.jp/
住所:
〒150-6190
東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 24F・25F
電話番号:
050-5358-4170
メール:
お問い合わせフォーム:https://worklear.jp/contact/
ワークリア求人ページURL:https://worklear.jp/solution/recruitment/
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- すべての家族に”写真を撮る喜び”を 医療的ケア児・発達障害児にも寄り添う写真館 - 2026年1月20日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【後編】 - 2026年1月12日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【前編】 - 2026年1月11日



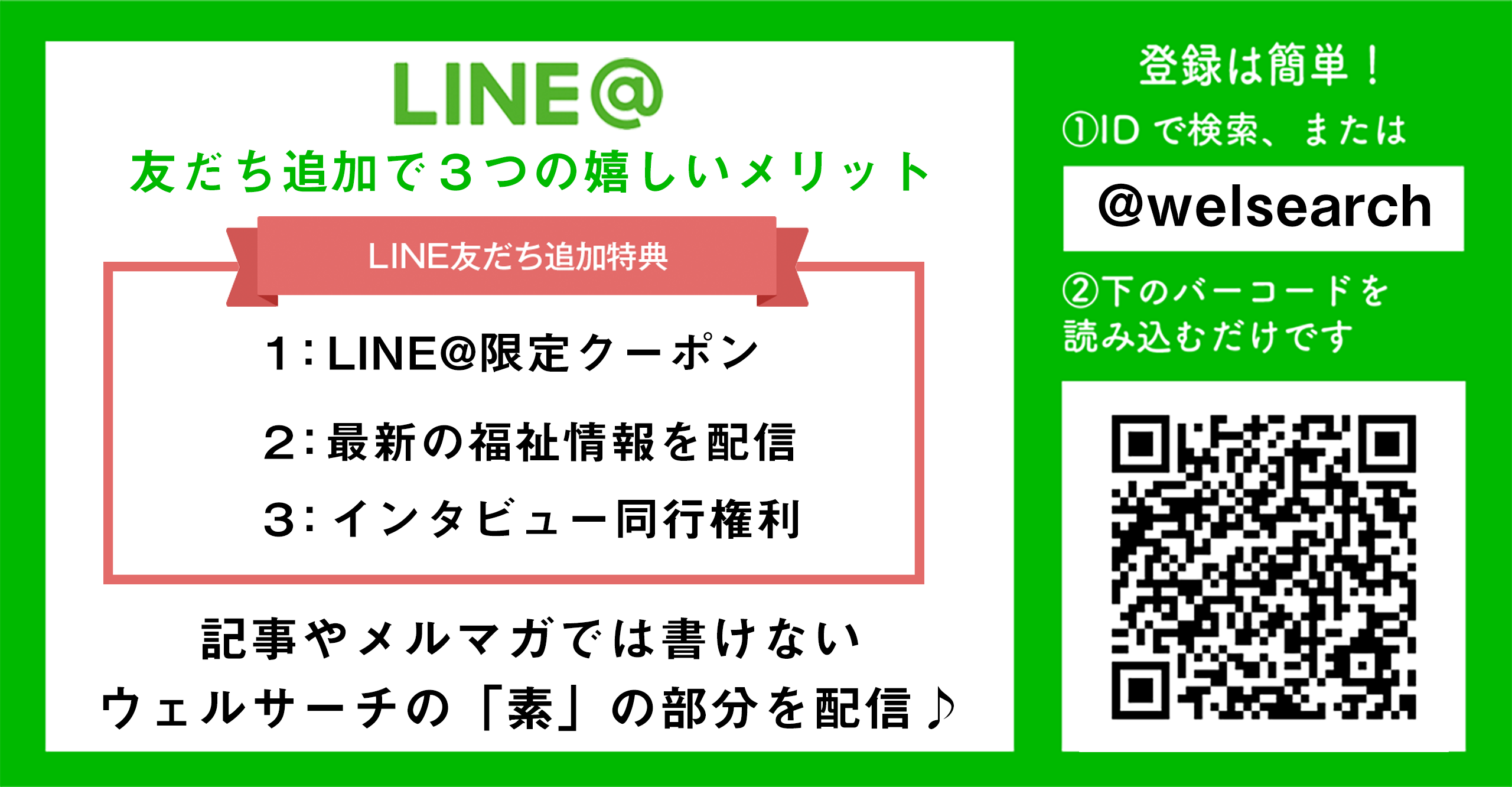
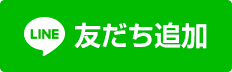
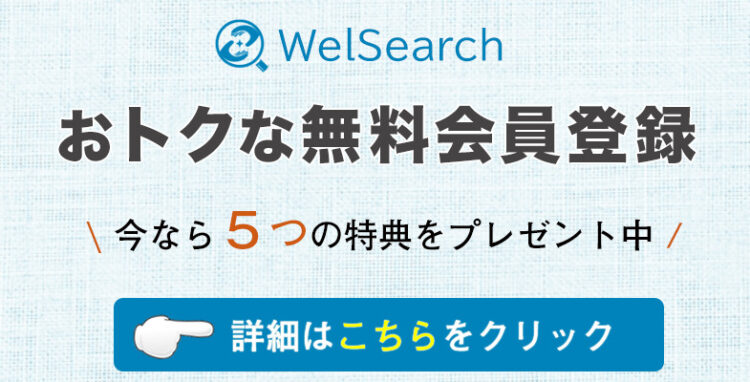

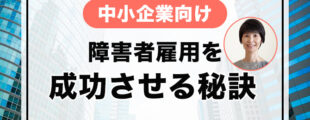
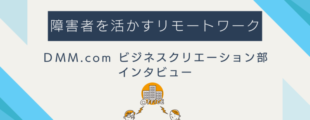
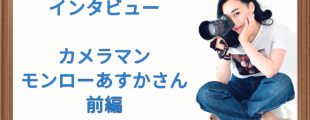
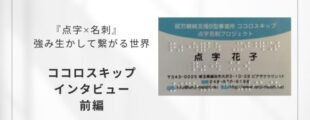

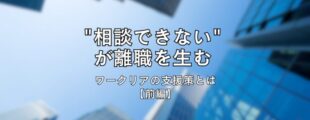
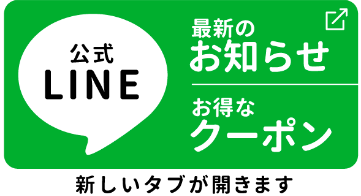


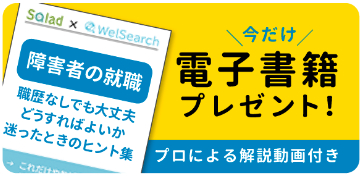
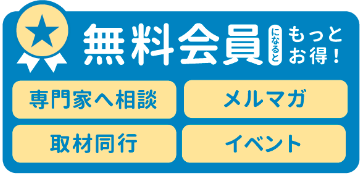

この記事へのコメントはありません。