高齢や障害があると、金銭や書類の管理に不安を感じることはありませんか?
成年後見制度ほどではないけれど、少し支援があれば……。
そんな方のための「日常生活自立支援事業」を、小山市社会福祉協議会の取り組みから紹介します。
お好きなところからお読みください
小山市の社会福祉協議会について

―― まずは小山市社会福祉協議会様の活動についてお願いします。
――山口様
社会福祉協議会は、地域住民、福祉関係事業者、行政、ボランティア団体、障害者等の当事者団体などの支援を受けながら活動している民間の組織です。
社会福祉協議会の大きな理念は、地域福祉を地域住民と一緒に推進していくことで、これが社会福祉協議会の主な目的となっています。
―― 基本的には行政と福祉をつなぐ橋渡しですね。具体的にはどのような活動をなされていますか?
社会福祉協議会の活動
――山口様
まず、地域住民への福祉情報の発信・広報業務があります。
広報誌などを使って小山市内の福祉情報を発信したり、社会福祉協議会の事業紹介を行っています。また、学生等との交流を通じて福祉教育活動も実施しています。地域のボランティア団体への後方支援や、新たな担い手を探すための講座など、参加機会を作る等、地域福祉の意識づくりが一つ目の活動です。
続いて、地域の仕組みづくりについてです。
社会福祉協議会には、市社会福祉協議会とは別に地域で活動する地区社会福祉協議会という地域団体があります。こうした団体の活動を推進・後方支援し、各地域での福祉活動が進むよう支援しています。
地域の福祉に関する交流の場づくりも行っており、例えば車椅子バスケットボールやボッチャ等の福祉スポーツ体験イベントを開催しています。
また、権利擁護や生活困窮等サービスに関する心配がある方に対し、身近な相談機関として相談支援体制を整えています。地域の地縁団体や福祉関係団体と連携し、共同募金活動や寄付の受付、福祉活動への助成なども行っています。
最後に、地域が安心して暮らせるまちづくりの一環として、災害支援に力を入れています。
災害時には職員を被災地に派遣してお手伝いするほか、日頃から災害対応の学習機会や関係者の顔の見える関係づくり等を行っています。これらが社会福祉協議会の大きな活動となります。
―― 色々な団体や個人の活動の支援というイメージですね。
――山口様
行政からの補助、委託を受けて、社会福祉事業を行っています。社会福祉協議会の大事な理念の1つに「住民主体」という考えがあり、活動する住民が中心にいて、それを支えるというのが社会福祉協議会の役割です。
あすてらすおやまが提供する日常生活支援事業とは

―― 社会福祉協議会の事業の一つである、あすてらすおやま様の行っている「日常生活自立支援事業」とはどのようなものなのでしょうか?
――山口様
日常生活自立支援事業の背景について説明します。
平成11年に制度改革があり、「措置から契約」利用者本位の福祉制度の実現が目標とされました。介護保険制度もこの頃考えられました。
この改革により、福祉サービスが変わりました。これまで行政が決めていたものが、利用者とサービス事業者との契約制になったのです。
認知症の高齢者や知的障害のある方等、判断能力の低下した方も自分でサービスを選択し契約する時代になったのです。
しかし、契約内容が理解できなかったり、自分で決めるために詳しい説明や一緒に考えてくれる人が必要という課題が生まれました。こうした方の自己決定を支援するために、地域福祉権利擁護事業(後の日常生活自立支援事業)が始まりました。
サービス利用には支払いなどの金銭管理も必要になるため、あすてらすおやまでは3つのサービスを提供しています。第一に、サービス選択の支援。第二に、金銭管理の支援。第三に、通帳や印鑑の預かりサービスです。
―― そこは社会福祉協議会様全体の理念と同じで、あすてらす様がなんでもやるのではなく、支援がメインですね。その中で、ある程度判断力があるが色々手続きなどに不安がある方がサービスを利用する形で。
日常生活支援事業が対象となるケース
――山口様
例えば、契約内容を読んでいただいて全く理解できない場合は、あすてらすおやまでの支援は難しいと判断します。
逆に、何でも自分でできてしまう十分に自立されている方は支援の対象外となります。
―― ある程度の金銭や、印鑑、書類などを預かるという上では、信頼関係が必要となりますが、その辺りどのような面を意識していらっしゃいますか?
――山口様
信頼関係の構築については、最も大切なことは本人が利用したいという気持ちをしっかりと聞き出すことです。判断力が低下してくると、周りで支援してくださる方が大勢いらっしゃいますが、そうした方々の気持ちが強く出すぎてしまうケースがあります。
「この人は自分では難しいから、あすてらすおやまが必要だ」と判断されがちですが、本人は実際にはもう少し自分でやりたいという気持ちを持っていることがあります。一度自分でやってみる。でもやっぱりうまく管理できなくて、支援が必要だと自分で感じることが必要だと思います。
そのため、一回だけの面接ではなく、2回、3回と分けて実施し、1週間から2週間の間隔を置いて、本人にじっくりと考えていただきます。説明した内容を振り返っていただき、その上で「お願いしたい」という気持ちを確認できた時点で、支援を開始するようにしています。
―― やはり最後はやっぱり当人の判断ですね。
――山口様 本人が望んでいなければ、このサービスは成り立ちませんし、信頼関係も築くことはできないと思います。
―― 信頼関係があるからこそですね。金銭関係も絡むからこそなおさら。
日常生活支援事業を契約した後の流れ
――山口様
あすてらすおやまと契約すると、まずキャッシュカードを金融機関に返却します。お金をおろす際には、利用者が払戻請求書を自宅で記入・押印。その後、あすてらす職員が通帳を預かり、金融機関で払い戻しを行ないます。
もしくは、利用者と一緒に金融機関へ行き、利用者に払戻請求書を銀行で記入・押印していただきそれを見守り・支援する代行支援。利用者の代わりに社会福祉協議会が、払戻請求書に記入・押印し、金融機関へ訪問しお金を払い戻す代理支援の2種類の支援がございます。
代行支援に関しては、自分で通帳印鑑を保管するか書類預かりサービスを利用し、あすてらすで管理することを選択できます。代理支援に関しては、預かりサービスを利用し、あすてらすが生活費を払い戻し本人へ届けます。また、収支の状況確認等通帳の管理も行っております。
自分で自由にお金をおろせないこともございますので、必ずこうしたリスクについて事前に説明し、ご本人に判断していただくようにしています。
――そこはリスクでもありますが、高齢や障害などで判断力が少し落ちてくると金銭管理能力に不安が出てくることもありますので、メリットとも言えますね。
――山口様
何にお金を使いたいか、いくらお金を使いたいかいつ頃使いたいかを確認し、本人と相談しお金を下ろして届けています。そのため、ちょっと油断して多額のお金を下ろし、使い切ってしまうということはなくなります。
――代行支援と代理支援、どちらの依頼が多いのでしょうか?
――山口様
支援の中心は代理支援になっています。意思決定の支援なども並行して行っていますが、最も相談が多いのがお金の管理がうまくできないケースです。
そのため、金銭管理とセットで通帳と印鑑を預かる書類預かりサービスを一緒に利用する方が多いです。
最近は事例も複雑化しており、借金があったり、近所の方にお金を借りたりといった返済トラブルが発生し、「借金を返済してもらえないか」という相談が増えています。
本来、お金のトラブルには積極的に関わらない方針ですが、このような相談が多いため、本人がどうしてもその人に返済したいという強い気持ちがある場合は、一緒にその方のお宅に行き、返済のための話し合いの場を設けることもあります。
高齢者と障害がある方の割合は?
――サービスはさまざまな方が利用されますが、高齢者の方と障害がある方、どのような割合になっていますか?
――山口様
利用者の県全体での割合を見ると、圧倒的に多いのは軽度認知症高齢者で、その次が精神障害者です。精神障害者は若い方から高齢者まで幅広い年代が含まれます。
県全体では約6割が高齢者、残り3割程度が精神障害者、1割が知的障害者となっていますが、小山市の場合は知的障害者の利用が多く、高齢者4割、精神障害者3割、知的障害者3割という割合になっています。
―― 利用される方の金銭管理指導なども行っていらっしゃるのですか?
――山口様
私たちは利用者と一緒に計画を立てます。預かりサービスを利用している方は出納帳をつけて収支を管理し、月にいくらまで支出可能かを提示・助言します。
その上で、それ以上を使って生活が苦しくなった場合は、通帳を見せながら現状を説明し、「今は出せない」ということを理解してもらい、我慢していただくようなやり取りを行っています。
それでも納得いただけない場合はあえて、最低生活ラインを残してお金を渡して苦労してもらうみたいなやりとりも行います。
社会福祉協議会としてデジタル化にどう対応する?

―― 最近ですと、デジタル化などの波がありますし、マイナンバーなどの扱いもありますが、その辺りはどのようになっていらっしゃいますか?
――山口様
栃木県社会福祉協議会からの指導で、マイナンバーカードは預かることができません。また、近年多いトラブルとして、PayPayや楽天ペイなどの電子決済サービスがあります。
これらは簡単に作成できるため、通帳を預かっていても、利用者がペイサービスで支払いを行い、気がつくと口座残高がなくなっているというケースが増えています。
―― デジタル化によるトラブルの一例ですね。
――山口様
この点については助言・指導しても改善が難しく、どうしても使ってしまうのが現状です。使わないでほしいと伝えても止めることができません。そこはコミュニケーションを取る以外に方法がなく、強制的にやめさせることはできません。
例えば、使いすぎて生活が困窮してしまった場合は、まずその状況を実感してもらい、失敗を一つの学習機会として捉えていただき、そこから再度相談を重ねていくという アプローチを取っています。やはり強制することはできないためです。
―― デジタル化の波の中で、対応することも増えたかと思いますが、対策などはどうされていますか?
――山口様
まだそうした具体的な議論をしているわけではないので、なかなかイメージがつかないのが正直なところです。ただ、デジタル化の波で常に進化を続けており、対応を考える必要があると思います。
県社協あすてらすと市社協あすてらす同士では、クラウドサービスでの情報共有などが進んできています。しかし、利用者への対応のデジタル化ついてはまだ手探りの状態です。今後は個人の方への対応も必要になってくるでしょうし、デジタル化にどう対応していくかが大きな課題となっています。
――デジタルに対応する人材を想定していく必要がありますね。
デジタル化に対応できる人材が必要
――山口様
AIに強い人材とか、そういうのは今後必要かなと思います。
例えば、支援後の記録や利用者との面接記録、簡単なエクセル管理などAIの指示を与え少しでも業務を効率化できる人材がいれば活躍していただきたいと想像しています。
――ニーズも多様化していますし、今後利用者もさらに増えるかと思いますが、対応はどうしていく感じですか?
――山口様
ニーズが減ることはなく、むしろ増えていく傾向にあります。
現在、物価高騰やインフレが進んでいます。資本主義社会では格差が拡大しており、判断力が低下した方など社会的弱者の資産は目減りしている状況です。
そのため、あすてらすのニーズは今後も増加していくと考えられます。
最近の利用者で多いケースとして、社会福祉協議会では生活困窮者の食料支援も行っていますが、「食料がない」という相談があります。なぜ食料がないのかを調べると、判断力の低下が影響していることが分かります。
こうした場合、あすてらすも一緒に協力して問題に取り組まなければ、食料を渡すだけでは根本的な解決は困難です。家計を適切に管理するという支援の選択肢として、あすてらすおやまが求められているのだと感じています。
――利用者とニーズ、増える一方ですが、人員的にはどうなのでしょうか?
日常生活支援事業の料金体系
――山口様
正直、人員的にはかなり厳しい状況です。ギリギリの運営で、実際のところ赤字運営となっています。
利用者からは一応料金をいただいていますが、現在は1回の支援で1,000円、預かりサービスで月500円、生活保護の方からは料金をいただかない形で運営しています。
しかし、到底運営できません。頼みの綱は事業委託費ですが、あすてらすの事業費は、市からの委託金ではなく県社会福祉協議会からの委託金となっています。ただし、委託費は大体正職員1人分の人件費程度しかなく、あすてらすおやまでは職員3人で運営しているため、非常に厳しい状況です。
――そういう意味では人員補充も厳しいですね。
――山口様
将来的にAIに任せるなど、効率化の流れに遅れをとると、いつまでも人手不足と赤字が続く厳しい状況が続いてしまうよう感じています。
――人数少ない中でも、工夫されながら運営されてる感じですね、現状は。
――山口様
もちろん利用者とのコミュニケーションで難しい局面などもありますので、あすてらすおやまではチームアプローチとして辛いケースを一人で抱え込ませないよう配慮しています。
お金の面については、予算を決める側ではないので私にはどうすることもできませんが、職員のケアについては工夫しています。必ずチームで動くようにして、辛いケースは必ず共有するようにしています。
そうした話をしっかりと聞いて助言し、一人で抱え込んで追い詰められることがないよう話し合い、みんなで考えて解決できるような組織、チーム内で連携が取れる体制を作っています。
小山市の社会福祉協議会による広報の工夫
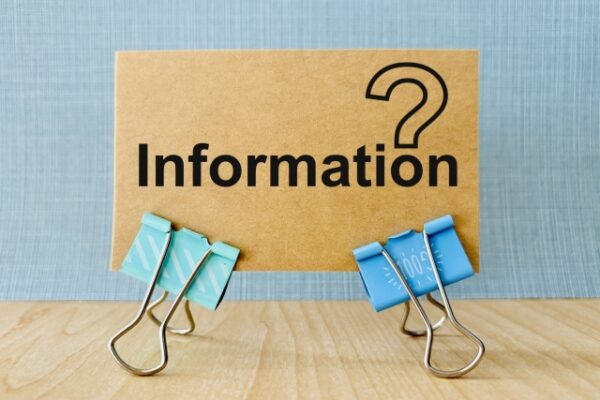
―― あすてらすおやま様のサービス含め、社会福祉協議会様ではさまざまな取組みをなされていると思います。それらを利用する方達にどのような形の広報活動をされていますか?
――山口様 高齢者の方にとってはデジタル関係が難しいということもあり、やはり紙媒体での広報が中心になります。
デジタルを使えない方が多いことを考えると、従来の方法にも一定の効果があると思っています。ただし、紙での広報にも限界があることは確かです。
―― 伝える時に意識されてることなどありますか?
――山口様
小山市社会福祉協議会としては、いわゆる「福祉色」の強いイメージのイベントではなく、スポーツや明るい教育活動で子どもたちにアピールしたり、そうしたイベントに参加してもらうという方法を取っています。
例えば小山のご当地キャラに来てもらったりしながらPRし、私たちの取り組みを知ってもらいます。メインは楽しいことで、そこから福祉についても学んでもらうというアプローチが良いと思っています。福祉を前面に出したイベントでは、なかなか人が集まらないのが現実です。
―― 堅苦しいイベントではなく、気楽に参加できることは重要ですね。
地域福祉の未来は?利用を検討する方へ

―― 今後の活動の展望などをお聞かせください。
――大加戸様
あすてらすおやまだけでなく、小山市の地域福祉全体で考える必要があります。社会福祉協議会には多くの事業があるため、それらとの横の連携が重要です。
この事業に限らず、職員同士のつながりや連携も重視しながら進めていきたいと考えています。
―― 最後、この記事を読んでくださる読者に向けてのメッセージをお願いいたします。
――山口様
あすてらすおやまは、本人の希望があれば気軽に相談できるサービスです。
判断力の程度について私たちが面接した際に、支援が必要なレベルだと判断し、一定のガイドラインをクリアすれば、比較的気軽に利用できるサービスといえます。
ただし、その反面、先ほどもお話ししたように自由が制限される利用者が感じることも多いです。支援者の方が熱心すぎる場合、本人の気持ちが軽視されてしまうこともあります。
そのため、最も大切なのは本人の気持ちを引き出すことです。周りの方は、自分が利用したいという気持ちを表現できるよう、いろいろとお話を聞いてあげてください。
もちろん、ご本人から直接お電話いただければ、それが一番良いことだと思います。本人の希望に寄り添えるよう私たちも努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
―― ありがとうございました。
地域福祉の課題と展望
小山市社会福祉協議会の活動、特に日常生活自立支援事業「あすてらすおやま」の取り組みについて紹介させていただきました。
高齢化や障害による生活上の困りごとに対し、成年後見制度よりも利用しやすい支援があることを、より多くの方に知っていただく必要があります。
また、物価高騰による生活困窮や、デジタル化への対応、福祉現場の人員不足といった現代的な課題も浮き彫りになりました。
一方で、住民主体という理念のもと、本人の意思を最大限尊重しながら支援を行う姿勢や、楽しいイベントを通じて福祉を身近に感じてもらう工夫など、地域福祉の新たな可能性も見えてきます。
困ったときに一人で抱え込まず、気軽に相談できる場があることを、多くの方に知っていただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
小山市社会福祉協議会「あすてらすおやま」案内
所在地:〒323-0023 栃木県小山市中央町2丁目2-21 小山市総合福祉センター1階
電話番号:0285-22-5353(事業直通)/0285-22-9501(代表)
受付時間:平日8:30~17:15(土日・祝日・年末年始は休業)
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- 「人を咲かせる花屋」ローランズ 障害者雇用の新しいモデルを創る 後編 - 2026年2月16日
- 「人を咲かせる花屋」ローランズ 障害者雇用の新しいモデルを創る 前編 - 2026年2月16日
- コスプレで届ける笑顔と元気──日本コスプレ委員会の地域貢献活動 - 2026年2月14日

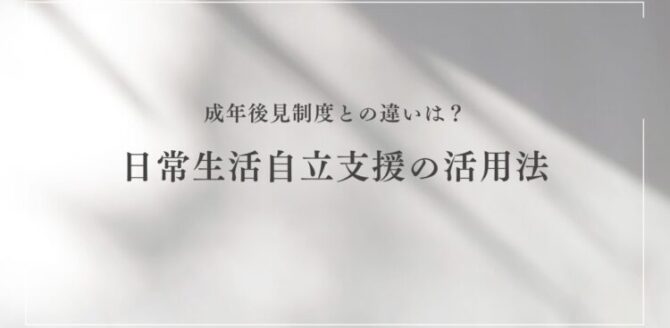

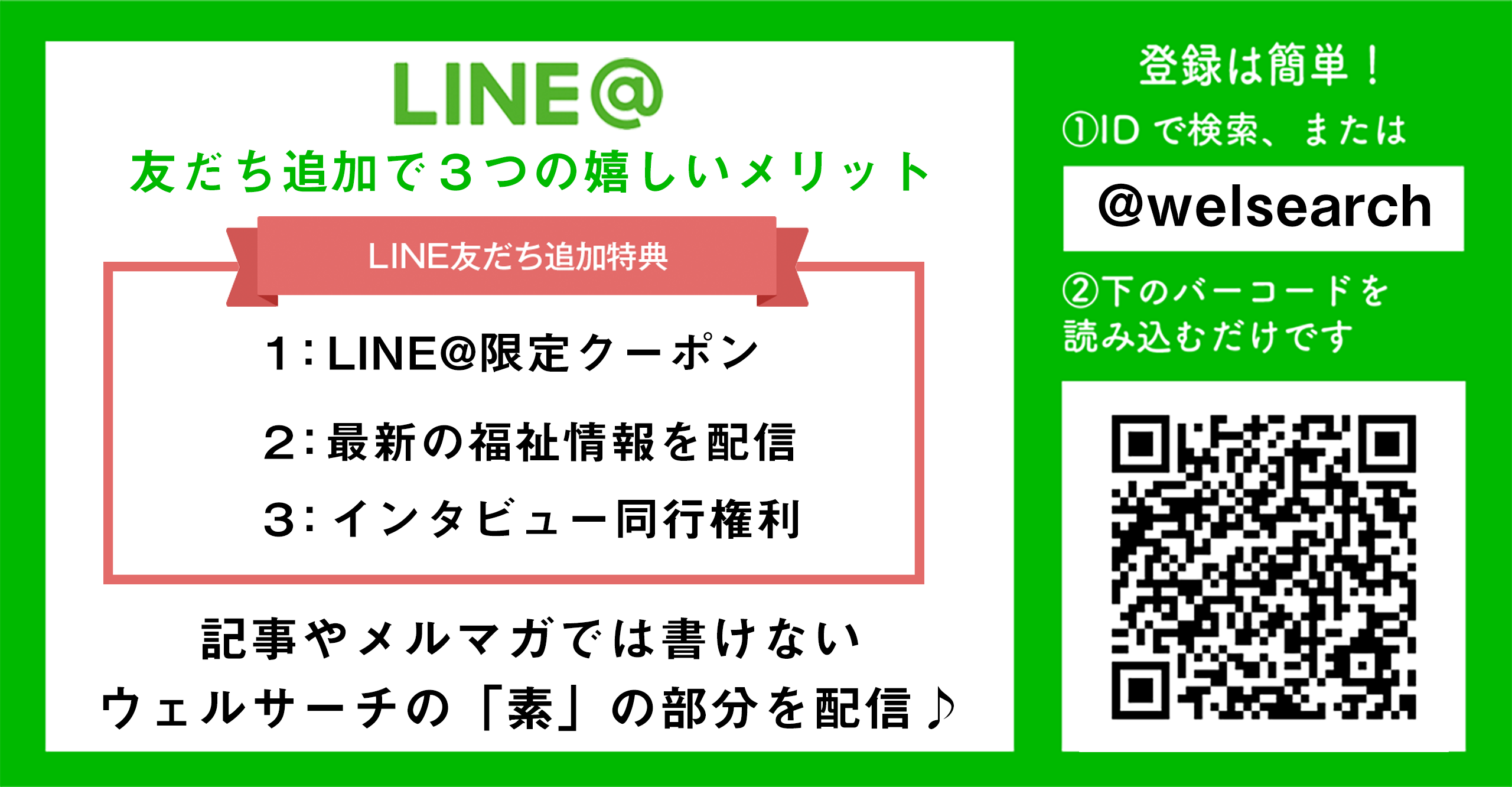
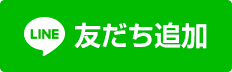
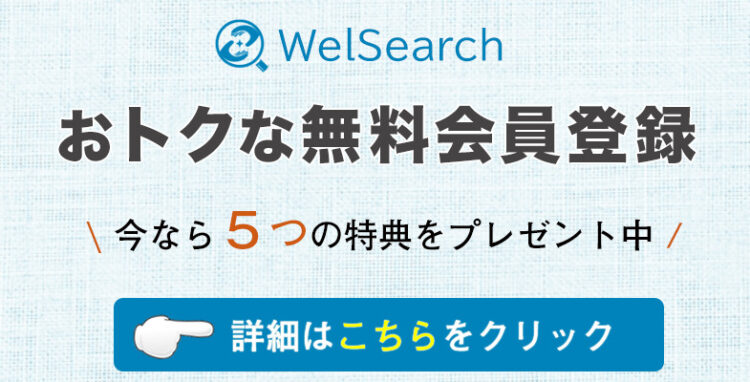

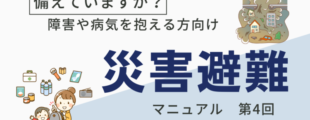
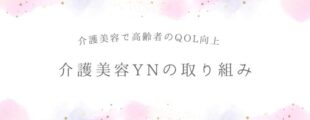
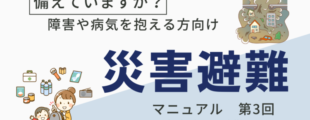

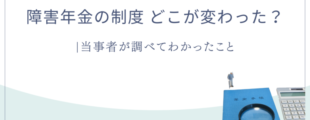
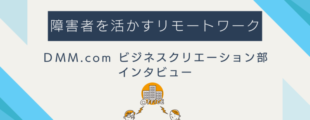
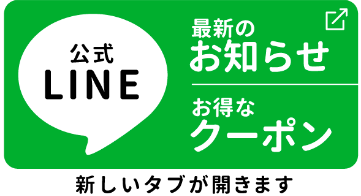


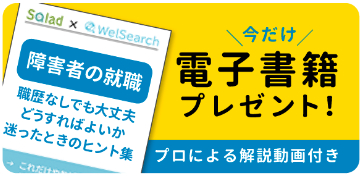
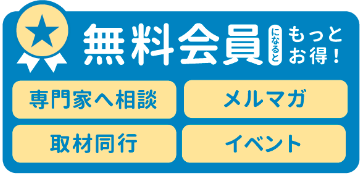

この記事へのコメントはありません。