開き戸を自動ドアにするシステムクリエーションです。
要介護者がいる場合、自宅のいたる部分で負担を感じさせてしまいます。
しかし、家をバリアフリーにすると考えても、費用の面が気になってしまうでしょう。
そこで使えるのが「補助金」です。
そこで今回は、どのような条件で補助金制度が支給されるのか、どんな部分に使えるのかや申請の流れを解説しますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
お好きなところからお読みください
介護リフォームは介護保険による「居宅介護住宅改修費」が適用
介護のためのリフォームには、お金がかかります。
手すりをつけたり玄関をスロープにしようと考えても、やはり気になるのは費用面ではないでしょうか。
しかし、このような介護のためのリフォームには、「居宅介護住宅改修費」が適用されるのです。
自宅を改修(リフォーム)することで、介護者にかかる負担を軽減できます。
費用は、居宅介護住宅改修費として20万円が上限です。

居宅介護住宅改修費の支給条件
居宅介護住宅改修費の支給条件は、3つあります。
1つ目は、「要介護認定されている介護保険の被保険者であること」です。
要介護認定で「要支援1〜2」もしくは「要介護1〜5」のいずれかに認定されていなければいけません。
2つ目は、「被保険者の住宅と一致すること」です。
被保険者が実際にその住宅を利用しているかどうか、という部分になります。
「介護保険被保険者証」に記載されている住所でなければ、補助金は受け取れません。
3つ目は、「被保険者が住宅で暮らしていること」です。
被保険者が、福祉施設や病院に入院している場合は、自宅を利用しているとは言えません。
そのため、補助金の対象外となってしまいます。
- 要介護認定されている介護保険の被保険者であること
- 被保険者の住宅と一致すること
- 被保険者が住宅で暮らしていること
居宅介護住宅改修費の支給額
居宅介護住宅改修費の支給額は、最大20万円です。
そのうち、所得に応じて7割~9割の補助を受けることができます。
自己負担が1割となった場合、最大で18万円の支給。
ただし、介護保険を利用した補助金は「償還払い」となっています。
補助金の対象となる介護リフォーム

補助金の対象となる改修は、6項目と決められています。
それぞれは、あくまで要介護者が快適に暮らせるようになることが目的です。
6項目は、以下の通り。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 床材の取り替え
- 扉の取り替え
- 便器の取り替え
- 5つに付随する改修工事
具体的に、どのような改修ができるのか、以下で解説していきます。
手すりの取り付け
転倒を防止したり、移動を手助けするための手すり取り付け工事です。
手すりをつける部分は、玄関や廊下、階段やトイレなど、要介護者が必要となる部分となります。
細かい形状の指定はないため、要介護者の使いやすいものを取り付けることが可能。
高さや形状など、要介護者と相談して取り付けられます。
段差の解消
転倒防止や移動の手助けとなるための工事です。
とくに車椅子利用者の場合、段差があると移動が難しくなります。
このような段差をなくして、平滑化したりスロープを設置したりすることが可能。
比較的大規模な改修になりますが、補助金が出ることで、自己負担少なく改修できます。
床材の取り替え
転倒防止のための工事です。
住宅に使用されている床は、滑りやすいものがあるため、要介護者の転倒の原因となる恐れがあります。
このような床を、滑りにくい床に交換したり、車椅子利用者が使いにくい畳の床をフローリングにすることが可能。
床材をまるごと交換することもできますし、滑りにくい加工を施すこともできます。
扉の取り替え
要介護者にとって、ドアはさまざまな負担を感じる部分です。
握力が弱くなりドアノブを回しにくくなったり、車椅子利用者の場合は、開き戸が邪魔になったり、自身では開閉できないケースがあります。
このようなドアを、使いやすいものに変えることが可能です。
開き戸から引き戸にしたり、重い引き戸から軽い引き戸にしたり、自動ドアにすることもできます。
便器の取り替え
要介護者が利用しやすい便器に取り替える工事です。
高齢者や要介護者にとって、和式の便器はとても使いにくいため、洋式便器に取り替えることができます。
また、洋式便器に取り替える際は、洗浄機能や暖房機能がついている便器でも可能。
さらに、元々様式便器の場合でも、高さや向きを変える工事ができます。
5つに付随する改修工事
「5つに付随する改修工事」は、上記の改修に付随して必要となる工事です。
たとえば、手すりを付ける際の下地補強、便器取り替えの際の給排水設備工事などが当てはまります。
不安な場合は、5つに付随する工事かどうか、一度確認しておくと良いでしょう。
賃貸の場合も改修は可能
現在お住まいの住宅が賃貸の場合でも、改修リフォームは可能です。
ただし、家主(オーナー)の承諾が必要になります。
また、「転居や退去の際に元の状態に戻してほしい」という条件の場合、元に戻すための費用は、全額自己負担です。
居宅介護住宅改修費を申請する流れ

居宅介護住宅改修費の利用の流れを解説します。
正式な流れで進めなければ、補助金を受け取れない可能性があるので、注意しましょう。
以下の流れで手続きを行ってください。
- ケアマネージャーに相談(ケアマネージャーが作成した理由書が必要になるため)
ケアマネージャーがいない場合は、役所の高齢支援課へ相談 - 住宅の状態や要介護者の状態を把握した上で、改修の提案・相談
- 住宅改修事業者により見積もり
- 住宅改修費の申請
- 許可が下り次第工事開始
- 工事終了後、住宅改修事業者へ支払い
- 改修費の領収書や費用の内訳、改修前と後の写真等を添えて提出
- 住宅改修費の払い戻し
居宅介護住宅改修費を申請する上での注意点
補助金を申請する上で、必ず注意しなければいけないのが、「工事を始める前」に申請しなければいけないという点です。
工事着工前に申請することが、絶対条件となっています。
工事開始時や終了時に申請しても、原則受理されません。
また、ケアマネージャー等による「理由書」が必要になるため、自己判断で改修を依頼しないようにしましょう。
補助金申請で自宅での暮らしが便利になる

このように補助金制度を利用すれば、現在お住まいの住宅での暮らしは、とても便利になります。
現在要介護者が負担を感じているのであれば、補助金を利用した介護リフォームを検討してみましょう。
また、介護保険による補助金のほかに、自治体による助成金の利用も可能です。
支給額や支給条件はお住まいの地域によって異なりますが、100万円近い助成金を受け取れることもあります。
当社で扱っている、開きドアを自動ドア化する装置「スイングドアオペレーター」の取り付けも、補助金や助成金の対象です。
取り付け額は40万円程度ですが、自己負担額0になった事例もあります。
詳細は、こちらの記事で紹介しております。
スイングドアオペレーターや補助金の申請に関して気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。
もちろんご相談だけでも構いません。
また、スイングドアオペレーターの詳細は、こちらをご参照ください。
最新記事 by 合同会社システムクリエーション (全て見る)
- 一般的な開き戸(ドア)はどの位車椅子利用者への負担をかける?|実際の声も紹介! - 2021年8月22日
- 補助金制度で介護リフォーム!自己負担を少なくする申請の流れや条件とは? - 2021年7月19日
- 自宅の玄関を自動ドアにすると家族みんなが快適になる! - 2021年5月2日





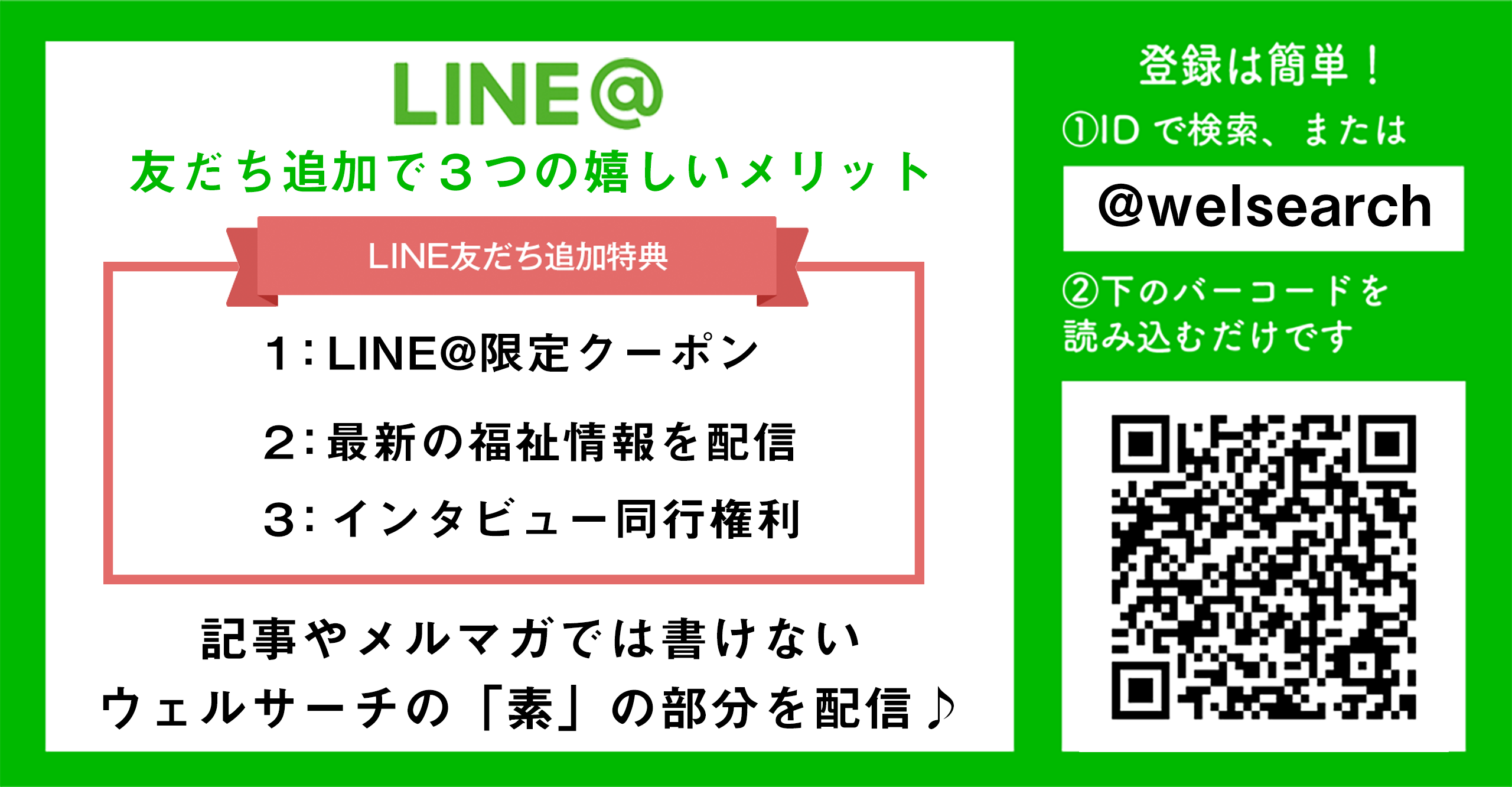
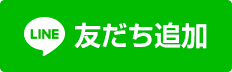
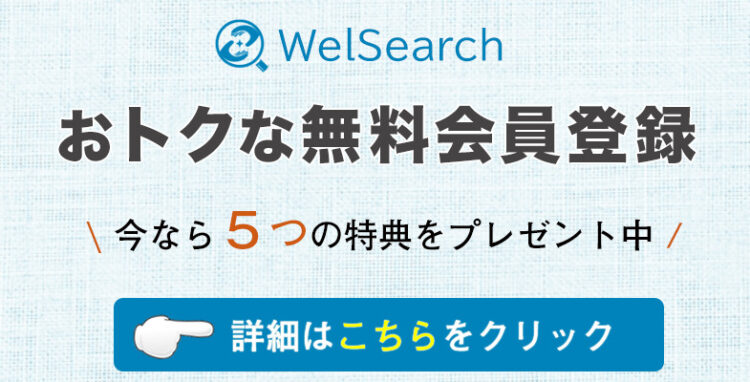

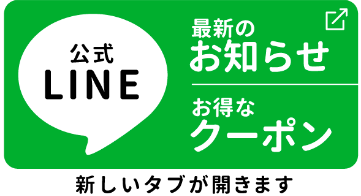


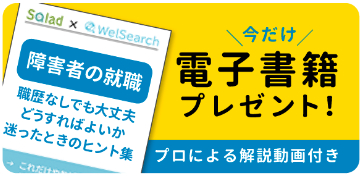
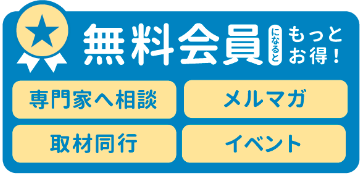

この記事へのコメントはありません。