2025年9月、二子玉川で開催された「Age-Well Festival 2025」。
このイベントは「高齢社会をポジティブに体感・発信する」ことをテーマに、企業や団体がそれぞれの取り組みを紹介し、来場者と交流する場として企画されていました。
参加前は、正直なところ「福祉イベント=生活に困っている高齢者をサポートするための機器やサービス展示」というイメージを持っていました。事前に見た公式ページからも、高齢者向けの催しが中心で、来場者の多くも高齢者層なのだろうと考えていました。
一方で、発達障害当事者として福祉に関わってきた私には、別の期待もありました。
- 実際の高齢化社会に対して、企業や団体がどんな取り組みをしているのか
- 高齢福祉や障害福祉に共通する「姿勢」や「考え方」に触れられるのではないか
そんな思いから、「少しでも新しい視点やヒントを持ち帰れれば」という気持ちで会場に足を運びました。
【注記】この記事は筆者個人の体験に基づく感想です。紹介するサービスや取り組みについては、各自でご確認・ご判断いただければと思います。
お好きなところからお読みください
会場の第一印象 ――「気軽に参加できる福祉イベント」

会場は駅を出てすぐの場所にあり、アクセスの良さからか、多くの人でにぎわっていました。
最初に目に飛び込んできたのは、老若男女を問わず大勢の人たちの笑顔。
一目見ただけで「みんな楽しんでいるんだ」と伝わってくる空気がありました。
参加者は高齢者層が中心でしたが、思っていた以上に多様な年齢層が訪れていました。
親子連れや若い世代の姿もあり、「高齢者だけのイベント」という印象はすぐに覆されました。
雰囲気を一言で表すなら、まさに「気軽に参加できる福祉イベント」。
堅苦しさや重々しさはなく、文化祭や地域のお祭りに近い明るさが漂っていました。
「福祉=困っている人のためのもの」「難しい制度や機器の説明ばかり」という固定観念を持っていた自分にとって、この雰囲気は新鮮でした。
むしろ、こうした気軽に立ち寄れる場だからこそ、福祉に興味を持つ人が増えるのではないかと感じました。
さらに安心感を覚えたのは、会場のスタッフやブース出展者、さらには来場者同士までもが、自然に声を掛け合っていたことです。
私自身もスタッフや企業の方から気軽に話しかけてもらい、「その場にいる人全員で作り上げているイベント」という温かさを実感しました。
印象に残ったブース・取り組み紹介
会場を歩きながら、いくつものブースを回ってみました。どのブースも工夫が凝らされていて、それぞれに「福祉の新しい形」を感じさせてくれる取り組みばかり。
ここでは、その中でも特に印象に残ったブースをいくつかご紹介したいと思います。
AIで「想いを残す」 ― 株式会社レガシィ「AIユイゴン Well-B」

会場でまず目を引いたのが、株式会社レガシィのブースでした。ここで紹介されていたのは、AIを活用して遺言書の草案を作成できる「AIユイゴン Well-B」というアプリ。
遺言というと、紙に書いたり専門家と一緒に作成したりというイメージが強いですが、このサービスではスマートフォンやパソコンを使って、対話形式で自分の想いを話すだけで遺言の草案が自動で作成されるというものでした。
さらに音声入力にも対応しているため、キーボードが苦手な方でも利用しやすい工夫がされています。
私は個人的にAI分野に関心があるので、この取り組みには特に注目しました。
- 「遺言=難しいもの」から「もっと身近で日常的なもの」へ近づける可能性
- 高齢や障害があっても、声で想いを残せる手軽さ
こうした視点に大きな可能性を感じました。
もちろん法的効力を持たせるには専門家による確認が必要ですが、「AIが支援してくれるからこそ第一歩を踏み出しやすい」というのは、とても現代的な価値だと思います。
このブースを通して改めて実感したのは、技術の発展とともに「残せるもの」も進化していくということ。終活や福祉の分野にとっても、AIは心強い味方になるのではないかと感じました。
美しさは「生きる力」になる ― 介護美容YN

次に紹介したいのは、介護美容YNのブースです。
ここでは高齢者施設などで提供されている美容施術(ネイル・メイク・エステなど)が体験できました。イベント当日はネイルの体験が行われており、多くの方が楽しそうに参加されていたのが印象的でした。
「福祉」と聞くと、どうしても「最低限の生活を維持するための支援」というイメージを持ちがちです。しかし、美容は単なるオシャレではなく、人が生きていくうえで心と体を晴れやかにする力を持っていると実感しました。
爪や肌を整えることは、見た目を美しくするだけでなく、自己肯定感を高め、精神的な前向きさを引き出すことにつながります。
実際、介護美容YNが行っている施術は、ネイルやメイクを通じて高齢者の笑顔や意欲を引き出し、心身の活性化やQOL(生活の質)向上に寄与しています。触れ合いや色彩の刺激は、安心感や「幸せホルモン」の分泌を促すとも言われています。
私自身もこのブースで、「ただ日々を過ごす」のではなく、「日々を楽しく、明るく生きる」ための支援が福祉にはあるのだと強く感じました。美容はまさにその一助となりうる存在です。
「福祉=困りごとを解決するもの」から「福祉=人生を豊かにするもの」へ。介護美容の取り組みは、その転換を象徴しているように思えました。
快適な眠りが福祉を支える ― パラマウントベッド

続いて紹介したいのは、医療・福祉分野で広く知られているパラマウントベッド株式会社のブースです。
会場では実際のベッド製品が展示されており、私自身も体験させてもらいました。正直なところ、これまでは「介護用ベッド」という印象が強くありました。
しかし、実際に横になってみると、介護現場だけでなく日常生活でも十分に使いたいと思えるほど快適。まるで身体をやさしく受け止めてくれるような感覚がありました。
介護を必要とする高齢者や障害のある方にとって、このベッドがもたらす恩恵は大きいはずです。動きやすさや安全性はもちろんのこと、「眠る」という人間にとって最も基本的な営みを支えてくれるからです。
さらに感じたのは、睡眠の質が心身の健康の根幹にあるということ。良い眠りが確保できるだけで、日常の過ごし方や気持ちの持ち方まで変わってきます。パラマウントベッドのような製品は、まさに「福祉=生活の質を底上げするもの」であると実感しました。
技術の進歩とともに、眠りの環境はますます整えられていくでしょう。その最前線を担う取り組みの一端に触れられたことは、大きな学びになりました。
花と人が共に咲く ― 株式会社ローランズ

最後にご紹介したいのは、株式会社ローランズのブースです。
会場では色とりどりの花が並び、華やかで明るい雰囲気が広がっていました。花を眺めているだけで心が晴れやかになり、自然と笑顔がこぼれるのを感じました。
ローランズは、花屋事業を通じて人々の暮らしに彩りを届けると同時に、障害や難病など多様な困難を抱える人が自分らしく働ける環境づくりに力を入れている企業です。
展示されていた花々を見ていると、「障害があるから」「ないから」という区別ではなく、一つひとつの仕事に誠実に向き合い、心を込めて取り組んでいる姿が伝わってきました。
改めて思ったのは、どんな仕事であっても「やりがい」や「思い」が込められているかどうかで、人は輝けるということです。花という目に見える形でその成果が表れているからこそ、働く人の誇りや喜びがまっすぐに伝わってきました。
障害や年齢に関わらず、誰もが自分の力を発揮し、輝ける場所がある。そのことを、ローランズの花々は静かに、しかし確かに教えてくれているように思いました。
当事者として感じた気づき

会場全体を体験して、最初に抱いていた「高齢者のためのイベント」という印象は大きく変わりました。確かに企業のPRの場ではありましたが、それ以上にイベントステージでの催し物やスタンプラリーなど、多世代で盛り上がれる仕掛けがありました。
参加してみて、「高齢者だけのものではなく、みんなで楽しむイベント」だと強く感じました。発達障害当事者として参加してみても、安心感や共感を覚える瞬間がありました。
高齢者に限らず、身体に不自由があってもサポートが充実している今の社会。その姿を見て、「自分もまた、その恩恵の中で生きている」と幸せを実感しました。
また、「福祉=お世話される」というイメージも変わりました。支援とは単に助けてもらうことではなく、活力をもらい、その力でどう生きるかを選ぶもの。
楽しんでこそ、そこに生きがいが生まれるのだと実感しました。そして最後に、福祉は決して堅苦しいものではなく、日々を豊かに、充実させるためのものだという気づきがありました。これは当事者としても、支援者としても共通する大切な視点だと思います。
まとめ
Age-Well Festival 2025は、私にとって「福祉=困りごとの支援」というイメージを大きく変える体験となりました。
会場には高齢者だけでなく、多様な世代の人々が集まり、笑顔と活気にあふれていました。展示ブースや体験を通じて感じたのは、福祉は単に「支援される側」と「支援する側」を分けるものではなく、誰もが共に参加し、楽しみ、支え合うものだということです。
印象的だったのは、
- 技術の進歩が日常をより快適にする可能性を示してくれたこと
- 美容や花といった「楽しみ」が生きがいにつながること
- 支援が「お世話」ではなく「活力を与え、共に生きる力になる」こと
これらの学びは、発達障害当事者である私自身にとっても、大きな気づきでした。福祉は特定の人のためだけではなく、「自分ごと」として日常に結びつくものだと実感できたからです。
【注記】この記事は、筆者個人の体験に基づく感想です。紹介したサービスや取り組みについては、各自でご確認・ご判断ください。
最後に、この記事を読んでくださった方に一つお願いがあります。もし次回、こうした福祉イベントがあれば、ぜひ一度足を運んでみてください。福祉の堅苦しいイメージが変わり、生活を前向きにする新しいヒントや出会いがきっとあるはずです。
「福祉は暮らしを豊かにする力になる」
その可能性を、私自身もこれから探し続けたいと思います。
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- 「人を咲かせる花屋」ローランズ 障害者雇用の新しいモデルを創る 後編 - 2026年2月16日
- 「人を咲かせる花屋」ローランズ 障害者雇用の新しいモデルを創る 前編 - 2026年2月16日
- コスプレで届ける笑顔と元気──日本コスプレ委員会の地域貢献活動 - 2026年2月14日

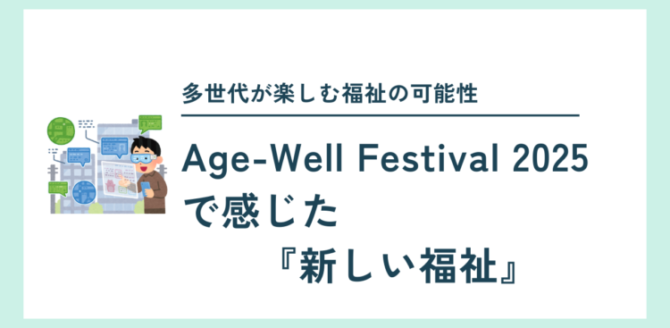

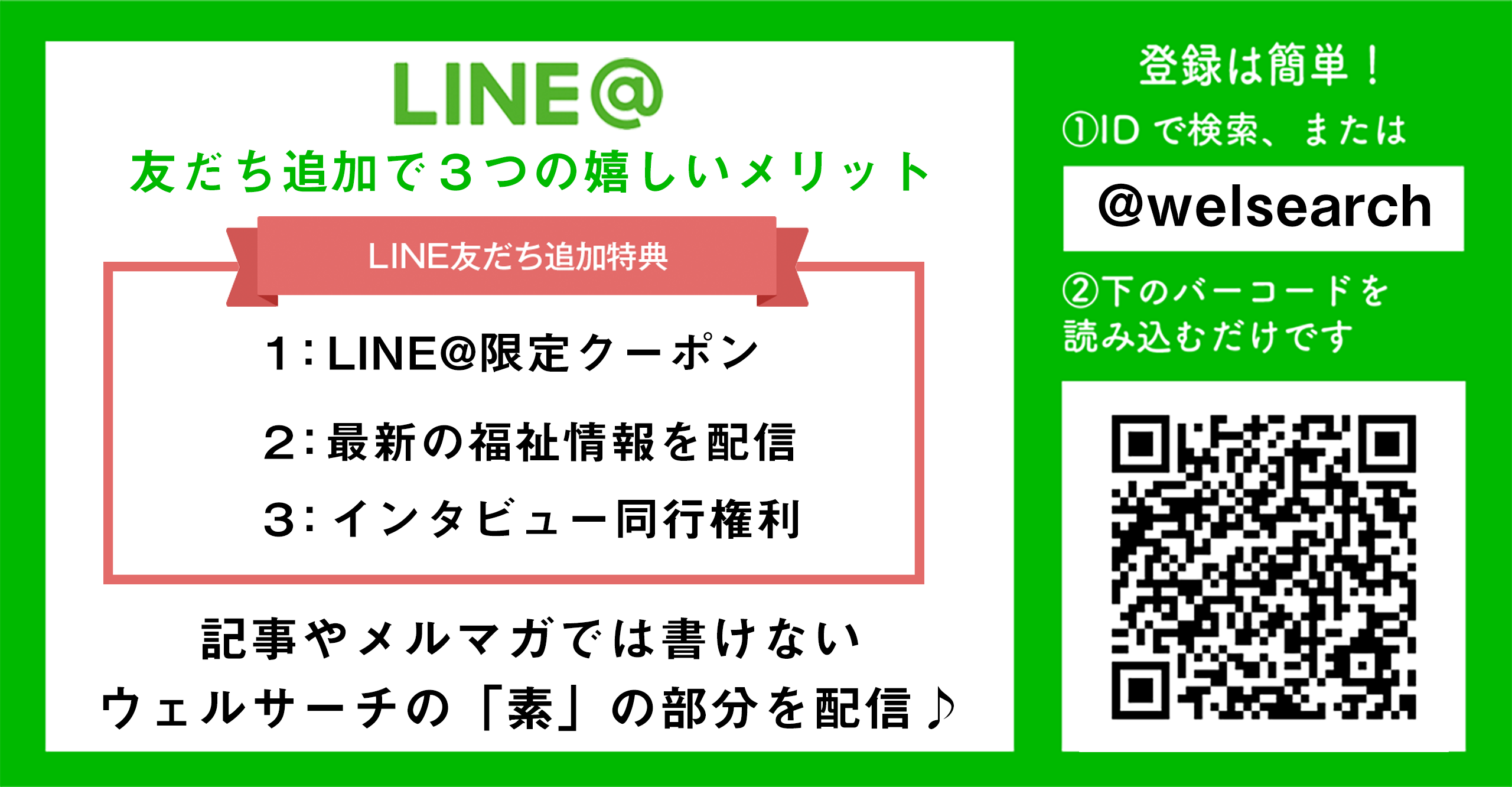
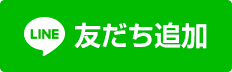
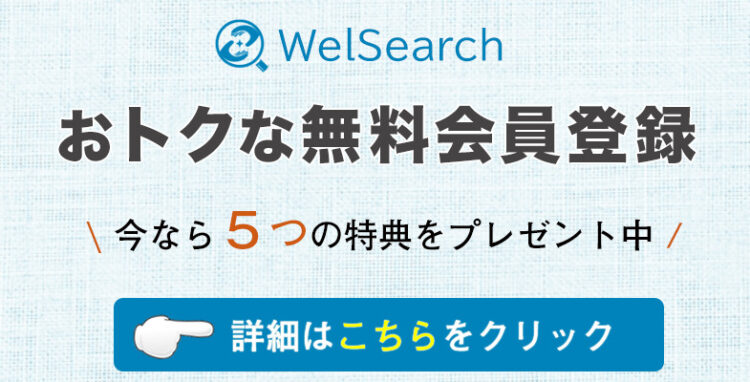

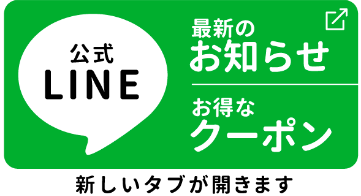


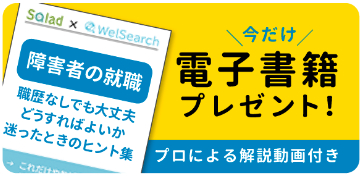
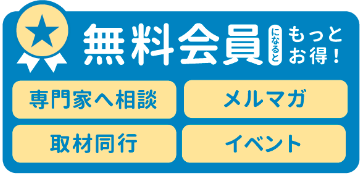

この記事へのコメントはありません。