2025年9月16日、東京ミッドタウン八重洲カンファレンスで開かれた「Age-Well Conference & Festival 2025」に足を運びました。
これまで私は主に障害福祉について考え、発信してきましたが、これからの福祉を語るうえで高齢化社会への取り組みは避けて通れないテーマだと感じています。
参加前は「病院や施設関係者が多いのでは」と想像していました。けれど、前週に訪れたAge-Well Festivalで「高齢福祉=施設」というイメージがすでに変わりつつあると実感したばかり。
今回も多様な人と出会い、さまざまな視点に触れられるのではないか。そんな期待を胸に会場へ向かいました。
実際、会場に一歩足を踏み入れると、参加者の服装や年代は実にさまざま。
起業家や行政関係者、学生からシニア世代まで、幅広い人たちが一堂に会しており、「老いを再定義する」というテーマにふさわしい多様性が一目で伝わってきました。
福祉の発信者として、まだ知識が足りない高齢化社会への理解を深めたい。
その思いで参加したこのイベントは、「高齢化=衰え」ではない世界を体感する貴重な機会となりました。
【注記】この記事は筆者個人の参加体験に基づく感想です。講演内容については、公式情報もご確認ください。
お好きなところからお読みください
基調講演レポート「長寿社会に生きる」― 秋山弘子氏
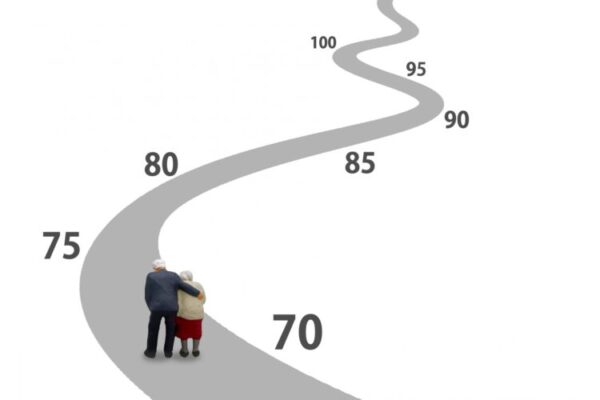
開会の挨拶に続いて登壇したのは、東京大学 高齢社会総合研究機構 名誉教授の秋山弘子氏。
演題は「長寿社会に生きる」。
老年学の第一人者として長年現場に立ってきた秋山氏は、人生100年時代における”老い”の捉え方を根底から問い直しました。
人生設計の大転換
印象的だったのは、織田信長の「人生わずか五十年」に始まり、「いまは100年を生きる時代」という言葉。
かつてはおおよそ決められた人生設計を誰もがたどっていたのに、いまは自分で人生を描く時代になったと語ります。
秋山氏が紹介した「サクセスフル・エイジング」の概念は特に印象的でした。
これは単に長生きすることではなく、
- 病気や障害がないこと
- 認知能力や身体機能を維持すること
- 社会とつながって役割を持って生きること
の3つの要素から成り立つとのこと。
特に3つ目の「社会とのつながり」が重要だと強調されていました。
さらに興味深かったのは、人間の能力の発達曲線についての説明です。
従来の考え方では若い時に能力がピークを迎え、その後低下するとされていましたが、実際には様々な能力があり、年齢によって異なる発達パターンを示すとのこと。
具体的には、短期記憶能力は30歳頃から低下する一方で、語彙力や問題解決能力は年齢を重ねても伸び続けるというデータが示されました。
この事実は、老いを「成熟のプロセス」として捉える視点を提供してくれました。
セカンドライフの設計について、秋山氏は「働く」「学ぶ」「遊ぶ」「休む」をうまく組み合わせながら役割を持って生きることが重要だと強調しました。
これらの比率は体の調子や家族状況によって変えていくべきだと述べ、70歳を過ぎてから農業を始め、4人の仲間と株式会社を設立したご自身の体験も共有されました。
「貢献寿命」という新しい概念
最も心に残ったのは、秋山氏が提唱する「貢献寿命」という概念でした。
これは単に健康寿命を延ばすだけでなく、社会とつながり役割を持って生きる期間を延ばすことの重要性を表現したもの。
柏市での高齢者就労支援プロジェクトでは、地域内で歩いていける距離に仕事場を作り、休耕地を活用した農業や植物工場、学童保育などの就労機会を創出。
その結果、就労が高齢者の健康や認知機能に好影響を与えることが科学的に実証されたそうです。
また、「モザイク就労」(時間・空間・スキルのモザイク)という概念も紹介され、ICTを活用したマッチングシステムで個人の関心や能力に合わせた働き方を可能にする取り組みが説明されました。
当事者として感じた共通点
私自身、この講演で最も共感したのは「ただ長く生きることが目的ではない」という視点でした。
障害がある人も、若い世代も同じように「何のために生きるのか」「どんな役割を持つのか」を見つめることが、生きる活力につながるはずです。
高齢者が働く意味も、お金のためだけではなく「社会とつながり続ける」ことにある。この視点は、私自身のこれからの生き方を考えるうえでも大きなヒントになりました。
年齢や障害の有無に関わらず、誰もが社会の一員として役割を持って生きることの価値を改めて実感させられる内容でした。
Age-Well Design Award(個人部門)レポート
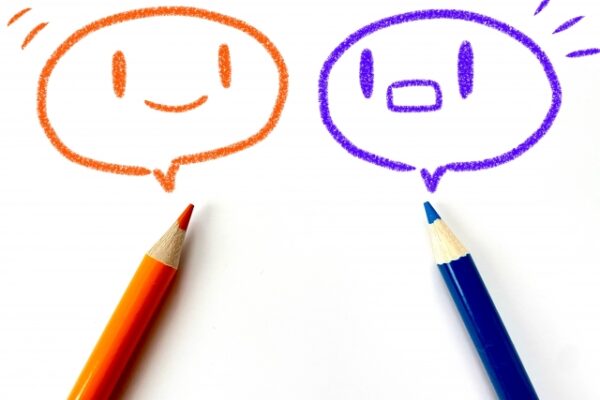
午後に行われたAge-Well Design Award 個人部門の表彰式。
ここで紹介された5つの実践はどれも華やかな新技術よりも、「人と真剣に向き合う」ことの力を静かに証明していたように感じます。
5つの実践事例から見えた共通点
リハビリテーション病院での関わりでは、半身麻痺となった77歳の女性が「こんな体じゃ生きていても意味がない」と諦めていたところから、トイレの自立という小さな目標を積み重ね、最終的に「夫と鎌倉に行きたい」という前向きな目標を持つまでの変化が紹介されました。
介護施設での「夢を叶えるプロジェクト」では、認知症を患う87歳の女性の過去の好きだったこと(紅茶、ホテル、英語)を掘り起こし、施設内でアフタヌーンティーパーティーを開催。その結果、「次は外でケーキを食べたい」という新たな目標が生まれたそうです。
他にも、リフォーム事業を通じて「もう年だから」を「まだまだ」に変える支援や、スマートフォン販売でのデジタル不安解消、孫世代の相棒サービスでの伴走支援など、多様な分野での取り組みが発表されました。
傾聴がつくる変化
受賞者たちに共通していたキーワードは、何よりも「傾聴」でした。
高齢者とひと口に言っても背景や望みは一人ひとり違います。
「自分はこうしてあげれば良いだろう」と決めつけるのではなく、相手が何を求めているかを時間をかけて聴き取り、その声を起点に支援を組み立てる。
その基本を徹底していたことに深く心を動かされました。
もう一つ印象的だったのは、「小さな成功体験を積み重ねる」というアプローチです。
いきなり大きな目標を設定するのではなく、段階的な目標設定と即時のフィードバック・称賛で自己効力感を高めていく手法が、どの事例でも共通して使われていました。
当事者として感じた気づき
私自身、福祉を発信する立場として「自分が語りたいこと」「伝えたいこと」を優先しがちでした。
けれど今回のアワードで、「相手が何を求めているのか」に耳を澄ませることこそが、次に進むための一歩だと痛感しました。
発達障害や高齢者支援など分野を問わず、傾聴から始まる支援が人の可能性を引き出す。
そのシンプルで力強い原点を、これから自分の発信に活かしていきたいと思います。
Age-Well Design Award (企業部門)レポート
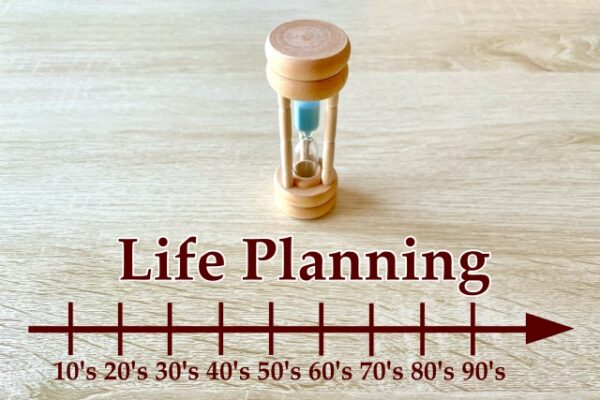
続いて企業部門の表彰式。
ここで紹介された8社の取り組みはどれも最新技術の華やかさよりも、「人と真剣に向き合う」ことの力を静かに証明していたように感じます。
8社の実践事例から見えた共通点
外見ケアで尊厳を守る取り組みでは、有料老人ホームで寝たきりや発語困難な方に個別化した外見ケアを提供。ケアを通じて表情や目線が回復し、家族や施設全体のケア意識が向上する変化が紹介されました。
地域コミュニティの再生では、近隣住民をつなぐアプリ運営だけでなく、実際の地域拠点も併走。60代以上の参加比率が高い「地域の仕事マッチング」**で、シニアの技能と地域ニーズをつなげています。
在宅介護の新しい仕組みとして、月30本のコンテンツを配信。属人的になりがちな介護サービスを標準化し、入居者一人ひとりの「やりたい」を形にする取り組みを展開しています。
他にも、対話型生成AIで遺言作成を「未来へのギフト」として支援する取り組みや、住まいを「薬」に見立てた自己回復力を育む住環境デザイン、看護の語源「nurse=育む」に立脚した地域づくりなど、多様な分野での実践が発表されました。
技術よりも「人」を起点にした企業姿勢
私は最初、企業部門と聞いて「最新技術のアピール合戦」を想像していました。
ところが実際に目にしたのは、人を中心に置いた地道な取り組みばかり。
もちろん生成AIやアプリなどの技術は活用されていますが、それはあくまで人と人をつなぎ、寄り添うための手段でした。
各社がそれぞれの得意分野を活かし、「自分たちだからこそできる福祉」を模索している姿も印象的でした。
当事者として感じた気づき
どの企業も、単なるサービス提供にとどまらず、「自分たちの強みをどう福祉に活かすか」を真剣に考えていました。 「企業=営利」だけではない現実に、素直に感動しました。
私自身、発信者として「自分が伝えたいこと」を優先しがちでした。 けれど今回の企業部門で、個人部門と同じく「相手が何を求めているのか」に耳を澄ませることの大切さを改めて実感しました。
企業であっても個人であっても、傾聴から始まる支援が人の可能性を引き出す。 そのシンプルで力強い原点は変わらないのだと、これから自分の発信にも活かしていきたいと思います。
「老いを再定義する」体験から見えたもの

Age-Well Conference & Festival 2025は、単なるイベントではなく、「老い」や「長寿」をどう生きるかを社会全体で問い直す場でした。
一日を通して感じたのは、高齢化社会を支えるキーワードは”人”そのものだということです。
基調講演からは、人生100年時代を「衰え」ではなく成熟と貢献のプロセスとして捉える視点を学びました。
個人部門の受賞者からは、傾聴と寄り添いが人の可能性を引き出す力になることを、実例をもって示されました。
企業部門では、最新技術を活かしつつも、人と人のつながりを中心に据えた地道な取り組みが多く、福祉の本質を改めて実感しました。これは、高齢者だけの話ではありません。
「何のために生きるのか」「自分にできる社会への還元は何か」という問いは、若い世代にも、障害のある当事者である私自身にも深く響くものです。
福祉は特定の人のためだけにあるものではなく、誰もが自分ごととして向き合うテーマ。 「老い」をポジティブに捉えることは、自分のこれからの人生をどうデザインするかを考えることでもあります。
今回の体験を通じて、福祉を発信する一人として。そして一人の生活者としても「老いを再定義する」というメッセージを、これからの発信や日常の選択の中で生かしていきたいと強く感じました。
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- 移乗介助のリハビリにも|自立支援型立位介助ロボット『すくっとたてる君』開発背景 - 2025年12月12日
- 障がいがある方向けの短時間職業体験が育む「働く自信」|志村学園×レバレジーズの挑戦 - 2025年12月4日
- 絵本が紡ぐ、共生社会への想い|絵本作家・由美村嬉々(木村美幸)先生インタビュー後編 - 2025年12月2日



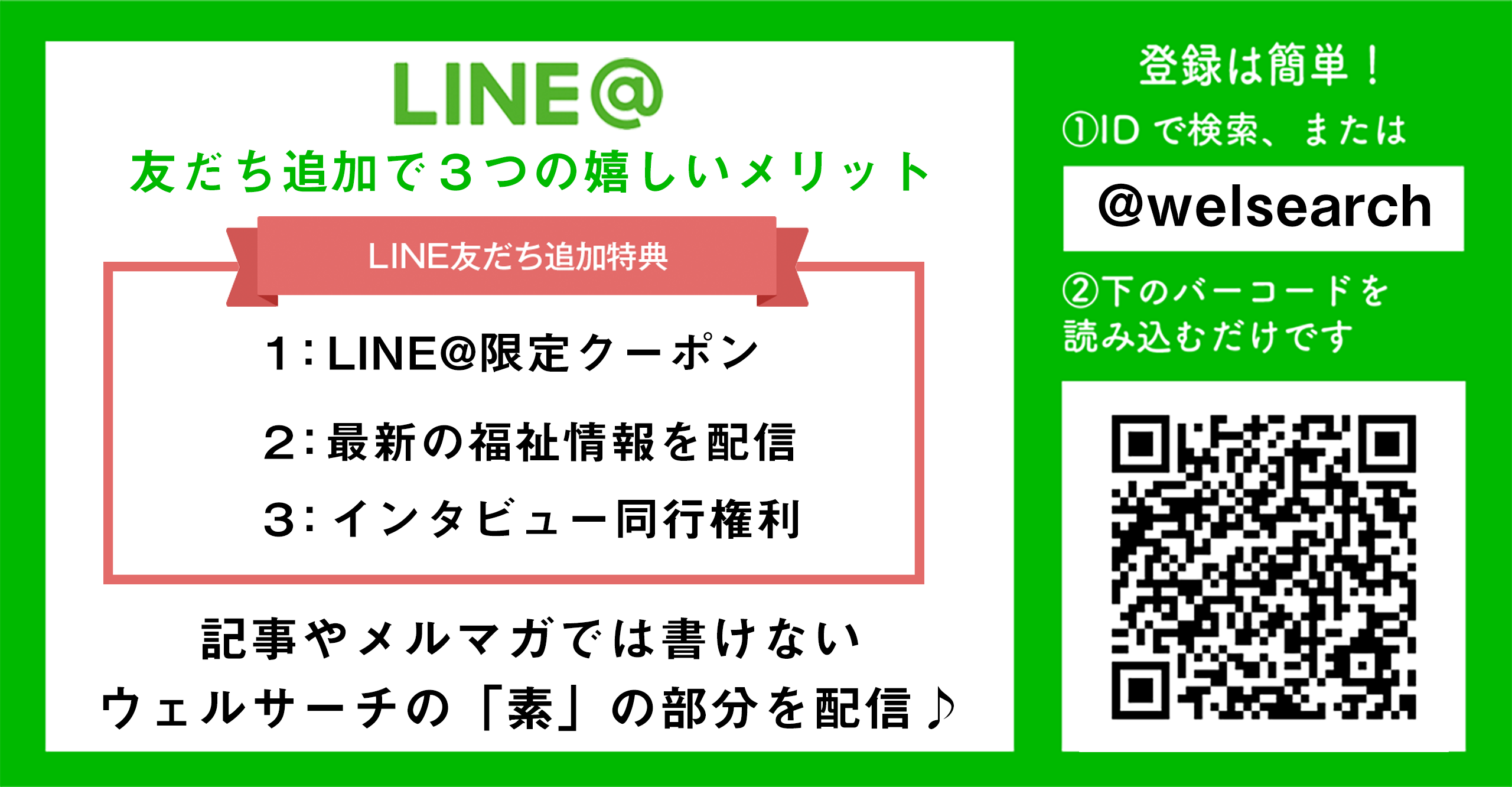
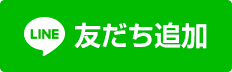
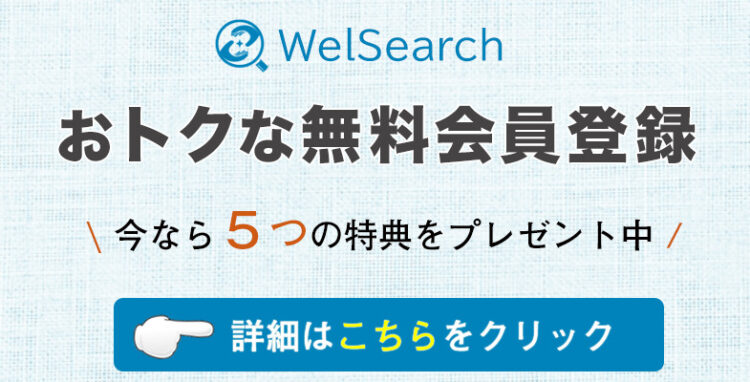

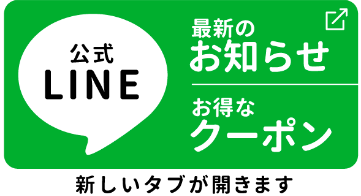


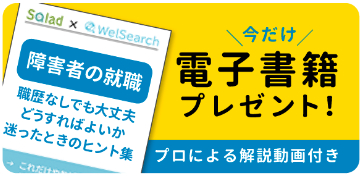
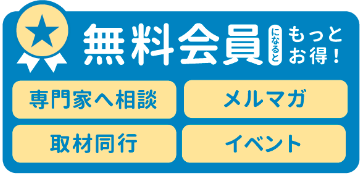

この記事へのコメントはありません。