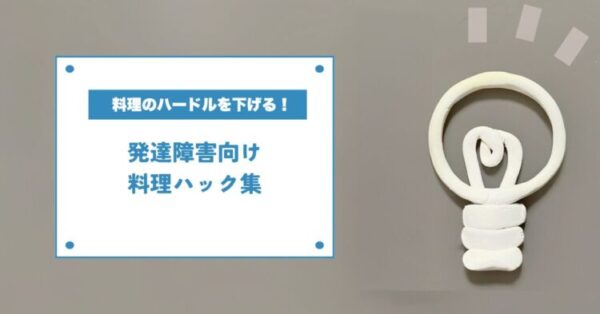料理は、思っている以上にエネルギーが必要です。
特に発達障害があると、「何から始めたらいいのかわからない」「途中で疲れて投げ出してしまう」など、多くの困りごとに直面することがあります。
私自身も、火をかけたまま忘れてしまい、思わぬ事故になりかけた経験がありました。そんな経験から、「できるだけ楽に、でも安心して食事ができる工夫」を探すようになったのです。
最近では、冷凍食品や100均の便利グッズを活用することで、料理のハードルをぐっと下げることができます。
今回紹介するライフハックは、発達障害のある方だけでなく、忙しい方や体力に不安のある方にも役立つ生活の知恵です。
私の体験をもとに、ちょっとした工夫で「料理の面倒くささ」を軽減する方法を紹介していきます。
お好きなところからお読みください
発達障害当事者にとっての「料理」とは?
料理は、生きるために必要な日常のひとつですが、発達障害(ADHDやASD)がある方にとっては、想像以上に負担の大きいタスクとなります。
「料理が苦手」と一言で片付けられがちですが、その背景には、発達障害の特性による様々な困難が隠れているのです。
ADHD・ASDの特性が料理に影響する
発達障害のある方が料理でつまずきやすい理由として、以下のような特性が関連してきます。
ADHD(注意欠如・多動症)の例
- 手順を覚えられず、段取りがバラバラになる
- 注意がそれやすく、火の消し忘れや食材の入れ忘れが発生する
- 一つの作業に集中しきれず、途中で飽きてしまう
- 食材を出しっぱなしにして片付けが後回しになりがち
ASD(自閉スペクトラム症)の例
- 食材の触感やにおいが苦手で、調理に強いストレスを感じる
- 音や光に敏感で、調理中の環境が苦痛になる
- こだわりが強く、レシピ通りにできないと落ち着かない
- 予定外の変更に対応できず、料理中にパニックを起こすこともある
こうした困難は、料理に限ったことではありません。
日常生活のさまざまな場面で同じように現れるため、発達障害のある人にとっては、「当たり前の日常」をこなすこと自体が高いハードルになりやすいのです。
「失敗の積み重ね」が苦手意識を深めていく
こうした困難があると、料理を始めるたびに「うまくいかない」「疲れる」「怒られる」といったネガティブな経験が積み重なりやすくなります。
たとえば…
・「うっかり鍋を焦がしてしまい、自分を責めてしまった」
・「料理ができない=ダメな人間だと思われる気がする」
・「挑戦してもまた失敗するのが怖いから、やらないようにしている」
このような心理的ハードルは、多くの当事者に共通する悩みとも言えるかもしれません。
他の障害にも通じる”料理の壁”
料理に関する困りごとは、発達障害に限ったものではありません。
たとえば、身体障害がある方が包丁を使うのに苦労したり、慢性的な疲労や体力の問題を抱えている方が長時間の調理を避けたくなるのも、同じように”料理の壁”を感じている状態といえるでしょう。
だからこそ、「誰でも使える、ラクになる工夫」を見つけていくことが大切になってきます。
料理のハードルを下げる!近年の便利な流れ
理に苦手意識があると、「失敗したらどうしよう」「何から始めたらいいのか分からない」と不安になりがちです。しかし最近では、冷凍食品・ミールキット・スマート家電・便利グッズの進化によって、そうした不安をやわらげてくれる選択肢がどんどん増えてきました。
時短・簡単・安全に使えるアイテムが続々登場!
ホームセンターやネット通販などをなんとなく眺めていると、面白そうだなと思った商品はありせんか?
たとえば…
- 電子レンジだけで食べられる冷凍ミール
- カット済み食材とレシピが届くミールキット
- 火加減や調理時間を自動で調整してくれるスマートオーブン
- ボタンひとつで缶や瓶を開けられる自動オープナー
- 滑り止め付きの調理器具や視覚に配慮した計量カップなど
どれも、「料理にハードルを感じる人」にこそ使ってほしい、心強い道具ばかりです。
「便利なものを使っていい」時代に
かつては「手間をかけることこそが正義」といった空気がありましたが、今はそうではありません。
無理なく、自分のペースで生活を整えていくために、便利な道具を活用すること”前向きな選択なのです。
私自身、こうした道具に興味を持つようになってから、「これなら失敗しなくて済むかも」と少し前向きに料理に向き合えるようになりました。
冷凍食品×100均グッズでできる!簡単ライフハック
「料理は面倒」「手間が多すぎる」と感じている方にとって、冷凍食品と100円ショップの調理グッズは、心強い味方となります。ちょっとした工夫で、火を使わず、包丁もいらず、洗い物も最小限に抑えることが可能です。
【冷凍食品編】電子レンジ一つで済む”ラクうまごはん”
最近は、電子レンジでチンするだけで完成する冷凍食品がたくさん登場しています。
一例として…
- 麺類(うどん・ラーメンなど)は、そのまま容器ごと温めるだけ
- 冷凍野菜はカット済みで、炒め物やスープにもすぐ使えて便利
私自身も、「電子レンジひとつで済む」冷凍麺やご飯をよく活用しています。そこに冷凍野菜をちょっと足せば、栄養もとれる一皿ごはんに早変わりするので手放せません。
【100均グッズ編】料理が苦手でも安心して使える
100円ショップには、料理のハードルをぐっと下げてくれる便利グッズが揃っています。
- 温野菜メーカーやレンジで卵料理が作れる容器
- 一人用ごはん炊き容器やノンスリップ付き保存容器
- シリコンスチーマーは特にお気に入り。使い終わったらたたんで収納できるのも◎
こうしたアイテムは、「火を使わない」「包丁を使わない」だけで本当に安全になると実感しています。失敗しづらく、安心してチャレンジできるようになりました。
【組み合わせアイデア】私が実践している例
私が日常でよくやっているのは、冷凍の麺類+シリコンスチーマー+冷凍野菜の組み合わせです。麺と野菜を一緒に加熱するだけで、お手軽栄養ごはんが完成します。また、一膳分のご飯を小分け冷凍しておけば、食べたいときにすぐ温めて食べられて本当に助かりました。
他にも…
- 冷凍おかずと一人用のプレートを組み合わせて「洗い物ゼロ弁当風」
- 小分けトレーにスープやおかずを冷凍して、朝レンチンで一品完成」
なんていう工夫もしています。あなたならどう組み合わせますか?
私の料理のリアルと、小さな成功体験
料理をしようとすると、思いがけない失敗ってありますよね。私の場合、「火をつけっぱなしで忘れてしまった」という経験が何度かありました。幸いIHだったので大事には至りませんでしたがも、鍋を焦がしてダメにしてしまいます。
そのとき思ったのは「やっぱり自分には料理は向いてないのかな」という気持ちでした。安全には気をつけたいけど、それ以前に「料理をすること自体が怖くなってしまった」のです。
電子レンジから始まった、小さな一歩
そんな私が変わるきっかけになったのは、ある日100均をふらっと歩いていたときに見かけた、「電子レンジで簡単に○○が作れる!」という調理グッズでした。元々100均巡りが好きだった私は、「まあ試してみるか」と軽い気持ちで手に取ります。
お湯を沸かさなくても作れることに驚きましたし、「これならインスタントばかりじゃなくて、もう少し体にいいものも食べられそう」と感じました。
火を使わない・包丁を使わない=安心してチャレンジできる
それからは、火を使わずに済む冷凍食品や電子レンジ用グッズを活用するようになりました。特にお気に入りなのは、冷凍うどんとシリコンスチーマーです。そこに冷凍野菜を足すだけで、立派な一食になります。
火も包丁も使わず、洗い物も少ない。これだけで「失敗したらどうしよう」という不安が減って、自然と料理にチャレンジできるようになりました。
今の私にとって、料理は”自分をつくる”時間
今では、料理はただの作業ではなく、肉体的にも精神的にも「自分を作る」時間になりました。便利グッズに頼りすぎず、でもうまく活用しながら、「今日はこの食材を使ってみよう」「これなら簡単に作れそう」と、ちょっとした工夫を考えることが日々の楽しみになっています。
ちょっとした工夫が、暮らしを変える
過去の自分に伝えたいことがあるとしたら、こう言いたいですね。「視野をちょっと広げるだけで、料理に限らず生活ってもっとラクになるよ」と。
食事はただの栄養補給じゃなく、楽しむものなのです。そして、そこに「作る楽しみ」が加われば、もっと食事が豊かになると今では感じています。
まずはここから!今日からできる小さな工夫
「料理を始めなきゃ」と気負わなくても大丈夫です。ほんの少しの工夫で、日々の食事はぐっとラクになるものです。
たとえば、100円ショップで気になる調理グッズをひとつ選んでみるだけでも、「これならやってみようかな」という気持ちにつながります。
コンビニやスーパーで冷凍食品をいくつかストックしておくと、疲れている日や気分がのらないときにも、「とりあえず食べられる」安心感が生まれるでしょう。
最初からうまくいかなくても、グッズを使いこなせなくても、「ちょっと試してみた」「今日は火を使わずに済んだ」そんな一つひとつが、大きな前進になります。
料理は、あなたのペースで進めていくもの。あなたのやり方で、ラクに、楽しく、少しずつ付き合っていければ、それだけで十分だと思います。
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- コスプレで届ける笑顔と元気──日本コスプレ委員会の地域貢献活動 - 2026年2月14日
- 多様性を認め、それぞれの得意で生きる社会へ|発達障害当事者会「一刻の会」が歩む支援の道 - 2026年2月12日
- すべての家族に”写真を撮る喜び”を 医療的ケア児・発達障害児にも寄り添う写真館 - 2026年1月20日