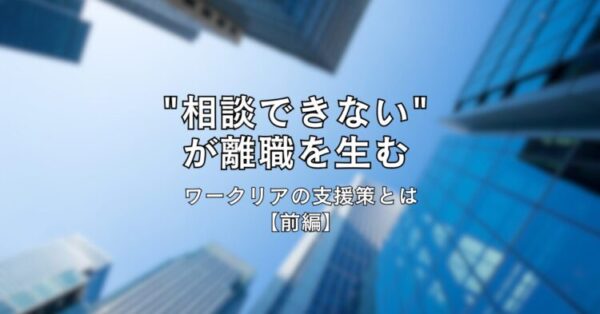精神・発達障がい者の定着率は45%。多くが「相談できない」ことで離職します。
一方、ワークリアは約150名を雇用し、定着率約90%を実現。
未経験者が多い中でなぜ高い定着率を保てるのか。
秋葉原のサテライトオフィスで事業責任者の津留様、広報担当の安藤様に伺いました。
お好きなところからお読みください
ワークリアの事業概要と障がい者雇用への取り組み
—— まず、ワークリア様の事業についてご説明をお願いいたします。
——津留様 (以下敬称略)
ワークリアは、レバレジーズ株式会社が運営する障がい者の就労支援サービスです。
レバレジーズは2005年4月の設立で、今年の4月でちょうど20周年を迎えました。現在、社員数は約4,000名、昨年度の売上高は1,000億円を突破しています。創業以来、黒字経営を継続している会社です。
事業内容としては、自社メディアや人材関連事業を展開しています。IT人材サービスの「レバテック」や、福祉・看護師・保育士などの人材事業を手がける「レバウェル」などが主力サービスです。
現在、50以上のサービスを運営しており、IT事業、ヘルスケア事業など、多岐にわたる領域で事業を展開しています。私たちが所属しているワークリアは、若年層事業の中に位置づけられるサービスで、私はこのワークリアのサービス責任者を担当しています。
ワークリアの社内におけるミッションは、レバレジーズ株式会社の法定雇用率の達成と社内サービスにおけるBPO成果の最大化です。現在ワークリアでは、約150名の障がい者の方を雇用し、レバテックやレバウェル、経理、総務など様々な別事業部の業務を請け負っています。
働いていただいている方の特徴としては、若い世代が中心です。
9割以上が34歳以下の若年層です。未就業の方、つまり働いた経験がない方が多くいます。
また、正社員として働いていたものの体調を崩され、障がい者雇用として初めて働く方もいらっしゃいます。
障がい種別としては、精神・発達障がいの方が9割を占めています。年齢が若く、就労経験が少なく、精神・発達障がいをお持ちの方が、現在150名ほど在籍しているという状況です。
——拠点はどちらにあるのでしょうか。
——津留
都内と千葉に拠点があります。
渋谷に2拠点、秋葉原に2拠点、千葉に1拠点の、合計5拠点で運営しています。この部署は2018年に設立され、今年で8年目を迎えました。
未経験者やスキルの浅い方を積極的に受け入れている姿勢が印象的でした。5拠点で展開し、8年の実績を積み重ねてきた組織の基盤がしっかりしていることが伝わってきます。
なぜ精神・発達障がいに注目するのか
—— 精神・発達障がいの方に注目されているのは、やはり精神・発達障がいの方が増えているという背景があるのでしょうか。
——津留
おっしゃるとおりです。数が増えてきているというのが一番大きな理由です。
—— 一般的に企業は、身体障がいの方は雇用するけれど、発達障がいの方は敬遠する傾向があると聞きます。そういった傾向は実際にあるのでしょうか。
——津留
当社は障がい者雇用には後発で参入した企業です。
オフィスのバリアフリー化など、身体障がいの方を雇用するための物理的な環境整備が特に整っていたわけではありませんでした。
そのため現状では、デスクワークを中心とした業務で能力を発揮したいとお考えの方々にご活躍いただいています。
結果として、現在は精神・発達障がいのある方々の採用が中心となっております。
——一般企業では、発達障がいの方をどう扱っていいかわからないという部分が大きいように思います。
——津留
ADHDは最近かなり有名になってきた障がい名だと感じます。一方で、自閉症やASDと呼ばれると、まだ認知が十分ではなく、もっと重い障がいというイメージが強くついてしまう傾向があります。
「発達障がい」という言葉でくくられた時に、最初にイメージされるのは圧倒的にADHDが多いという印象です。
—— ADHDは、少し慌てん坊で失敗しやすいというイメージが強いですね。一方で、ASDの方は特に人間関係で困難を抱えることが多いように思います。一般企業に入っても、障がい者雇用であっても、相談できない部分が大きいのではないでしょうか。
——津留
ASDの方で前職が一般雇用だった場合、短期で辞めてしまった方が多くいらっしゃいます。
相談がうまくできなかった、障がいを言わずに入社したという方も多いです。「いけると思って頑張ったけれど、やはり人間関係が…」という理由が一番大きいと感じています。
—— やはり、人間関係が一番大きな離職理由なのですね。
——津留
人間関係の中でも、同僚というよりは上司との関係でうまくいかなかったというケースをよく聞きます。
「すごく怒られた」といった話も聞くことがあります。
—— 私自身もADHDとASDの両方を持っており、相談することができずに前職の工場を辞めてしまった経験があります。
——津留
相談を自分からどのタイミングでしたらいいのか、上手に相談しなければという思いが頭にあるとおっしゃる方が多いです。ただ、コミュニケーションに自信がないため、どうしようと悩んで抱え込んでしまい、パンクしてしまうという話はよく伺います。
ADHDとASDでは企業側の理解度にも差があるという現実も見えてきます。
相談のタイミングがわからず抱え込んでしまう。この課題にどう向き合うかが、定着率を左右するポイントなのだと感じました。
120種類の業務と定着率約90%を実現する仕組み
——津留
BPO組織ですので、レバレジーズグループ内の各部署から切り出した業務を、障がい者の皆さんに担当していただいています。
業務内容は事務作業だけではなく、かなり幅広いのが特徴です。
データ入力、ライティング、資料作成といった業務に加えて、本社にある社内向けカフェでの接客業務、さらには専門性の高いデータ分析や経理業務まで、多様な仕事をお任せしています。
—— かなり幅が広いですね。
——津留
長くご在籍いただいている方の中には、やりたいことやチャレンジしたいことが在籍中に変わっても、その中で挑戦できる環境があります。
これが、ワークリアで長く働きたいと思っていただける理由の一つになっていると考えています。
常時120種類ほどの業務があるので、挑戦したい意欲のある障がい者の方には、非常に適した環境だと思います。
—— それだけ業務の種類があれば、適性に合った仕事が見つかりそうですね。
——津留
健常者であっても、仕事は実際にやってみないと向いているかどうかわからないものです。
体調が良い日には少しチャレンジングな業務に取り組み、体調が優れない日には自分のペースでできる業務を選ぶなど、体調と相談しながらカスタマイズできる仕組みになっています。
こうした取り組みもあって、現在、定着率は約90%を維持しています。一般的に、精神・発達障がい者の方の定着率は約45%と言われていますので、比較してもかなり高い数字を実現できていると考えています。
——数字で見ると、かなり高いですね。
——津留
現在の障がい者雇用の現状は、精神障がい者の方が大幅に増加しており、その中でも働きたい方が増えています。ハローワークの新規求職申込件数でも、精神障がいの方は顕著に増加している傾向にあります。
一方、企業側も法定雇用率の引き上げが来年7月に控えており、それを達成できていない企業が半数以上存在します。そのため、障がい者雇用を進めなければならないという危機感を持つ企業が徐々に増えています。求職者側でも働きたい障がい者の方が増えているという、双方のニーズが高まっている状況です。
——企業側の障がい者雇用に対する理解は、まだ十分とは言えないのではないでしょうか?
——津留
障がい者雇用でよくあるのが、本人の能力や可能性に対して、過剰な配慮から不必要な制約を設けてしまうケースです。
あまり仕事を任せないといった対応をすることで、本当はできるのに機会を奪ってしまうことがあります。
当社では、障がい者雇用であっても、主体的に働いてほしいという考えのもと一緒に働いています。そういった過度な制約がないことを、喜んでくださるポイントの一つになっているのではないかと思います。
健常者でも実際にやってみないと向き不向きはわからないという言葉が印象的でした。
過剰な配慮で機会を奪うのではなく、主体的に働ける環境を用意する。この考え方が、障がい者雇用の本質なのかもしれません。
企業が選べる3つの障がい者雇用手法
——津留
現在、他の会社様に提供しているサービスが、「ワークリアStep」になります。企業が障がい者雇用を行う際の手法は、主に3つあると考えています。
1つ目は、企業が自社で面接を行い、採用し、業務を切り出して、その会社の中で雇用するという、当社のような一般的なパターンです。
2つ目は農園型です。
—— 農園型というのは、初めて知りました。
——津留
農園型とは、業務創出や定着支援のノウハウに課題を感じている企業が活用する仕組みです。専門企業のサポートを受けながら、障がい者の雇用機会を生み出します。
この仕組みでは、障がいのある方は企業の社員として雇用契約を結びます。しかし実際の勤務地は自社オフィスではなく、提携している専門農園です。
業務内容は、自社のコア業務とは別の役割として、コーヒー豆の焙煎や農作業などを専用の施設で行っていただくスタイルになります。
企業にとっては、採用後の定着支援などを専門パートナーに一任できるため、実務的な関与を抑えつつ雇用を推進できるというメリットがあります。また、収穫物を福利厚生として活用し、社内コミュニケーションの活性化に繋げている事例も見られます。
—— 発達障がいの方が農園で働くのに向いているという話を聞いたことがありますが、実際のところ、適性はあるのでしょうか。
——安藤
農園型の業務は、オフィスワークと比べて単純作業が中心になるため、業務内容的にプレッシャーがかかりにくいという特徴があります。
そのため、体調の調整がしやすく、精神的な負担も軽減されます。特に精神障がいの症状が重めの方などは、農園の方が働きやすいとおっしゃるケースもあります。
ただ、もちろん個人差はありますので、一概には言えない部分もあります。
—— 発達障がいの方への支援として農園型が推奨されることも多いですね。
——津留
業務自体が難しすぎて対応できない方や、障がいの程度によっても適性は変わってきます。農園型で働けてよかったという障がい者の方の声もありますので、何が良い悪いという話ではありません。
ただ、この働き方だと、働く障がい者のキャリアパスが殆ど無い為、昇給や昇進、他業務への切り替えなどの実現が難しい現状があります。また、企業側はずっと農園型サービスを提供する会社に費用を払い続ける形になるため、企業側の負担は継続的に大きくなります。
3つ目がサテライト型です。これはサテライトオフィスの運営会社と提携して雇用する手法になります。
サテライト型では、障がいのある社員が、本社から離れた専用のオフィスに勤務し、自社の実務やサポート業務を行う働き方です。障がい者の方を雇用したことがなく、マネジメントのノウハウがない企業にとっては、導入しやすい選択肢といえます。
ただ、基本的には業務の切り出しが必要になります。
当社の場合は業務切り出しのサポートも行っていますが、事務業務など障がい者の方にお任せする業務の準備がないと、活用が難しい面もあります。
また、契約サービスを利用する形になるため、費用はかかります。その中で、昨年12月からリリースしているのが、当社が運営する「ワークリアStep」というサテライトオフィスサービスです。
当社では既に150名ほどの障がい者の方を雇用しており、1年間の定着率が約90%という実績から、ノウハウが蓄積されていました。それを他の企業様にも提供したいという想いからスタートしたサービスです。
「ワークリアStep」の主なサービス内容
——津留
まず1つ目が、サテライトオフィスという場所の提供です。
2つ目が採用支援で、面接のサポートや人材紹介も行っています。
3つ目が労務育成支援です。障がい者の方への研修や業務サポートを実施しています。
さらに、業務の切り出しも行っているため、自社で障がい者の方に任せる業務の切り出しが難しい場合でも、当社で切り出した業務を提供することが可能です。
—— 今日伺っているこちらが、その拠点ですね。
——津留
はい、今回お越しいただいたのが、秋葉原のサテライトオフィス拠点です。当社の社員が常駐しており、働きやすい環境を整備しています。
最大の特徴は、「企業で活躍できる戦力になるまで、当社がしっかりと育成する」という点です。
障がい者雇用の経験豊富なレバレジーズの社員が常駐し、戦力化までの育成をサポートしています。
—— 就労支援施設とも近い形態なのでしょうか。
——津留
仰る通りで、常駐している社員の中には、国家資格を保有している専門スタッフもおり、安心してご利用いただける体制を整えています。
業務の振り返りや体調管理も、当社の専門スタッフが対応しているため、定着率も比較的高い状態を維持できています。現在、隣と隣のお隣の部屋では、別の企業の障がい者社員の方が実際に勤務されています。
特に農園型はキャリアパスが限られるという課題があり、サテライト型のワークリアStepは業務の切り出しから育成まで包括的にサポートする点が特徴的です。
国家資格を持つスタッフが常駐し、戦力化まで伴走する。企業にとっても障がい者にとっても安心できる仕組みだと感じます。
インタビュー前半を終えて
ワークリアが提供する「ワークリアStep」は、障がい者雇用のノウハウがない企業でも安心して導入できるサテライト型サービスです。
業務の切り出しから採用支援、育成まで包括的にサポートし、国家資格を持つ専門スタッフが常駐する環境で、未経験の障がい者を戦力化していきます。企業内雇用、農園型、サテライト型。
3つの手法にはそれぞれメリットとデメリットがあり、企業の状況に応じて選択できる時代になってきました。大切なのは、「障がい者を雇用する」という義務感だけでなく、「どう働いてもらい、どう活躍してもらうか」を考えることなのかもしれません。
では、ワークリアで働く障がい者の方々は、どのような支援を受けているのでしょうか。週1回の振り返り面談、業務量調整シート、感覚過敏への配慮。具体的な支援内容と、「相談しやすい環境」がなぜ定着率約90%につながるのか。
後編では、現場で実践されている具体的な支援の仕組みと、転籍後も同じ環境で働けるユニークな制度、そして未来に向けた展望について詳しくお伝えします。
相談できないが離職を生む|障害者雇用の定着率90%以上を誇るワークリアの支援策とは【後編】
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- すべての家族に”写真を撮る喜び”を 医療的ケア児・発達障害児にも寄り添う写真館 - 2026年1月20日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【後編】 - 2026年1月12日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【前編】 - 2026年1月11日