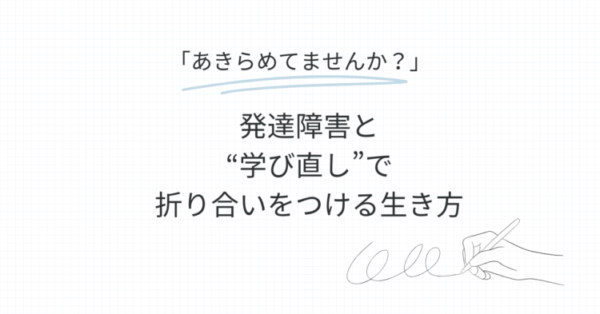発達障害には大きく分けて
- 注意欠如多動症(ADHD)
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 限局性学習症(SLD)
があります。
私はADHDとASDの両方の特性があり、これまでの人生でうまくいかないことの連続でした。
-
- 忘れ物やなくし物が多い
- 言わなくていいことを言ってしまい、場の空気が読めない
- うっかりミスが多く、職場で叱責される毎日
障害のことを知った当初は「障害だからしょうがない」というあきらめの気持ちが強くありました。しかし、当事者として発信を始め、学び直しを重ねる中で、少しずつ変化が生まれています。
今回は、発達障害との「折り合いのつけ方」について、私自身の体験をお伝えします。障害を知ることで見えてきた、あきらめではない道筋をご紹介できればと思います。
お好きなところからお読みください
勉強を始めたきっかけ
現在私は、児童発達支援士という資格の取得を目指して勉強しています。
発信者としての責任感から
発信者として当事者目線の体験談は重要ですが、何かを発信するのであれば裏付けとなる知識も必要です。特に発達障害という分野では、間違った情報や根拠のない方法論が広まってしまうリスクもあります。
SNSやブログには「これで発達障害が改善する」「この方法で人生が変わった」といった情報があふれていますが、中には科学的根拠に乏しいものや、特定の人にしか効果がないものも少なくありません。
私自身も診断を受けた直後、藁にもすがる思いで様々な情報を試しました。ですが、結果的にどれも期待したような効果は得られません。時間とお金を無駄にしただけでなく、「やっぱり自分はダメなんだ」という諦めの気持ちを強くしてしまいました。
こうした経験から、当事者が混乱してしまう情報の怖さを身をもって知っています。だからこそ、私が発信する情報には責任を持ちたい。根拠のある、信頼できる内容をお伝えしたいという思いが強くなったのです。
資格取得への決意
そこで、発信内容により信頼性を持たせるために、児童発達支援士の資格勉強を始めました。(同時に「発達障害コミュニケーションサポーター」という資格の勉強も進めています。)
「児童」と名前に付いているため、最初は「大人の発達障害には関係ないのでは?」とも思いました。しかし調べてみると、発達障害の基本的な理解や支援の考え方は、年齢に関係なく共通する部分が多いことがわかったのです。
学び続ける意味
正直なところ、50代になってから資格勉強を始めることに迷いもありました。「今さら勉強して意味があるのか」「若い人に比べて覚えが悪いのでは」「仕事や家庭と両立できるのか」といった不安もあったのです。
周囲からも「そんなに頑張らなくても」「体験談だけで十分じゃない?」という声もありました。確かに、発達障害の当事者として体験談を語ることにも価値があります。でも、それだけでは不十分だと感じていました。
「学問に王道なし」という言葉があるように、勉強はいくつになっても意味があるものです。むしろ、人生経験を積んだ今だからこそ、学んだ知識を実体験と結びつけて理解できる部分もあると思います。
読者により信憑性の高い情報をお届けしたいという思いで学習を続けていますが、勉強を進める中で思わぬ副次的な効果があることに気がつきました。
思わぬ発見:学んでいたのは”他人のため”じゃなかった
「児童発達支援士」という名前からもわかるように、この教材は発達障害を抱える子どもの親御さんや支援者に向けたものです。発達障害を持つ子どもに対してどのように接するか、どのような支援方法があるかが詳しく紹介されています。
まだ学習途中ではありますが、勉強を進める中で様々な支援法を学んでいます。
- TEACCH(構造化された教育プログラム)
- ABA(応用行動分析)
- SST(ソーシャルスキルトレーニング)
福祉の発信者として「このような支援方法があるのか」と改めて知識を深めていたのですが、学習を続けるうちに、ある疑問が浮かんできました。
「これは子どもの療育のためのテキストだけれど、大人にも応用できるのではないか?」
TEACCHの構造化や視覚的支援、ABAの行動分析など、テキストで学ぶ内容は子どもだけでなく、発達障害に悩む大人にとっても十分有益なはずです。
「発達障害だからもうしょうがない」そう諦めていた自分にとって、今学んでいることを実践すれば何か変わるかもしれない。まだ小さな光ですが、希望が宿った気がしています。
「年齢に関係なく、人は変われる」という実感
一例として「物理構造化」というものがあります。簡単に言うと「場所と活動の結びつけ」です。
例えば:
-
- 食卓は食事をする場所、仕事をする場ではない
- ベッドは寝る場所、スマホを見る場所ではない
このように、その場所で何をするかを明確にすることです。意識的に「ここで何をするか」を決めるだけでも効果がありますし、物理的に仕切りを置いて視覚的に場所と活動を区別することで、混乱や迷いを防ぎ、集中しやすくできます。
児童支援で紹介されているこの物理構造化は、決して子どもだけに有効な支援ではありません。「子どもに必要なことなんて大人には効果ない」と思う方もいるかもしれませんが、学んで実践してみると、自分の生活に応用できることがたくさんあります。
物理構造化で得られる効果
実際に物理構造化を実践することで、以下のような変化が期待できます
混乱・不安の軽減
「どこで何をすればいいか」が空間で明確になることで、生活や仕事の中で迷ったり混乱したりする場面が減り、安心して活動できるようになります。
集中力の向上
余計な刺激を除いた空間作り(パーテーションや整理整頓など)によって、一つの作業や活動に集中しやすくなり、ケアレスミスを減らせます。
見通しの改善
「何をいつどこでやるか」を視覚的に把握できることで、不安やイライラが減り、自分で行動しやすくなります。
自信と自立の促進
活動・生活の”仕組み”が明確になることで、自分の力で判断・行動できる場面が増え、自己効力感や自立度が高まります。
パフォーマンスの向上
業務や勉強でも、必要な情報に注意を集中できる環境が整い、成果・効率もアップしやすくなります。
私自身の実践例
私の場合、以下のような取り組みを始めました。
- パソコンの前で食事をするのをやめる
- プライベートパソコンと仕事用パソコンを分ける
- 仕事場とプライベートの場所も明確に分ける
これらを実践してみると、食事と遊び、仕事とプライベートのスイッチが驚くほど簡単に切り替わるようになりました。仕事への集中もできるようになり、プライベートでは気兼ねなく休めるという効果も感じています。
まだ学習の入り口に立ったばかりの私でも、これだけのことが見えてくるようになりました。
もちろん、これで発達障害のすべての困りごとがなくなったわけでも、発達障害が「治った」わけでもありません。しかし、学ぶことによって少し前進し、障害との折り合いのつけ方が身についてきたのです。
情報化社会だからこその学び直し
今の世の中、ネットには膨大な情報があふれています。有料で有益な情報、無料でも有料級の情報、有料だが役に立たない情報、無料相応の軽い情報。玉石混交の中から必要な情報を見つけるのは確かに大変です。
しかし、昔に比べて学習環境が格段に整っているのも事実です。私がよく活用しているAIツールも、その一つです。
「今更勉強なんて」と思っている方もいるでしょう。実際、少し前の私も「50にもなって勉強しても無駄」という意識が心のどこかにありました。
でも、学びはいくつになっても恩恵をもたらしてくれます。
「折り合いをつける」という新しい視点
発達障害は治すものではなく、折り合いをつけるもの。これは発達障害の特性との付き合い方で大切なスタンスです。
しかし、その折り合いのつけ方を手探りで見つけるのは困難でしょう。私自身、そもそも「折り合いをつける」というスタンスすら知らなかった人間です。
学ぶことで、まず「障害は治すのではなく折り合いをつけるもの」と知ることができました。そして少しずつですが、折り合いをつける方法を身につけ、このように発信できる立場になりつつあります。
学ぶことは自分のためのこと
学ぶこと=専門家になることではありません。
学ぶというのは、まず自分のためにすることです。それが巡り巡って、他人のためにもなるのです。まずは、小さな一歩から始めてみませんか?
- 気になることをちょっと検索してみる
- 散歩のついでに図書館に立ち寄ってみる
- AIツールで疑問に思うことを質問してみる
どんな小さなことでも構いません。
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- 移乗介助のリハビリにも|自立支援型立位介助ロボット『すくっとたてる君』開発背景 - 2025年12月12日
- 障がいがある方向けの短時間職業体験が育む「働く自信」|志村学園×レバレジーズの挑戦 - 2025年12月4日
- 絵本が紡ぐ、共生社会への想い|絵本作家・由美村嬉々(木村美幸)先生インタビュー後編 - 2025年12月2日