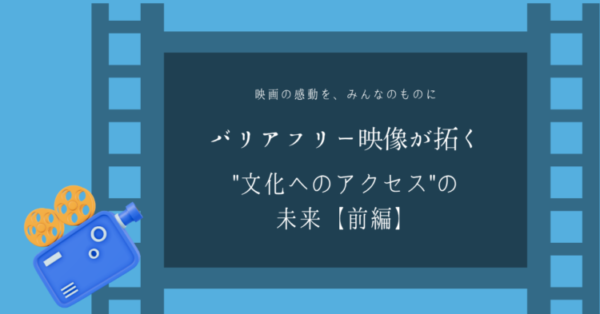「字幕がなければ、一生この映画を観られない」
ある聴覚障害者の切実な声が、すべての始まりでした。
映画や映像を「同じ時間・同じ空間」で楽しむため、字幕と音声ガイドの制作・普及に取り組むNPO法人メディア・アクセス・サポートセンター(MASC)。
設立16年、著作権の壁や技術開発など数々の困難を乗り越え、文化のバリアフリーを実現してきました。
今回は理事・事務局長の川野浩二さんに、その想いと取り組みを伺いました。
お好きなところからお読みください
「字幕がなければ一生観られない」MASCが生まれた理由
――まずは、メディア・アクセス・サポートセンター様の概要を教えてください。
――川野
私たちの事業は、大きく四つの柱で構成されています。
- 「アーカイブ事業」
- 「養成事業」
- 「開発事業」
- 「普及促進」
の4つです。
まずアーカイブ事業は、映像作品に付けられた字幕や音声ガイドを一元的に保存・管理する取り組みです。
例えばテレビ局がアニメ番組の字幕を制作しても、従来はそのデータが局の所有物となり、配信や再放送で活用されることはありませんでした。
視聴覚障害者に必要な情報保障が、その場限りで終わってしまう状況があったのです。
約20年前、活動開始当初からこの状況を改善する必要性を感じていました。
劇場公開時に制作したバリアフリー素材を確実にアーカイブし、配信や放送でも使えるようにする。それが一つ目の事業です。
二番目の養成事業は、バリアフリー字幕や音声ガイドの制作者を育成する取り組みです。
活動開始当時、特に音声ガイドは映画にほとんど存在していませんでした。
一部ボランティアが年間数作品、音源を作ってラジオ送信する程度です。
広げるには作り手を育てる必要があると考え、講座を開設して毎年プロ養成講座を実施してきました。
三番目の開発事業は、制作と鑑賞の両面における技術開発です。
現在は「メガネで見る字幕ガイド」や「スマホで聴く音声ガイド」という形になっていますが、字幕制作ソフトの開発から鑑賞手段の開発まで手がけてきました。
私自身が技術者出身で、作っても提供する手段がなければ意味がないという考えから、この分野に力を入れています。
最後の普及促進が、現在最も注力している部分です。
上映情報サイトなどを通じて、バリアフリー素材を実際に使ってもらう。
誰も使わなければ、制作側のモチベーションも下がってしまいます。
機器の普及も含め、多くの人に利用してもらうことが課題です。
――この事業を始めたきっかけを詳しく教えてください。
――川野
きっかけは約20年前、2005~2006年頃のことです。
当時、私はDVD制作のポストプロダクションで技術の仕事をしていました。
赤坂の職場で、ある聴覚障害の方が署名活動をされているのを知ったんです。
その方も赤坂に勤務されていて、事情を知りたく会社でお会いしました。
聴覚障害があり、どうしても観たい映画のDVDに字幕がついていない問題に直面していました。
字幕をつけて再発売してほしいと、署名活動をされていたのです。
実際にお会いして話を聞いたとき、彼の切実さが心に刺さりました。
「字幕がつかなければ、私は死ぬまでこの映画を観ることができないんだ」と言われたのです。
その言葉を聞いて、そういう現実があると本当に気づかされました。
それが全ての始まりです。
――障害福祉というと生存のための最低限の支援というイメージが強く、映像を楽しむことは後回しにされがちですね。
――川野
おっしゃる通りです。
ただ当時から、世界的には障害者権利条約の動きが始まっていました。
国内法としての障害者差別解消法につながる流れもあり、いずれ解決すべき課題だという認識はありました。
生きるために映画が必要かと問われれば、衣食住とは違うので後回しにされがちです。
でも映画を観て感動し、自分の生き方を考え直すきっかけになることもあります。
生活の潤いとして、文化へのアクセスは非常に重要です。
その理解を得るのが、最初は難しかったですね。
――活動立ち上げ時、どのような困難がありましたか。
――川野
フェーズごとに様々な障害がありました。
最初の大きなハードルは著作権、つまり権利処理の問題です。
DVDに字幕がないという問題から始まったので、MASC設立前の会社員時代ですが、まずDVD字幕の提供方法を考えました。
DVDをパソコンに入れて再生すると、完全同期してネット上の字幕が表示されるプレイヤーを開発したのです。
ところが、字幕の送信可能化権という権利が問題になりました。
クリアには原作者、脚本家、監督、JASRACという四者の許諾が必要でした。
当時は一つの映画に字幕をつけるたびに、作品に関わる四者全員と個別契約を結ばなければなりませんでした。
団体所属なら分かりやすいのですが、個人も含めて全て一件一件契約していたのです。
この状況が2年ほど続きました。
現在は法改正により、私たちは<文化庁の認証団体>となり字幕配信が可能になりましたが、最初は相当なパワーが必要でしたね。
――個人では到底無理ですね。
――川野
無理ですね。
ただクリアした後も、次のハードルがありました。お金の問題です。
制作にはコストがかかります。
メガネ字幕の仕組みにデータを載せるにも、ライセンス契約が必要でお金がかかります。
やったからといって、どれだけ利益が上がるのか。
DVDに字幕をつけても、プラスの収入はどれだけか。単なる出費だけなら、ビジネスとして成り立ちません。
映画は文化であると同時に、ビジネスでもあります。
その意義を説得しながら理解を得ることも、大きなハードルでした。
――ビジネスとして採算が取れないとなると、企業では続けられませんね。
――川野
だからこそ、会社のプロジェクトとして始めましたが、「会社では無理だろう」とNPOを設立したのです。
NPOには映画会社だけでなく、映画を作る側、興行側つまり映画館の団体、聴覚障害者の団体、視覚障害者の団体、点字図書館などサポート団体も参加してもらいました。
ロゴマークにある虹は、この「架け橋」のコンセプトを表しています。
本来それぞれが個別に要望や努力をしていたところを、全部まとめたのがMASCなのです。
著作権の壁、ビジネス化の壁、技術開発の壁。数々の困難を、映画会社も障害者団体も映画館も、みんなが手を繋ぐNPOという形で乗り越えてきた。
その「架け橋」の理念に、文化のバリアフリーへの本気度を感じました。
バリアフリー字幕と音声ガイド 見えない・聞こえない世界を繋ぐ技術
――バリアフリー字幕は、普通の字幕とどう違うのでしょうか。
――川野
聞こえない人向けの字幕には、大きく三つのポイントがあります。
一つ目は「話者」です。
誰が話しているか分からないと困ります。
一人だけのシーンなら問題ありませんが、映画では後ろ向きで話す場合もあり、画面に映っていないのに声がする場合もあります。
誰が喋っているかを示す必要があるのです。
二つ目は「効果音」です。
例えばチャイムが鳴って登場人物が振り向くシーンがあったとします。
聞こえる人はチャイムの音で「だから振り向いたんだ」と分かりますが、聞こえない人にはその情報がありません。
効果音を文字で表現する必要があります。
三つ目は「音楽」ですね。
これは難しい要素ですが、最低限音符マークを入れて音楽が流れていることを示します。
有名な楽曲なら楽曲名を入れたり、可能なら歌詞を入れたりします。
ただしセリフと重なる部分では歌詞は表示しません。
エンドロールなどで入れることが多いです。
取捨選択しながら、聞こえない人に最適な形で情報を提供するのがバリアフリー字幕です。
――視覚障害者向けの音声ガイドは、どういうものでしょうか。
――川野
見えない方向けの情報保障ですが、視覚障害者は非常に豊かな想像力をお持ちです。
これがポイントになります。
基本的にセリフ以外を描写しますが、やりすぎると想像の余地を奪ってしまいます。
情報が入りすぎると、かえって映画を楽しめなくなるのです。
大きなポイントは、映画監督の意向に沿ったガイドを作る必要があるということです。
これは同時性保持権という権利に関わります。
変なガイドをつけると、監督が本来表現したかったものを歪めてしまう可能性があります。
そういったことに気をつけながら、最大限映画を楽しめるガイドを心がけています。
制作の最後には必ずモニター会を開き、当事者に聞いていただきます。
そして監督やプロデューサーとディスカッションする。これが非常に重要なプロセスです。
簡単に言えば、画面が伝える情報を言葉で説明しますが、あくまで映像が主役です。
それを邪魔しない範囲で、適度にガイドをつけていきます。
――演者のセリフもあり、重なると混乱しますね。
――川野
そうなんです。
セリフとガイドを重ねることはまずありません。
逆に言うと、セリフの多い映画は入れる間がなく、そういう悩みもあります。
――映像制作側の意図と、受け取る側の立場、両方を大切にする必要がありますね。
――川野
その通りです。
一方的に制作者だけで判断せず、教育事業の一環として、良い字幕や音声ガイドをまとめたガイドライン冊子を作成しています。
現在2冊目ですが、障害のある方がどう見るか、どう楽しめるかというポイントに沿って、制作基準を定めながら活動しています。
――障害のない立場から、視覚・聴覚障害者の感覚を理解するのは難しいですね。当事者の意見を聞きながら進めるのでしょうか。
――川野
それが非常に大事です。
モニター会は必ず実施しますし、これまでも字幕を見てもらいアンケートを取ったり、音声ガイドを聞いてもらいフィードバックをもらったり、繰り返してきました。
最近アンケートは、あまりやっていませんが、当事者の意見は非常に重要です。
制作者が勝手に「こういうのがいいだろう」と決めて出すのでなく、当事者の意見をフィードバックしてもらいながら、良いものを作ることが大切です。
――制作側が伝えたいことと、受け取る側がどう受け取るかのすり合わせが必要ですね。
――川野
制作側の意図を受け取る側に伝え、受け取る側の感想を制作側にフィードバックする。その橋渡しによって、作品が作れるわけです。
制作の裏には必ずガイドラインと当事者の声がありました。
「制作者が決めるのではなく、受け取る側の感想を聞きながら作る」という姿勢に、本当のバリアフリーとは何かを教えられた気がします。
ろう者と難聴者、立場が違えば求めるものも違う 制作現場のジレンマ
――川野
ただ実は、難しいのは字幕の方なんです。
音声ガイドの場合、例えば「赤い」という表現を使っていいかという問題があります。
生まれつき全盲の方は赤色を見たことがないわけですから。
ただこれはそれほど大きな問題ではありません。
一方、字幕に関しては、生まれつき聞こえないろう者と、途中から聞こえなくなった難聴者・中途失聴者では、完全に文化が異なるのです。
それぞれに団体があり、そのくらい違います。
手話を主言語とするろう者は、生まれてから聞こえないため、文字を読むスピードは比較的遅い傾向があります。
ですから要約した字幕を好まれます。
一方、制作側、特に脚本家からは「要約はしてほしくない」という声があります。
また難聴者からは「要約は絶対にしないでくれ。一字一句、聞こえている音を全部知りたいんだ」という要望が強いのです。
この立場の違いは非常にはっきりしています。
本当にきちんとやるなら、ろう者向けと難聴者向けで字幕を分けた方がいいのですが、現状ではなかなかそうもいきません。
この問題は、字幕に関して今も課題として残っています。
――障害と一口に言っても、本当に様々ですね。
――川野
そうですね。
それを理解しないと、どちらか一方に偏ってしまいます。
――それぞれの立場で考えることが重要ですね。字幕のモニター会は難しいのでしょうか。
――川野
実は字幕のモニター会は実施していません。
音声ガイドのモニター会はやっていますが。
なぜかというと、先ほど言ったように、ろう者の主張と難聴者の主張は明確に違うため、議論の場では噛み合わないのです。
ある意味、最大公約数的なものになると分かっているので、最後にチェックはしていただきますが、議論の場は作っていません。
もう15~20年やっていますので、どういった字幕がいいかのノウハウは蓄積されています。
ガイドラインに沿って制作する形で進めています。
――最近はAIも登場していますが、AIで字幕を作るのと人が作るのとでは違いがありますか。
――川野
制作ツールとしてのAIは確かに使えます。
ただ最後に、その映画のニュアンスや作品全体のトーン、作品を理解した上での最終チェックは、当然人がやらないといけません。
制作ツールとしてのAIは効率よく使えるので、それ自体は良いと思っています。
でも最終的には人の目、人の耳で確認した上で作り込まないと、良いものはできないと考えています。
――人の感性はAIには理解できない部分がありますね。
――川野
その通りです。
特にAIが障害者のことを思ってやるといっても、本当に表面的な情報しか取れない部分があります。
そこは絶対に人の手が必要ですね。
もっとも、将来もっと賢いAIが出てくるかもしれませんが、現時点ではそういうことです。
同じ「聞こえない」という状況でも、求める字幕は真逆でした。
完璧な正解がない中で、15年以上のノウハウを積み重ねながら最大公約数を探り続ける。
AIが進化しても、最後は人の目と耳で確かめる。
その地道な努力に、深い敬意を感じました。
インタビュー前半を終えて
「字幕がなければ一生観られない」という言葉の重さ。
取材を通じて、バリアフリー映像が単なる福祉サービスでなく、文化へのアクセス権を保障する取り組みであることを痛感しました。
川野さんが語る立ち上げ期の困難は、想像以上のものでした。
著作権という法的な壁、ビジネス成立という経済的な壁、そして技術開発という実務的な壁。
一つの映画に字幕をつけるため、原作者、脚本家、監督、JASRACという四者と個別契約を結んでいた時代があったという事実は、この活動の先駆性と困難さを物語っています。
特に印象的だったのは、「架け橋」というコンセプトです。
映画を作る側、映画館、聴覚障害者団体、視覚障害者団体、サポート団体。
本来それぞれが個別に要望や努力をしていた関係者を全て結びつけたNPO設立は、まさに革新的な取り組みでした。
また、バリアフリー字幕と音声ガイドの制作で、「当事者の声を聞く」ことの重要性を改めて認識しました。
制作者が一方的に判断するのでなく、モニター会やアンケートを通じて当事者の意見をフィードバックしながら作り上げていく。
この姿勢こそが、質の高いバリアフリー映像を生み出す源泉なのでしょう。
一方で、ろう者と難聴者で求める字幕仕様が異なるという課題は、バリアフリーの難しさを象徴しています。
要約を好むろう者と、一字一句を求める難聴者。
この対立する要件をどう最大公約数的にまとめるか。
単純な解決策がない問題に向き合い続ける姿勢に、この活動の奥深さを感じました。
後編では、利用者の反響、アーカイブ事業の本格始動、そして「感動をみんなのものに」という理念実現に向けた今後の展望について伺います。
【後編に続く】
後編では以下の内容をお届けします
- 「家族全員で映画館に行けた」という利用者の声
- 約1,000本の映画データベース化によるアーカイブ事業
- 観る側・作る側へのメッセージ
- 「感動をみんなのものに」という目標への挑戦
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- すべての家族に”写真を撮る喜び”を 医療的ケア児・発達障害児にも寄り添う写真館 - 2026年1月20日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【後編】 - 2026年1月12日
- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【前編】 - 2026年1月11日