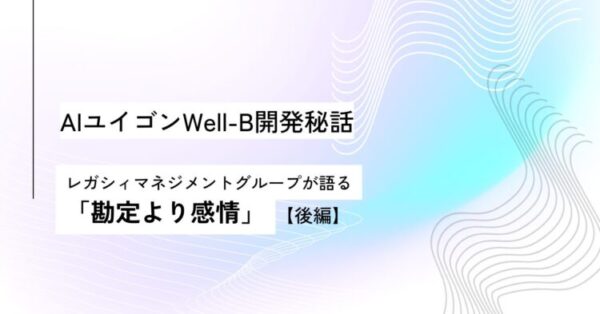前編では、レガシィマネジメントグループが開発した「AIユイゴンWell-B」について、その誕生の背景と「勘定より感情」という理念をご紹介しました。
AIユイゴンWell-B開発秘話|レガシィマネジメントグループが語る「勘定より感情」【前編】
わずか9%という日本の遺言作成率を上げ、「もめない社会」を実現したいという思い。そしてAIだからこそ話せる本音があり、人間と同等かそれ以上にカウンセラーとして優秀だという発見もありました。
しかし、遺言を作成する主な対象となるシニア層にとって、AIやデジタル技術は決して身近なものではありません。「使ってみたいけれど、最初の一歩が踏み出せない」「セキュリティが心配」そんな声にどう応えるのか。
後編では、シニア向けデジタル支援サービス「ワクデジ」の実践から、デジタル遺言における真正性とセキュリティの課題、そして空き家問題や障害者支援といった社会課題へのデジタル活用まで、福祉分野におけるテクノロジーの可能性を探ります。技術と心を両立させる取り組みが、ここにあります。
お好きなところからお読みください
「ワクデジ」が架け橋になる、シニアとデジタルの距離
――天野
私たちが取り組んでいるサービスの一つに「ワクデジ」というものがあります。日頃、私たちもシニアの方々を対応していて感じるのですが、実務的に資料をまとめてお渡しすることはもちろん必要です。
ただ、メールで送った方が良い場合やデータで見ていただく方が良いケースもあって、使える方にはメールで送ったりもしています。
また、私たちは相続のせんせい」というWebサービスも開発しています。このアプリでは相続手続きに関するやり取りができるようになっていて、お客様が戸籍を取得したらスマホで撮影してアップロードしていただければ、私たちが確認して、作成した手続書類等もWEB上でで提供できます。
オンライン上で相続手続きや相続関係の報告・共有ができる、。こうしたシステムは数年前から運用しているんですが、どうしても億劫さが勝ってしまう方もいらっしゃいます。
ある程度やればできるかもしれないけれど、人間はきっかけが大事で、なかなか最初の一歩が踏み出せないものなんですよね。特にシニアの方になればなるほど、その傾向があります。その気持ちは痛いほど分かります。
ですから、私たちがお伺いした際に、「スマホでこうやれば見られますよ、パスワードはこう設定すればいいんですよ、ログインは面倒かもしれませんが入れていくと便利ですよ」こうしたことを丁寧にお伝えしていくことが、シニアの方には大切なんです。
丁寧だからこそ時間もかかりますし、ご自宅に訪問するとなると労力もかかります。でも、そこを惜しまずきちんと行うことが私たちには大事だと考えています。
シニアが増えていくからこそデジタル支援が必要
これからもシニアの方はどんどん増えていく時代ですし、そうした方々が増えるほどデジタル化が遅れてしまっては、日本の国力が衰えてしまいます。
私たちができることとして、訪問してデジタル支援をしていく、スマホの支援をしていく。これを遺言アプリでも実践していこうと考えています。既存の先行サービスで培ったノウハウを、遺言アプリでも展開していくつもりです。
――天野
もちろん、詐欺の問題やセキュリティの問題で社会問題になることも多いんですが、それはやはり何事にもデメリットはあるものです。ただ、メリットの方が大きいと考えています。国としてもデジタル庁で推進していますし。
実際、私たちのお客様の中にも、デジタルをきちんと活用されている方は本当にしっかりやられていて、学びの意欲も高い方は高いんです。そのきっかけが大事だと思っているので、きっかけ作りを社会貢献も含めてやっていきたいと考えています。
デジタル遺言の可能性と課題|真正性とセキュリティの両立
――天野
今回の法務省からの中間試案にも録音・録画機能が一案として出ていましたが、私たちもそれには賛成です。実際の肉声や録画している状況、話し方の表情、身振り手振り。こうした要素があると非常に伝わりやすいと感じます。
ただ、それだけでは伝わらない部分もありますし、誤解を受ける可能性もあるんです。元気がなく見えるから「本当に大丈夫なのか」「本意なのか」と、うがって見られてしまうデメリットも一方ではあります。
ですから、きちんと紙の遺言と、私たちのような専門家やアプリがフォローする仕組み。これが本当に大事だと思っています。段階的にデジタルだけで完結していく形に持っていくことが重要なのではないでしょうか。
偽造への対策|マイナンバーとブロックチェーン
――天野
政府の方でも様々な案を作っていただいているようで、マイナンバーを使った本人確認や、ブロックチェーンを使った認証の仕組み。
この辺りを駆使していけば、デジタル技術の発展とともに遺言の真正性は担保できるのではないかと思っています。
AIの技術はどんどん発展していて、動画や音声で判定していく技術も加速的に進むでしょう。私としては、今後遺言がデジタルに向かっていくにつれて、良い方向に改善していくと考えていますね。
セキュリティと信頼の構築
――天野
懸念点としては、政府の方でもデジタル遺言に関して記載がありましたが、やはり便利な一方で、セキュリティのリスクは非常に高いという点があります。
それを運営する事業者についても課題があります。デジタル遺言では、保管や業務フローにおいて民間事業者にどんどん委ねていこうという案もあるのですが、そうした業務を行う民間事業者には、プライバシーマークへの取り組みや、きちんとセキュリティを担保できる要件を満たしていく必要があると考えています。
安心できるところでないと、特にシニアの方々にとっては不安が大きいと思います。ですから、セキュリティへの不安を解消できるような企業体制、そうした要件を政府として法律でしっかり固めていくと思うのですが、それに則って準拠し、きちんと提供するというコンプライアンス意識。これが大事だと思っています。
ここでも感情を大切にしている
――天野
私たちはここでも「感情」を大切にしています。私たちも企業体ですので、ビジネスとして収益をきちんと確保していかないと運営できないという面もあり、それはすごく大事なところではあるんです。
ただ、それよりもお客様の感情として不信感が出てしまうと、そもそもビジネスにつながっていかないんですよね。
ですから、安心感を与えられるように感情に寄り添い、お客様の声をきちんと聴くことができるよう、セキュリティをしっかり整備する。ここは本当に大事だと実感しています。
――天野
完全に二元論で割り切れるものではないと思っています。数字の勘定と心の感情、技術と気持ち。これはゼロか百かではないんですよね。
技術についても、わかりやすく安心して伝えられるようなコミュニケーション。これは人材開発において本当に大事だと考えています。
私たちも企業の中で人材開発を最重要課題として取り組んでいるのですが、特にシニアの方への説明は、技術と気持ちがうまく混ざった形で伝えないとできないと思うんです。
それを意識した教育が大切だと考えています。
空き家、士業不足、障害者支援|デジタルで挑む社会課題
――天野
私たちは相続・事業承継を専門にやってきていまして、今後も不動産やM&Aといったクロスセルを進めていきますし、デジタルサービスでのクロスセルも展開しています。
実際に相続されたお客様がワクデジというサービスを使っていただいたり、遺言のサービスも新規のお客様だけでなく、既存のお客様でも「お父さんの時は遺言がなかったけれど、お母さんの時には作ってみよう」とか、子供世代の方が「次の世代に向けて、まずはアプリで気軽に作って考えてみよう」という形で利用されています。
今後については、このデジタルサービスに関して様々な開発アイデアがあります。相続分野では遺言の機能を拡張的に増やしていくこともそうですし、ワクデジについてもアプリ化していこうという動きもあります。
それから、日本には様々な社会課題があるんですよね。人口減少に伴って、相続では特に空き家の問題が増えてきています。シニアの方が増えることで、家を維持できないという問題です。
また、私たち士業も人材がどんどん不足していまして、シニアの方々、財産を守っていく士業のメンバーも減少時代に突入していきます。
そこで、士業においてもデジタルによってより効率的にお客様を支えられる仕組みを作る必要があると考えて、士業向けのデジタル化にも注力しています。
それから、障害のある方々に対しても、私たちは相続の仕事をしている時に、特に相続人で障害のある方がいらっしゃる場合、様々な思いがあることを実感しています。
障害のある方が安心して暮らせる社会として、財産をどう考えるか。信託という考え方が日本でも普及してきていまして、成年後見だけでなく、信託も非常に重要な選択肢になってきています。
ただ、まだまだ信託も社会に適応した形で、手間や費用がかかる部分がありますので、そこを払拭できるようなデジタル化が大事だと思っています。
こうしたことも今後、デジタルサービスによってどんどん実現していきたいと考えています。
「未来へのギフト」として遺言を捉え直す
――天野
私たちは今回の遺言アプリもそうなんですが、遺言や相続対策を「死の準備」ではなく、「未来へのギフト」、未来への贈り物として捉えていきたいという価値観の転換を考えています。
ご本人にとっては安心感。「これで一通り自分の使命を果たせた」という思いを持っていただけます。ご家族にとっては争いのない未来が期待できて安心される。本当に安心のためになるものだと思っているんです。
AIを使うことで、誰もが気軽に温かく取り組める文化を作っていきたいと考えています。一見、今回のアプリなども無機的なものに見えてしまうかもしれませんが、私たちとしては「勘定より感情」
数字の勘定より心の感情を大事にして、今後も事業展開を進めていきたいと思っています。ぜひ皆様のご意見、様々なご意見をいただきながら、どんどん前進していきたいと思っています。
AIユイゴンWell-B開発秘話インタビューを終えて
訪問してスマホの使い方を丁寧に教える「ワクデジ」、マイナンバーやブロックチェーンで真正性を担保するデジタル遺言、信託のデジタル化による障害者支援。
レガシィマネジメントグループの取り組みは、単なる業務効率化ではありません。そこには常に「人」がいて、「感情」がありました。
「気持ち、感情にバランスの重心を置くとうまく収まる」という言葉が、すべてを物語っています。技術と心は対立するものではなく、むしろ技術があるからこそ、より深く人の心に寄り添えるのだという確信しました。
数字があってこそ心の安定が得られ、AIだからこそ本音が話せる。そんなパラドックスを、同社は実践を通じて証明しようとしています。
遺言を「死の準備」ではなく「未来へのギフト」として捉え直す。この価値観の転換は、高齢化が進む日本社会全体にとって、大きな意味を持つでしょう。
デジタル化が進む時代だからこそ、「勘定より感情」という原点を忘れない姿勢が、私たちに新しい福祉のあり方を示してくれているように感じます。
2025年10月のAI EXPOでの新機能体験会、11月以降のセミナー開催と、同社の挑戦は続きます。技術と心が融合した、温かなデジタル福祉の未来を、これからも見守っていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
レガシィマネジメントグループ
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- 移乗介助のリハビリにも|自立支援型立位介助ロボット『すくっとたてる君』開発背景 - 2025年12月12日
- 障がいがある方向けの短時間職業体験が育む「働く自信」|志村学園×レバレジーズの挑戦 - 2025年12月4日
- 絵本が紡ぐ、共生社会への想い|絵本作家・由美村嬉々(木村美幸)先生インタビュー後編 - 2025年12月2日