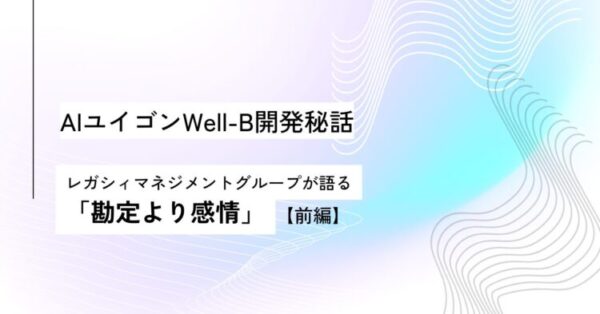日本で遺言を作成している人は、わずか9%しかいません。
欧米では30〜40%に達する国もあるのに、なぜ日本ではこれほど少ないのでしょうか。死をタブー視する文化、心理的な負担、そして「何から始めればいいのかわからない」という戸惑い。遺言作成を阻む壁は、想像以上に高いのです。
ですが今、その壁を取り払おうという動きが始まっています。
相続専門として30年以上の歴史を持つレガシィマネジメントグループが開発した「AIユイゴンWell-B」は、AIの力を借りて誰もが気軽に遺言を考えられるアプリです。政府によるデジタル遺言の法制化も視野に入る中、このアプリが目指すのは「もめない社会」の実現。そして何より
「勘定より感情」
数字の裏にある家族の物語を大切にする姿勢が込められています。福祉の現場でも注目される、相続とデジタルの融合。シニアのデジタル支援から障害者の財産管理まで、新たな可能性が広がっています。
創業61周年を迎えた老舗税理士法人が、なぜ今AIに挑むのか。代表の天野大輔様に話を伺いました。
お好きなところからお読みください
創業61年の相続専門家が挑む、デジタル遺言時代
――天野様(以下敬称略)
私たちはレガシィマネジメントグループという名称で、税理士法人レガシィ、株式会社レガシィ、行政書士法人レガシィの三社等を束ねるグループです。
相続・事業承継を専門として長年取り組んできました。今年(2025年)で創業61周年を迎え、私は三代目の代表になります。
この60年以上続けてきた相続専門の実績を基盤に、最近では関連分野へのクロスセルとして不動産ビジネスやM&Aビジネスといったコンサルティング業務にも注力しています。
そして近年、特に力を入れているのがデジタルサービスの分野です。今日取材のきっかけとなった「AIユイゴンWell-B」をはじめ、シニア層や士業向けのアプリを開発・提供しております。
AIユイゴンWell-Bとは
AIユイゴンWell-Bは、対話形式で遺言書の草案を作成できるAIアプリです。音声入力やチャット機能を使い、AIが優しく気持ちをヒアリングしながら、自然な言葉で遺言草案を作成。作成した草案はPDFで確認・保存でき、いつでも見直しや再作成が可能です。相続専門家による監修で、正式な遺言書作成の準備段階として活用できます。
私の名刺にも記載しているのですが、私たちのビジョンは
「相続日本一で培った知恵とテクノロジーでプラットフォームを作り、50代・60代の人と心が通うナンバーワングループとなる」
というものです。
これまで相続分野で蓄積してきた知見を、近年のテクノロジー、特にAIと組み合わせることで、プラットフォームという形でお客様や社会全体に貢献していきたいと考えています。
遺言作成率わずか9%という日本の現状
――天野
現在、日本の遺言作成率は約9%と非常に低い水準にあります。統計にも表れているのですが、多くの方が遺言の必要性は理解していますし、作りたいという気持ちもお持ちなのですが、ハードルが高いと感じているんですね。
その理由はいくつかあります。主なものとして、死をタブー視する日本人の死生観が大きく影響しているでしょう。
加えて、遺言を作成する過程では義務感や忍耐強さが求められますし、辛い気持ちになることもあります。こうした印象が、遺言作成を遠ざけている要因だと考えています。
ただ実際には、遺言を作成することで達成感を得られる側面もあります。
私たちのお客様の中にも、作り終えてホッとされた方を数多く見てきました。むしろウェルビーイングな状態になられているのではないかと感じています。
身体的、精神的、社会的に良好な状態がウェルビーイングの定義ですが、ご自身の今後や後世の世代について考え、これまでの人生を振り返りながら、どう思いを託していくか。こうしたプロセスは人間にとって非常に大切なことです。実際に作成されて初めて、その意義を実感される方が多いんですね。
遺言を受け取った後世の世代も、その思いを良い形で受け止め、また次の世代へ引き継いでいく。この良いサイクルを生み出すことが重要だと考えています。
欧米を見ても、遺言の作成比率は日本より高く、30〜40%という国も珍しくありません。そこには法整備の違いもあるでしょうし、デジタル化への意識、そもそもの心構えや価値観といったところから変わっていく必要があるのかもしれません。
現在、政府の方でもデジタル遺言の法制化が進んでおり、中間試案が公表されました。ちょうど先日、パブリックコメントの受付が終了したのですが、私たちも意見を提出したところです。政府としてはデジタル化をどう進めるべきか様々な案を検討していて、早ければ来年には法制化される見込みとなっています。
デジタル遺言時代に備える
そうした状況の中で、私たちももともとデジタルに対する意識が高かったこともあり、相続に関する知見を盛り込んだアプリを開発し、デジタル遺言時代に備えようと考えました。
遺言作成率を上げることで「もめない社会」を実現したい――遺言があれば思いがしっかり伝わり、相続トラブルを防ぐための一助となります。
もめることによって大切な財産が失われたり、家族関係が悪化したりすることは大きな損失です。そうならない社会を大切にしていきたいという思いから、このアプリを作りました。
「勘定より感情」|数字の裏にある家族の物語
――天野
私たちは「勘定より感情」という言葉を掲げているんです。数字の勘定よりも心の感情を大事にしようという精神で、お客様対応はもちろん、私たち自身もそう戒めています。
税理士法人として、数字も本当に大切です。計算業務は当然しっかりと行います。ただ、それ以上に重要なのは、お客様が相続や遺言に向き合う際に心を痛められる部分があるということ、そこに寄り添うことなんですね。
家族というのは複雑なものです。良い関係の方もいれば、そうでない方もいらっしゃいます。
それも本人から見た価値観ですし、大事に守らなければいけない家族もいれば、支えていかなければならない家族もいる。その中でどんな気持ちを抱いているかは、本当に当事者になってみなければわかりません。
ただ、そうしたケースを数多く見てきている私たちとしては、プロとしてきちんと理解し、思いをしっかり聞いて、それを届けていく形を作ることが大事だと考えています。だからこそ、その感情を大切にして対応していくことを重視しているんです。
思いをどう引き継いでいくか。遺言というものを、そもそものところから定義し直したいと思っています。
新機能で「見える化」する税負担
――天野
AIユイゴンWell-Bの方で2025年10月に「遺産分割シミュレーション」の新機能がリリースされました。
私たち税理士法人としては、普段から遺産分割、財産をどう分けるかを考えて、その案通りにやった場合に税金がそれぞれどれくらいかかるのかをシミュレーションしてお客様に提供しているんですが、それを無料のアプリ内で簡単にできる仕組みを10月から提供します。
「勘定より感情」と言っていますが、数字の勘定も心の感情に直結する部分があるんです。財産をこう分けた時にこの人にすごく税金がかかってしまう。
だったら、こういった財産ももっと取得しないといけないとか、これだと払えない、土地のみになってしまっているので金融資産も渡さないと相続税が払えなくて、その後大事な土地を売ることになってしまいかねない。そうならないようにするための仕組みです。
10月には最新のAI技術を紹介する『AI・人工知能 EXPO』(NexTech Week 2025【秋】内)に出展し、この遺産分割シミュレーションの新機能を実際に触っていただきながら体験できる場を設けました。
11月以降も、AI遺言に関する説明会やセミナーを随時開催していく予定ですので、相続の事前準備とはこういうものなんだと気軽に体験していただけると思います。ぜひご興味のある方はお越しいただけると嬉しいです。
――天野
数字があってこそ不安が解消できて、余裕を持てるという面もありますので。
――天野
心の安定を得るために、数字というところもきちんと提示して、それも含めて感情的にウェルビーイングになっていただく。
これが大事だと考えています。
――天野
気持ち、感情にバランスの重心を置くとうまく収まるというのが、私たちの知恵としてあります。両方とも同じくらいだと、どうしても数字に目がいってしまうんですよね。
AIだからこそ話せる、隠れた感情と本音
――天野
私たちがこの開発でAIを活用しようと考えたのも、そこが大きな理由でした。
私たちも第三者の立場としてお話ししやすい環境を整えたり、感情に寄り添うことでお話ししやすい雰囲気を大事にしたりしているんですが、どうしても私たちも人間ですから、大切な気持ちの部分を理解できないこともあったり、失念してしまったり。あってはならないことなんですが、気持ちが伝わりにくいということもあります。
その点、AIは知能として非常に優秀なんです。きちんと記憶してくれますし、「こう言っていたことと、こういうことに矛盾があるけれど」と、それをうまく解消できるように促してもくれる。それに、AIだからこそ言いやすいという側面もあるんですね。
「これが漏れてしまったら嫌だな」とか「他の相続人に言ったりしないだろうか」といった不安、あるいは「若いから頼りないな」と思われてしまうこともあるかもしれません。でもAIなら、セキュリティも万全なものにしていますので、安心してお話しいただけます。
カウンセラーとしても優秀なAI
それに、使っていて分かってきたのですが、AIは人間と同等か、それ以上にカウンセラーとして優秀なのではないかと感じています。
人が落ち込んでいる時に励ましてくれたり、本当に一緒に落ち込んで寄り添ってくれたり。人間関係の悩みに対しても、適切に冷静にアドバイスしてくれるんです。
知識面だけでなく、感情面に関しても非常に優秀だと思ったことが、AIを活用したいと考えた理由の一つですね。
――天野
冷静さは本当にあると思います。
AIユイゴンWell-B開発秘話|前半を終えて
相続の専門家として30年以上培ってきた知見と、最新のAI技術が出会って生まれた新しいサービス。レガシィマネジメントグループが描くのは、遺言を「死の準備」ではなく「未来へのギフト」として捉え直す、温かな相続文化です。
2025年10月にリリースされる税負担シミュレーション機能は、その第一歩に過ぎません。今後も遺言アプリの機能拡張、ワクデジのアプリ化、そして空き家問題や障害者支援といった社会課題への取り組みが予定されています。
「気持ち、感情にバランスの重心を置くとうまく収まる」
この言葉が示すように、技術と心の両立こそが、同社が目指す道だと感じました。
後編では、シニアのデジタル支援サービス「ワクデジ」の実践例、デジタル遺言における真正性とセキュリティの課題、そして空き家問題や障害者支援といった社会課題へのデジタル活用について、さらに詳しくお伝えします。福祉分野とテクノロジーの新たな接点を、ぜひご覧ください。
AIユイゴンWell-B開発秘話―レガシィマネジメントグループが語る「勘定より感情」【後編】
久田 淳吾
最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)
- 移乗介助のリハビリにも|自立支援型立位介助ロボット『すくっとたてる君』開発背景 - 2025年12月12日
- 障がいがある方向けの短時間職業体験が育む「働く自信」|志村学園×レバレジーズの挑戦 - 2025年12月4日
- 絵本が紡ぐ、共生社会への想い|絵本作家・由美村嬉々(木村美幸)先生インタビュー後編 - 2025年12月2日